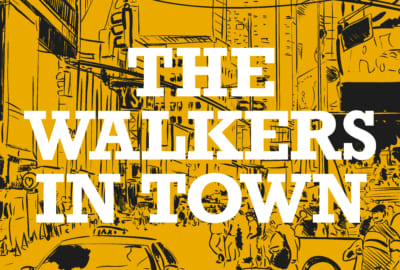1年の締めくくりである12月。さまざまな媒体や個人から、その年のカルチャーの動きや今後の動向についての見解が、いつにも増して発信される時期でもある。そんな折、EYESCREAM編集部から連絡が届いた。2018~2019年にかけてのドメスティックなロック・シーンについて話がしたいとのこと。早速打ち合わせに向かうと、息付く暇もなくああでもない、こうでもないと各々の考えが飛び交う。そんななか頻繁に出てきた2つのキーワードがある。“何かにとって代わるもの”、“型にはまらないもの”という意味を持つ“オルタナティヴ・ロック”と、音楽をさほど聴かない人でも、近年、ファッション方向で耳にしたことがあるであろう“グランジ”という言葉だ。
グランジの誕生と、時代がひっくり返った瞬間
では、そもそもロック・カルチャーにおける“オルタナティヴ”、“グランジ”とは何なのか。話は1970年代の中期にまで遡る。1950年代にアメリカで誕生したロックンロールは、時を経てさまざまな方向に派生、発展していった。1970年代に入ってからは、より技巧的なサウンドや、高価な機材を用いた精巧な音楽性に傾倒していく流れが激化していったことに対して、ロックンロールがもともと持っていたプリミティヴなエッジを取り戻そうという動きが起こる。ラモーンズやパティ・スミスといった、独自のスタイルを確立していたバンドやアーティストがいたニューヨークのエネルギーが海を渡ってロンドンに。1976年秋にセックス・ピストルズがリリースしたシングル「Anarchy In The UK」やダムドの「New Rose」が火付け役となり、パンク・ムーヴメントが巻き起こる。
しかし、パンクは1978年にセックス・ピストルズが解散したことで、1980年を迎えるまでには沈静化する。とは言えその文脈が切れたわけではない。パンクがこじ開けた扉の先には、ニューウェーヴ、ポストパンクと呼ばれる、さまざまなジャンルの音楽を独自のやりかたで積極的にミックスするバンドが登場したり、これまでのロックにはなかった不穏でダークな世界観を持ったバンドが人気になったりといった、新たな動きが生まれる。
そんなニューウェーヴにも、やがて産業化の波が押し寄せアイドル的な人気を持ったバンドも多く出てくるようになる。そこで、DIY性の高いアメリカを中心としたバンドを指して“オルタナティヴ”という言葉が使われるようになった。また、“オルタナティヴ”同様、音楽を活字で追うとよく出てくる“インディー”も、パンクからの一連の流れのなかで、広く使われようになった言葉で、こちらは非ロック的なものやイギリスのイメージも強い。
しかし現在、ロックの歴史を振り返って使われる“オルタナティヴ”は、大筋は変わらないものの、いささか背景が異なる。そこで語るべきが“グランジ”だ。MTVの発信するポップスや、ショウアップされたハードロックやヘアメタルといった音楽が隆盛を極めた1980年代。それらへの反旗として、パンクやポストパンク、先に述べたオルタナティヴやハードコア、1960年代~70年代のガレージロックや創成期のハードロックなど、挑戦的な初期衝動に満ちた音楽からの影響を受けたバンドが多く出てきた、アメリカはワシントン州のシアトルを中心としたシーンに注目が集まる。その荒々しいサウンドやラフなファッションから、“汚い”を意味するスラングを語源とした“グランジ”という言葉が生まれた。簡単に言えば二次パンク的なものである。
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
そしてグランジは、1991年に大きなバズを起こす。ニルヴァーナの2ndアルバム『Nevermind』が全米ビルボード・チャート1位に、パール・ジャムのデビュー・アルバム『Ten』は同チャート2位に、サウンドガーデンの3rdアルバム『Badmotorfinger』はグラミー賞にノミネートされるなど、まさに時代がひっくり返った瞬間がそこにあったのだ。ニルヴァーナをプッシュした先輩、ソニック・ユースのサーストン・ムーアはこの年の出来事を「Years Punk Broke」と呼び、のちに同タイトルの映像作品も発表されているので、ぜひ観てもらいたい。また、グランジ関連の映像作品となると、その勃興からシーンの最重要人物、ニルヴァーナのカート・コバーンの死までの動きを追ったドキュメンタリー作品『hype!』もおすすめだ。
オルタナティヴとは、既存の商業ベースに捉われない“新しい価値観”
“グランジ”は若者のファッションにも大きな影響を与えた。パンクとグラム・ロックを混ぜ合わせてさらに上塗りを重ねたような、ハードロックのファッションやサウンドを、“けばい”、“ダサい”の象徴として化石扱いするような流れが生まれ、オーバーサイズの擦り切れたジーンズ、くたびれたTシャツやネルシャツが大流行。ここ日本でも一大古着ブームとなった。余談だが、破れたジーンズを部屋に置きっぱなしにしていたら、おばあちゃんに変なアップリケを付けられた、という話はいわゆる“あるある”だ(笑)。
そういった流れがあって、現在一般的によく使われる“オルタナティヴ”という言葉は、1990年代以降のことを指す場合が多い。レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンやベック、ペイヴメントらはその代表的な存在。それ以前から活動していたREM、ソニック・ユース、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ビースティ・ボーイズらもまた新たに脚光を浴びることになった。
彼らの作品を聴いたことがある人ならわかるように、“オルタナティヴ”は明確なサウンド・スタイルを示すものではない。レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンは強烈なインパクトを持ったギターサウンドやリフに、それまでのロックらしい歌メロではなく終始ラップが乗ったメッセージ性の強い音楽。ペイヴメントはそれと対極にあるような、ゆるい脱力系ポップ。ベックは曲単位、作品単位でぜんぜん色が違う。にもかかわらず、オルタナティヴという言葉は、さまざまな文献で頻繁に落としどころとして使われている。ゆえに、筆者も「オルタナ・バンドをいくつか聴いてみたものの、さっぱりわからないんですけど……」という質問をよく受ける。
Rage Against The Machine – Killing In the Name
Pavement – Cut Your Hair
では、オルタナティヴとはいったい何なのか。言葉にするなら既存の商業ベースに捉われない“新しい価値観”だと考えてもらえればわかりやすいだろう。売れるためだけに音楽をやれば局地化して飽和する。そもそも選択肢は一つ二つじゃない。そのなかで実験的なことをやるのか、とことんシンプルなバンドサウンドにこだわるのか、もはや音楽ではないのか。そこまで包括した自由な表現、ということだ。なので、本記事はロックの文脈でそれを語ってはいるが、オルタナティヴという言葉は、たとえばヒップホップやR&Bにも存在する。現在隆盛を極めるヒップホップ・アーティストたちの多くは、もはやヒップホップやラッパーという呼称すら取っ払った独自の概念のもとに活動している。
参考記事:
ラッパーはロックスター? トラヴィス・スコットを軸にサウスシーンを探る
となると、もはやロックがどうとかヒップホップがどうとか、そういう話はどうでもいいということで、本末転倒してしまいそうなところだが、そうではない。そもそもルーツや趣味嗜好は人それぞれ。逆にオールドスクールなやり方をとことん追求するのも、そこに何滴、今の要素を垂らすのかも自由。遠く離れたインターネット仲間と曲を作るのも、教室の隣に座った友達とバンドを組むのも自由だ。
ミツキやスネイル・メイル、スーパーオーガニズムの活躍
ドメスティック勢も新たな局面へと
そんななかで、ひとつのニュースが入ってきた。世界で最も影響力のあるメディアの一つとされるPitchforkが発表する年間ベストアルバム企画の2018年版で、オルタナティヴ・ロック畑のシンガー・ソング・ライター、ミツキの『Be The Cowboy』が1位、スネイル・メイルの『Lush』が5位に選ばれたのだ。もともとインディー寄りだったPitchforkではあるが、ここ4年間の1位は、ケンドリック・ラマーが2回、ソランジュ、ラン・ザ・ジュエルズとヒップホップ/R&B勢が続いていたことを考えると、実に興味深い出来事だ。
Mitski – Nobody (Official Video)
ほかにも、フランク・オーシャンがフックアップしたスーパーオーガニズムは、日本でもTVコマーシャルで楽曲が使われお茶の間にまで響いた。それぞれのやり方でパンクの進化を体現したアイドルズやシェイム、キャッチーで人懐っこいキャラクターとローファイなポップサウンドで人気を博すハインズ、60年代や70年代の豊かなポップの実りを独特のユーモアで消化したレモン・ツウィッグス、ガレージやパンクのエネルギーをブチ切れたパフォーマンスで放出するスタークロウラーら、過去へのリスペクトを以て今だからこその音を鳴らすバンドたちが、素晴らしい作品を続々とリリースしたことも重要なポイントだ。2018年はオルタナティヴ・ロック/インディーにとって、明るい兆しのみえた年と言っていいだろう。
そして今、ドメスティックなオルタナティヴ・ロック/インディー勢の動きも、確実に新たな局面に突入する予感に溢れている。この10年ほどで急激にガラパゴス化していった国内アーティストだけが出演するフェスは今現在、100をゆうに超える数に上る。そもそもは、各々がカッコいいことをしているアーティストたちがその場に呼ばれるはずのフェスが、むしろアーティストの主な活動拠点となり、とにかく初見の人たちの足を止めるために、性急なノリ重視の曲とやたらと盛り上がりを煽るMCがテンプレート化してしまった。それによって、オーディエンスの画一的なノリは今に始まったことではなく取り立てて否定するものでもないが、そこに自由のあったロックまでもが、みんなで同じように楽しむ音楽になってしまった。
とは言え、そういったシーンとは関係のないところで、ぶれることなく独自の進化を遂げていったバンドも多く存在し、2010年代の初頭には、そのカウンターと言えるような若手のバンドが台頭してくる。HAPPYやthe fin.、YOGEE NEW WAVES、never young beach、Suchmos、GLIM SPANKY、DYGL、CHAIらの登場は、その代表と言っていいだろう。彼らのうちの何人かは、ライブのMCでも、決して声を荒げることなく「自由に楽しもう」とよく話す。
2018年もまた、新たにロック・シーンをかき回してくれるであろうアップカミングなバンドたちが頭角を現した年だった。インディー・ロックからそれと相反するニューメタル的なダイナムズムまでをも感じさせるNewspeak、色気たっぷりのホワイト・ノイズと麗しいメロディーを響かせるLuby Sparks、00年代のロックンロールやパンク・リヴァイヴァルの空気をたっぷり吸い込んだNo Buses、演奏下手な自分たちでもDIYでできることを追求するTENDOUJI……、と綴っているだけでもワクワクして仕方がない。
“ネオ・グランジ”という切り口で
2018年と今後の国内シーンを読み解く
さらに2018年が面白かったのは、国内における10年代のオルタナティヴ・ロック/インディーの潮流にはなかったテイストのサウンドが聴こえてきたということ。パンクやグランジの攻撃性や、90年代のアメリカン・ストリート色の強いオルタナティヴ・ロックのテイストを持ったサウンドが、時代の前に躍り出ようとしている予感がするのである。断っておくと、オルタナティヴ/グランジのムーヴメントからもう約30年が経過しているわけで、当時を思わせる懐かしいサウンド、というわけではない。あの頃のスタイルや闘争的なエネルギーを踏襲しつつ、今を感じさせる“ネオ・グランジ”とでも呼びたくなるような(既にカルチャー色を薄めたライトなファッション記事で使用されている言葉なので若干の抵抗感は持ちつつ)ものだと捉えてもらえるとありがたい。
w.o.d. – 丸い真理を蹴り上げて、マリー
まず紹介するのはこちらのバンド。ヴォーカルのサイトウタクヤがカート・コバーンよろしくなパジャマ・シャツ姿ということもあって、思いっきりグランジを感じる。その真意はわからないが、これをもってグランジと呼ばれることすら嘲笑っているかのような、皮肉めいたパンクなエネルギーを感じるところもまた、一周してグランジを感じる。昨年アップされた「スコール」のMVはオルタナティヴ・ロックのルーツにあるキュアーへのオマージュたっぷり。そういったちょっといけすかない雰囲気と音楽的懐の深さに、激クールな日本語メロディー。カッコいい。
SESAME // VAMPIRE BOYS [OFFICIAL MUSIC VIDEO]
SESAMEは、イギリスのマッドチェスターやブリットポップなどのインディーに寄った音ではあるが、本人たちも“ブリットなグランジ”と話しているように、グランジから受けた影響も大きい。またそのDIYなド派手な髪型、メイクやファッションにも注目。ヴォーカルのHiyokoはフットボールとインディーを感じさせるアディダスやアンブロ、今をときめくパンクでヒップホップなRAT BOYばりのバーバリーチェックなど、シンボリックな何かをコーディネートに混ぜているところもにくい。彼らのいるところ個性的な人間が集まる。そんな新しい世界が誕生する予感。
ステレオガール – GIMME A RADIO
サイケデリックやオルタナティヴ・ロック/インディー、ほかにも音には聞こえてこないさまざまな背景をポップに不思議に折衷するセンス。そして飄々とした歌い方でそんじょそこらのポップスなんて蹴散らすほどのメロディー。キャッチ―だが一切の媚びを感じない、クールで不思議な佇まいのなかにパンクが内包されている気がしてならない、ステレオガール。メンバー全員がまだ10代ということで、これからがかなり楽しみだ。
あっこゴリラ – GRRRLISM
脱線しすぎだという声は百も承知。しかしこの曲のタイトル、彼女の着ているTシャツにある“GRRRLISM”という言葉の綴りを見てほしい。これはグランジと同時期に起こった女性蔑視への抵抗であるパンク・ムーヴメント“RIOT GRRRL”へのオマージュだ。そしてRIOT GRRRLの象徴であるビキニ・キルのメンバー、トビ・ヴェイルが使っていた“Teen Spirit”というデオドラントの匂いがカートにも移っていると、同じくビキニ・キルのキャスリーン・ハンナが落書きをしたことは、ニルヴァーナの代表曲「Smells Like Teen Spirit」の曲名の由来になっている(当時、カート・コバーンとトビ・ヴェイルは付き合っていた)。あっこゴリラ自身も、パンクやオルタナティヴ・ロック好きは公言している。そうしてカルチャーは繋がっていくのだ。
ニトロデイ「青年ナイフ」Music Video
そしてニトロデイのフロントに立つ小室ぺいのファッション。カーディガンに好きなバンドのTシャツ(しかもG.B.H.)にジーンズときたら、w.o.d.同様、これまたカート・コバーンを思い出す。サウンドやメロディーは、ニルヴァーナというよりはピクシーズやサニー・デイ・リアル・エステイトのようなエモや、ポウジーズのようなパワーポップ寄りのオルタナティヴ・ロックなどのバンドからの影響が混ざり合っているように感じる。彼らもまだ10代。これだけシンプルで味わい深いサウンドを鳴らしていることに胸を躍らせていたところに、ちょうど新作がリリースされたという話題が届いた。
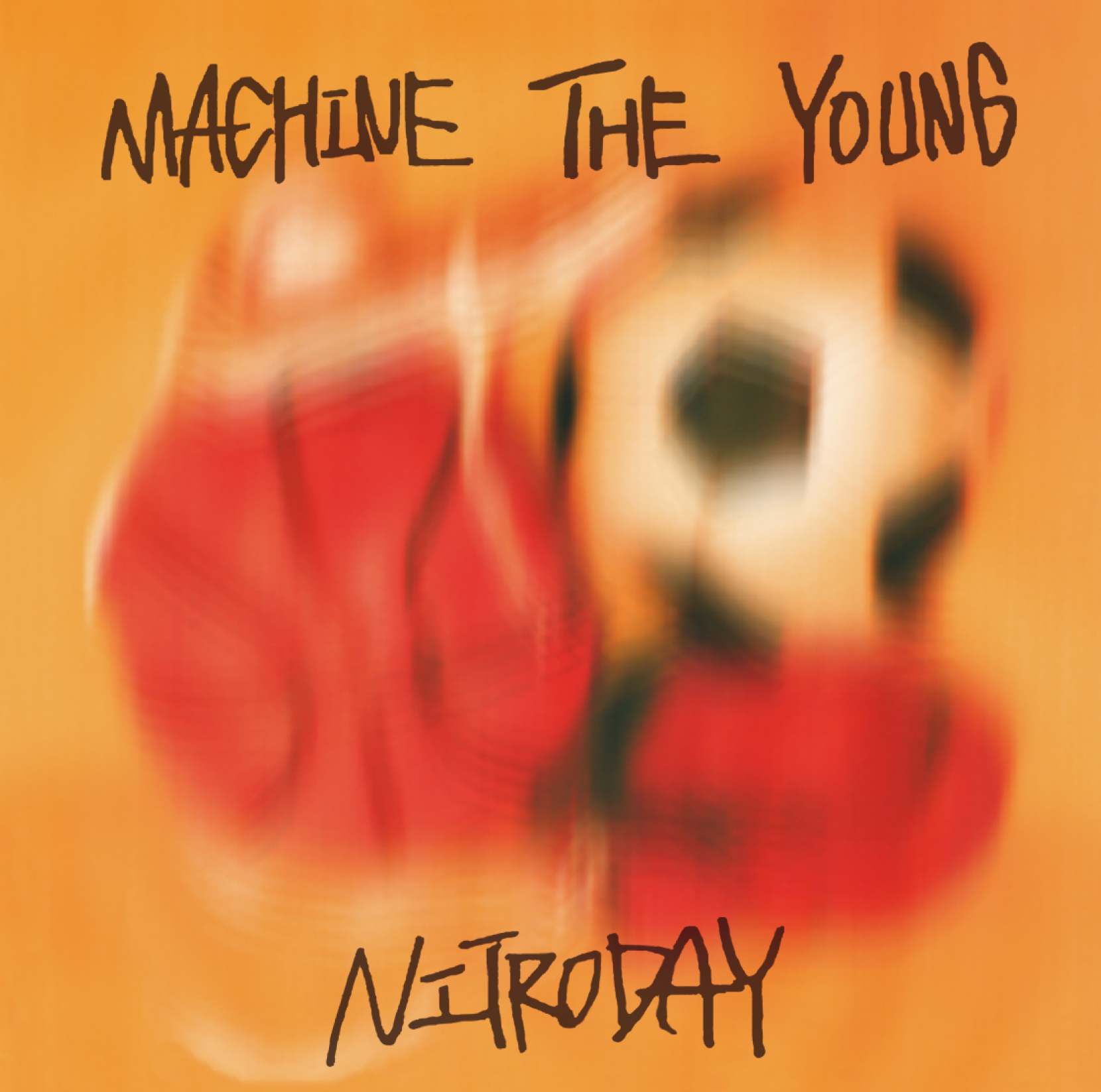
ニトロデイ『マシン・ザ・ヤング』
2018.12.05 RELEASE
理屈抜きに“これぞロック”だと感じさせるオールドスクールの持つ普遍性。オルタナティヴ・ロックやパワーポップ・フリークっぷり。ドメスティック・ロックに宿る情熱。フラストレーションや希望が渦巻く日常。きっと彼らにしかわからない真実。さまざまな生々しいエモーションが内包された、“バンドってめちゃくちゃカッコいい”ということを、某お笑いのネタじゃないが、細胞レベルで実感できる作品だ。
ニトロデイ “ジェット” (Official Music Video)
さまざまな情報が凄まじいスピード感で交錯する昨今。ひょんなことから予期せぬ何かがブレイクする可能性も大いにあると同時に、本来人々の目に留まるべきポテンシャルを持ったものが、誰にも気付かれることなく通り過ぎることもある。そんな時代だからこそ、ここに紹介したような、周囲の波にまどわされることのないプリミティヴなサウンドや主張を持ったバンドやアーティストの作品を手に取ってみることが、もっとも面白い時期に来ているのかもしれない。新時代のオルタナティヴ・ロック/グランジが今後、時代に何を残すのか、引き続き追っていきたいと思う。