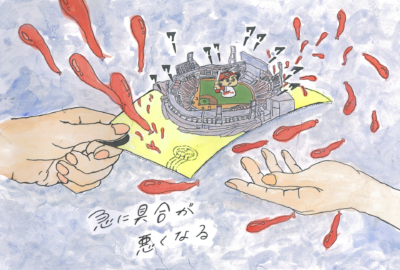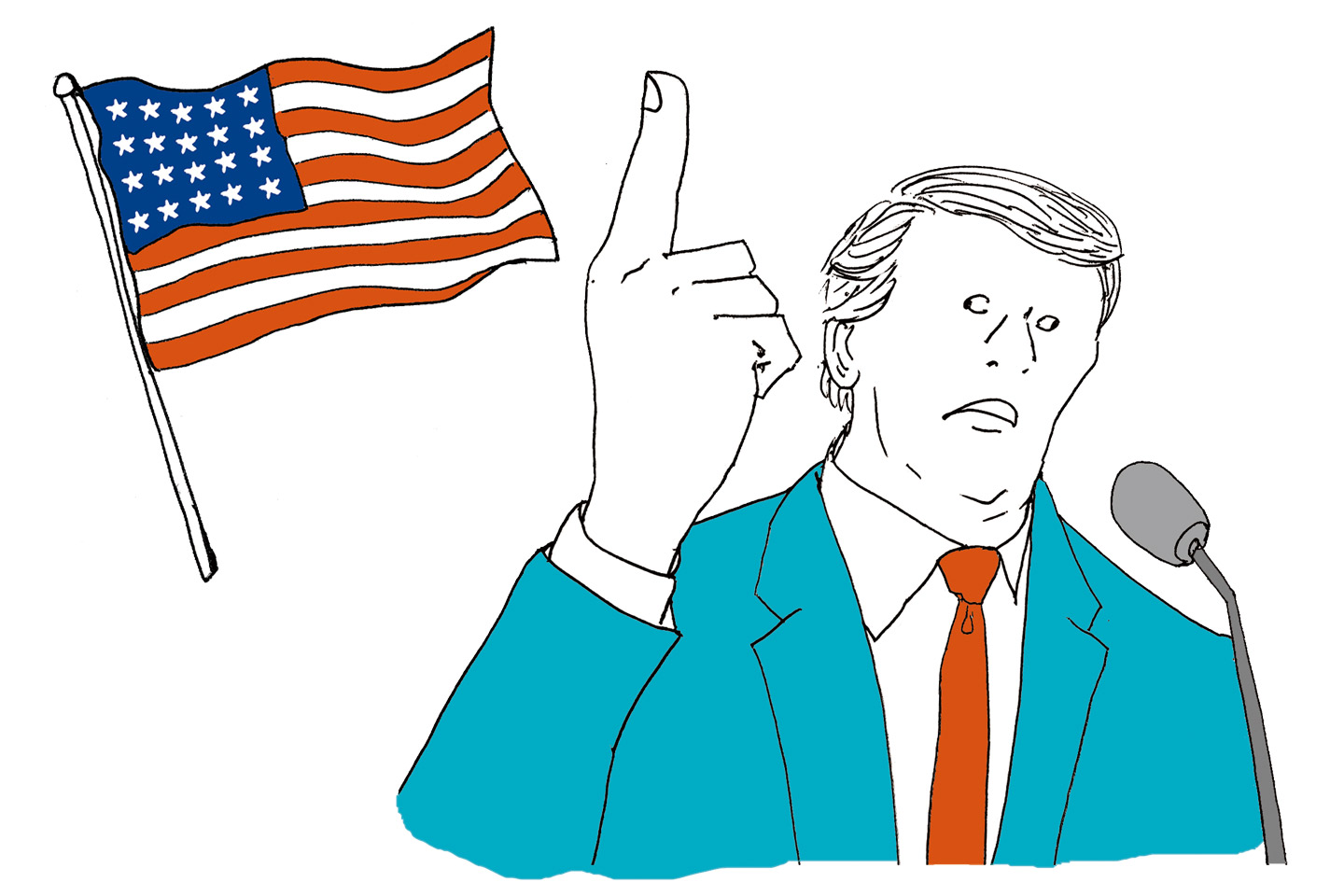
現在発売中のEYESCREAM12月号では、テン年代のアメリカ文学に注目。先日トランプ大統領が、初来日を果たしたとあって本誌の内容をピックアップ。
いま一番関心の集まる話題からみる文学とは。
トランプ時代がやってきた。しかも、フェイクニュースなる〝フィクション〞を引っ提げて。
文学もまた、闘いの舞台になる。ステートメントを掲げて、SNSを駆使して、ライムを刻んで……
〝自分たち〞の物語とは何かという問い掛けを巡って。
前々夜:1998年
~トランプ時代のアメリカ文学~
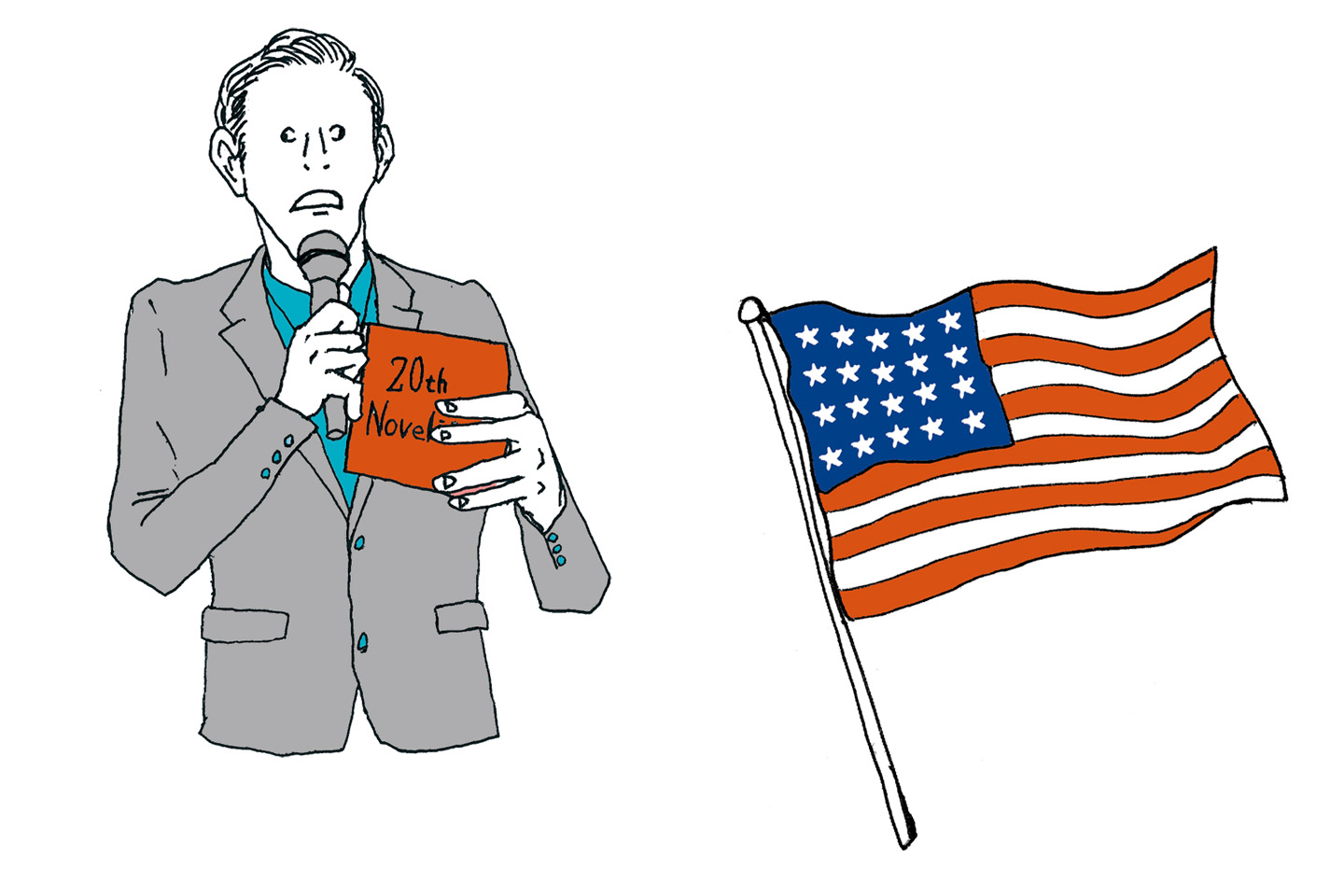
(咳払い)「紳士淑女のみなさま、本日はご参集いただきまして光栄に存じます」
(万雷の拍手)
「このたび、私どもモダン・ライブラリー社は、20世紀の偉大な小説トップテンを作成いたしまして」
(一同どよめく)
「本日の発表に至ったわけでございます」
(拍手と歓声)
「それでは準備よろしいでしょうか」
(いっせいに)「YES!」
「10位。『怒りの葡萄』ジョン・スタインベック」
「おお! ブルース・スプリングスティーンも取り上げたあの小説!」
「9位。『息子たちと恋人たち』D・H・ロレンス」
「おおっと、愛に生きた男ロレンス!」
「8位。『真昼の暗黒』アーサー・ケストラー」
「やべえ、読んだことない」
「7位。『キャッチ=22』ジョーゼフ・ヘラー」
「ヘラー最高! 異議なし!」
「6位。『響きと怒り』ウィリアム・フォークナー」
「高校の授業でがんばって読んだけど、わからんかった」
「5位。『すばらしき新世界』オルダス・ハクスリー」
「21世紀に向けてのディストピアものですねわかります」
「4位。『ロリータ』ウラジーミル・ナボコフ」
「映画化2回!」「発禁処分!」「言葉の美!」
「いよいよトップ3でございます。みなさま心の準備はよろしいでしょうか」
「あと出てないの誰だっけ」「オーウェルでしょう」
「アトウッドは?」「サリンジャーだって!」
「3位。『若き芸術家の肖像』ジェイムズ・ジョイス」
「そうか、ジョイスは外せないか」
「けっこういい青春小説だった気が」
「2位。『偉大なるギャツビー』F・スコット・フィッツジェラルド」
「永遠のギャツビー!」「忘れててごめん!」
「そして1位は……」
(一同固唾を呑む)
「1位。『ユリシーズ』ジェイムズ・ジョイス」
「金字塔! 異議なし!」
「ちゃんと読了した人いる?」
「ジョイス二つ?」
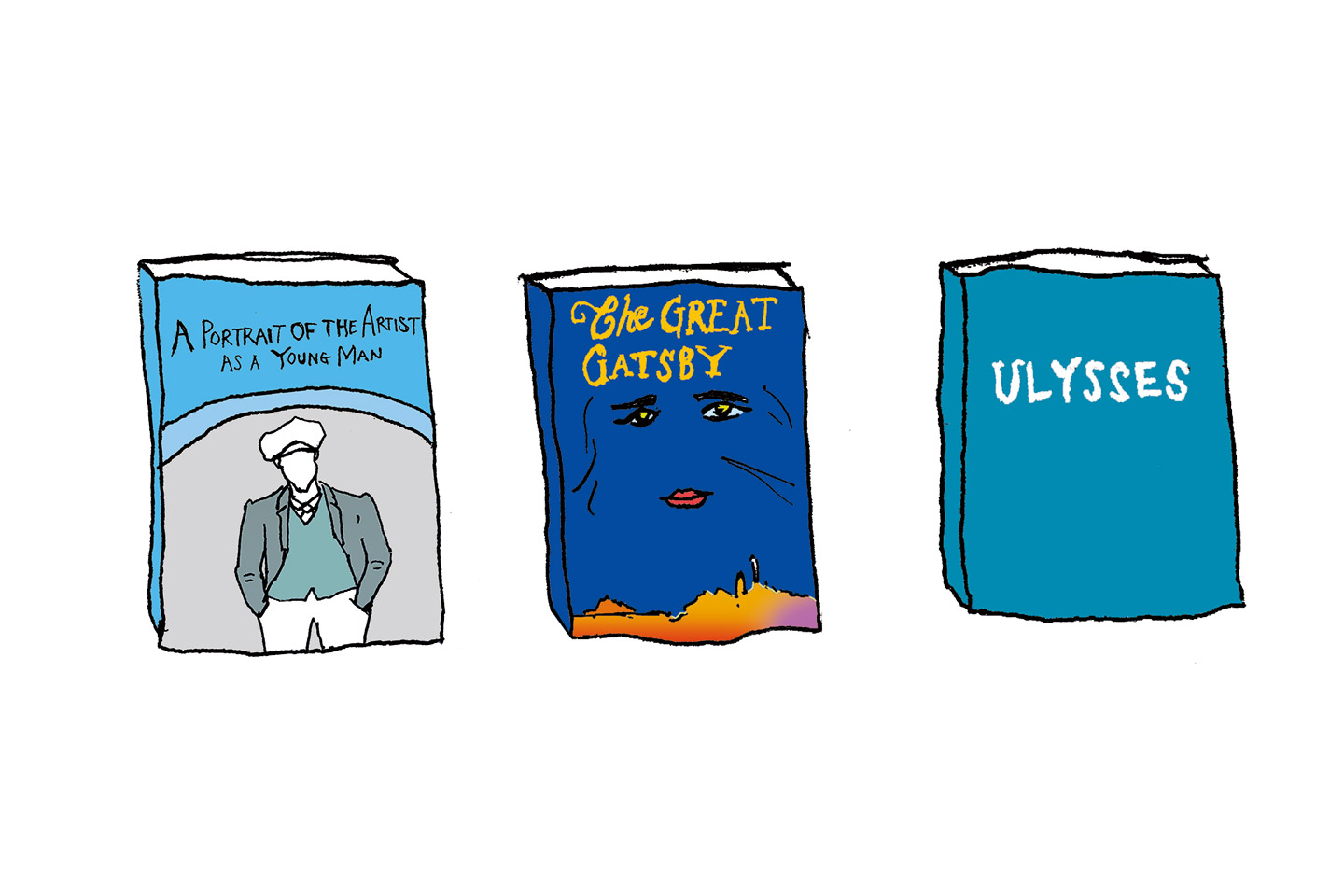
「いかがでしたでしょうか」
「なんか納得できないんですが」
「いや、編集会議で決めましたもので」
「それって誰が決めてるんですか」
「誰なんだよ」
「作家のウィリアム・スタイロン氏も入っておりますし、
歴史家のアーサー・シュレシンジャー氏もおられます」
「強そうな名前だ」「でも偏ってません?」
「そこは有識者が意見を戦わせた結果ですから、
そういうものとして受け入れていただければ」
「ピンチョンは?」「カミュとか」
「『百年の孤独』は?」「カフカは無視ですか」
「ベケットを外す理由がわからない」
「私は一介の司会者ですので、そのへんはなんとも」
「英語圏限定なら最初からそう言ってほしかった」
「その批判はまったくあたらないかと」
「全員男の作家なんですけど、女性作家はノーチャンスってことですか?」
「先進国の自己満企画だったか」
「……」
「なんだか日本の与党政治家みたい」
「一般読者の意見は無視するの?」
「民主主義の国なんだから我々だって一票を」
「わかりました。じゃあ一般の投票も募ります。
文学の対話ということで」
(一同)「YES!」
<「それでは、一般投票結果を発表します」
(有識者一同拍手)
「よろしくお願いします」
「10位。『フィアー:恐怖』L・ロン・ハバード」
(一般席中央前方が異様に盛り上がる)
「ん? 誰? その小説は何?」
「SF作家だそうです。
新興宗教サイエントロジー創始者の作品です」
「ええと……小説としての完成度とかは?」
「投票結果ですから。あと9作品あるから急ぎますんで」
「9位。『ミッション・アース』L・ロン・ハバード」
「また同じ人?」
「読んだ人と読んでない人の熱量の差は認めます」
「一票の尊さを否定してはならない」
「超大作らしいけど、信徒の人以外が読んでいる気配を感じないが」
「組織票が入ったとしか思えない」
「8位。『われら生きるもの』アイン・ランド」
(一般席右側が異様に盛り上がる)
「今度は誰なんだ」
「思想家だとか」「小説家じゃないってこと?」
「あなたたちだって小説に思想を求めるじゃないですか」
「7位。『アンセム』アイン・ランド」
「また複数エントリーじゃないか」
「ジョイス二冊で叩かれた我々って一体」
「6位。『1984年』ジョージ・オーウェル」
「知っている作家だ!」「これで安心できるな」
「さっきまでのは何だったのか」
「5位。『アラバマ物語』ハーパー・リー」
「人種問題は一大テーマですから」
「そういえば『ビラヴド』を選び忘れてた」
「でも、こちらのリストもアメリカ人だらけでは?」
「何をいまさら」「我々はアメリカ人ですから!」
「4位。『指輪物語』J・R・R・トールキン」
「実は私もけっこう好きで」「我が家も愛読していて」
「3位。『バトルフィールド・アース』L・ロン・ハバード」
(再び熱狂する客席中央前方)
「同じ人が三冊目とはこれいかに」
「映画化してコケたのでは」
「それなら聖書とかクルアーンが入るほうが安心できるが」
「それは今から2年後の話なので」「20世紀のバイブルなんすよ」
「2位。『水源』アイン・ランド」(打って変わって熱狂する客席右側)
「こちらも同じ作者三冊目……」
「共和党コアな支持者のバイブルだそうです」
「宗教と政治信条に乗っ取られたか」
「そもそも有識者の投票も組織票の一種じゃないですか」
「1位。『肩をすくめるアトラス』アイン・ランド」(狂喜乱舞の客席右側)

「プロへの反感がこうも露骨に出るとは」
「対話のきっかけはどこに……」
「あれ? サリンジャーは?」
「二人の作家から七冊選んじゃったぞ」
「でも民主主義ですから」
(有識者一同退場)