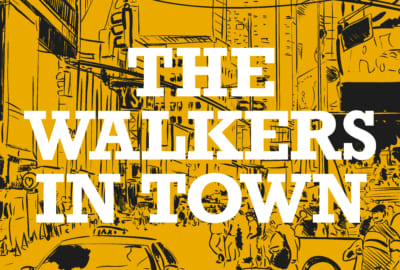蓮沼執太は多忙である。この数年をざっと振り返っても、2019年には野外フェスへの出演を皮切りに、野音でのワンマン、銀座でのゲリラライブとつづき、コロナ禍で拠点を日本に戻してからも、スパイラルホールでの配信ライブ、オーチャードホール公演、1年おくれの東京2020パラリンピックでは開会式に登場したかと思えば、2022年の恵比寿ガーデンホール公演を成功に導いている。これはおもに現場(ライブ)での活動の軌跡だが、同時並行的に進行していた楽曲~作品制作の成果も陸続とかたちになりつつある。今回のインタビューでは蓮沼執太フィル名義での2018年の『アントロポセン』以来となる、3作目『シンフィル』を中心に、蓮沼執太の創作の背景と原点に迫った。


―なにかにとりつかれているのかと思うぐらいの働きぶりですよね。蓮沼執太フィル名義の新作『シンフィル』を出したそばからソロ名義での『unpeople』をリリースし、関連した企画展を開催する。八面六臂のご活躍の秘訣を新書にでもまとめればいいのにと思いますよ。『失敗しない時間の使い方』みたいな。
蓮沼: いやいや(笑)。
―『シンフィル』の制作と相前後して、蓮沼さんご自身にも環境の変化があったとうかがっています。
蓮沼: 2019年の野音での蓮沼執太フィルのライブの前後のことです。コロナやブラック・ライブズ・マターがあった年の冬のことで、ニューヨークの友だちも引っ越していっちゃって、どうしようか、とりあえず僕も戻ろうという感じでした。ちょうどニューヨークと東京を行ったり来たりする活動スタイルにも飽きてきたこともあり、フィルの野音も終わり、よかったねといいつつ、次どういう方向性にしようかと考えていた時期だったので自然とそうなったともいえます。なにかがいったん終わって、また次、なにかをしたいなという感じでした。
―その時点で『シンフィル』の楽曲にとりかかっていたんですか。
蓮沼: ここに入っている曲をつくりはじめるかどうしようかな、というタイミングですね。
―いまさらうかがうのもなんですけど、蓮沼さんは音楽をどうやってつくっているんですか。つくっているという自覚もないままに楽曲ができているんですか。
蓮沼: そんなわけないじゃないですか(笑)。意識してつくっていますけど、フィルの場合は僕だけが演奏するわけではなくて、メンバー15人のために。15分の1、そうやってみんなで演奏するようにということなので作り方がそもそもちがいます。きちんと楽譜書かないと弾いてくれないですし。アルバムを3枚出してきたことで、僕なりのフィルの作り方みたいなのもできあがってしまっているところもあるんですが。
―フィルとソロではまったくちがう?
蓮沼: 「もはやちがう」といったほうがいいかもしれないですね。昔はあんまり差別化もせず、ほぼ一色でやっていましたけど、もうだいぶちがいます。ただ『シンフィル』では凝りかたまった作り方をさらに変えようというようなステップがあったので、ちょっと特殊です。
―蓮沼執太フィルの魅力のひとつは譜面や楽器編成に由来するサウンドだと思いますが、『シンフィル』は歌を意識された作品だと思いました。そもそもどういうきかっけでつくりはじめたんですか。
蓮沼: フィルは定期的というほどではないにせよ、ライブをつづけているんですね。みんなで集まって演奏すると楽しいんですね。楽しいと未来の話になり、メンバーのイトケンさんあたりがアルバムとかつくろうと提案があったりするんですよ。いやぁ、つくるとお金かかるしなぁ、とも思うんですが、まあやりましょうみたいなことになって、たとえば1曲1時間、何楽章かにわけて、インストでいろんな展開をする楽曲をつくる方向性もあるし、ポップス風のコンポジションでプレゼンテーションする方向性もある。どっちにしようかな、と考えてそっちを選んだ結果が『シンフィル』ということですね。
―後者を選んだ理由はなんだったんですか。
蓮沼: まずはどんな感じがいいんだろうと、いろんな人と話しました。やっぱり聴いてもらえないと音楽にならないというのがあるし、インストで1時間すごく巧みなことをやってみんなに聴いてもらえるか、となったときに少し開いていそうなほうを選んだという感じですね。
―社会的な変化や政治的な分断とか、外的な因子も影響している部分はあるのかしら。
蓮沼: 直接的な影響はないとは思うんですが、グループという集団そのものが社会みたいなものなんですね。今回も、物理的な面を考えても、コロナ禍で集まるなと政府や社会からいわれているから、レコーディングできないし、そもそもスタジオにも入れない。レコーディングしているときでも、風邪気味のひとがひとりいるだけで、敏感なひとは「マジで来るなよ、家でお大事にしてて」と思うメンバーも居るかもしれない。それってそのときの社会で実際に起こっていたことですよね。


―『シンフィル』ではどの曲が最初に完成しました?
蓮沼: 「HOLIDAY」でした。それは物理的にその曲を最初に作るきっかけがあったから。曲をつくってください、というコミッションだったんですね。2020年の冬かな。ただその時点ではアルバムのための曲ではなかったです。アルバム用では「Eco Echo」。「呼応」も最初のほうに作りました。
―キーになる曲を最初に録ったんですね。
蓮沼: そうですね。
―曲として強いもの。シングルの集合としてのアルバムのイメージだったんですか。
蓮沼: つくっている側としては、そうは思っていなかったんですけど、そういった感想もよく耳にしました。でも迷っていましたよ。方向性で迷っていたというよりは、レコーレィングの期間が結構間空いたんです。いちど2021年にスタジオに入って、次に入ったのはその1年後でした。
―コロナ禍でレコーディングも進んでなかったんですね。
蓮沼: 配信ライブはやっていましたけどね。ライブはできそうなタイミングのときに、差し込んでいった感じでした。文化村オーチャードホールでのフィルの公演もその時期ですね。ライブ中に3回目の緊急事態宣言が出されました。その反面、レコーディングは休んでいました。
―コロナ禍での配信や無観客ライブの経験が『シンフィル』に反映している面はありますか。
蓮沼: たとえばアルバムに入っている「#API」という曲はスパイラルでの配信ライブのときにつくった曲で、アルバムにも収録しました。形式的なことでいえば、フィルはいままでフィーチャリングという客演をしてなかったんですね。環ROYさんにラップしてもらうにせよ、キノピー(木下美紗都)に歌ってもらうにせよ、バンドにボーカルが内在していたんですね。それが『シンフィル』では「HOLIDAY」で羊文学の塩塚モエカさんに入ってもらったり、「#API」ではxiangyuさんに客演してもらったり、われわれが今までやっていないことやってみたという側面が『シンフィル』にはあるんですね。
―「共在」や「回復」がアルバムのテーマだとうかがいました。その点から考えると、コーラスとは唱和であり、声を合わせることは音楽におけるその共生の理念のあらわれでもあると思います。フィーチャリングの楽曲ではゲストの方と蓮沼さんの声質がよく合っていましたし、本作では蓮沼さんの歌手としての成長もひしひしと感じました。
蓮沼: がんばりました(笑)。とはいえボイス・トレーニングに通ったわけでもないですし、歌詞もJポップのようなものではないですし、作曲家の歌の延長ではあると思うんです。ただ声の出し方とか、フィルの音域、音質に対して自分の声をどうやって響かせるという点でいえば、ライブを経てコツを掴んだんだと思います。あとはつべこべ言い訳をせずに前に出て歌わないといけないなっていうのはありました。僕がきちんと前に出ることで、他のメンバーや楽器も前に出てくる。精神的な話ですけど、そういうものを見せていくほうが今回はおもしろいと考えていました。
―フロントマンの立場をひきうけている感じは如実に伝わります。一方で歌詞はポップスにありがちなラブソングではないですよね。たとえば最後の「Eco Echo」では共生をテーマに掲げつつも、人間の孤独もしっかり見据えています。
蓮沼: そこまで感じとっていただいてうれしいですね。
―アルバムの幕引きとしてもぴったりだと思いました。でもいい曲が多いから曲順を決めるのはたいへんだったでしょ?
蓮沼: そうなんですよ。現代だとね、曲単位で聴く人が多いと思うんですね。僕もそうです。レコードならかけた流れでそのまま全体を聴きますけど、サブスクだと曲単位で聴くことも多い。ただそのなかでも、音盤でどのようにして物語を紡ぐかという感性、そういう感触は忘れずにいたいと思うんですよね。

―冒頭で『シンフィル』で蓮沼執太フィルにおける音楽の作り方が変化したとおっしゃいましたが、具体的にどのように変化したのでしょう。
蓮沼: プロセスをわかりやすく説明すると、ファーストの『時が奏でる』(2014年)は自分のソロ曲を全部生楽器にアレンジした感じものだったんですね。2018年のセカンド『アントロポセン』はライブでやっていた曲を録っていくのと同時に書き譜みたいな感じで、たとえばゴンドウトモヒコさんがユーフォニアムを吹くからゴンドウさんのいい響きがするように旋律を書く――という感じで、全員に当て書きのように書いていったんです。そのふたつともちがった方向を模索しました。『シンフィル』ではまずはベーシックでフィルっぽい生音のよさを活かした録音を。その後持ち帰ってポスプロ(ポストプロダクション)と僕の電子楽器をふんだんに加えました。ちょうど3年前に蓮沼執太フルフィルという名義で公募で募ったメンバーたちと一緒につくった『フルフォニー』という作品があって、全10曲のうち、前半の5曲が新録で、後半はそれらのリミックスなんですね。フィルのメンバーにそのリミックスがわりと好評で、新作でも僕が好きにいじっちゃいなよ、という意見もあったんです。それを聞いて、たしかにそうだよなと思うところもありました。「フィルは生音だけで作る」と、いま思えばそれも凝りかたまった考え方だったかもしれない、そう思って作り方もオープンにしました。
―作品論的な見地からだと『時が奏でる』や『アントロポセン』は時間とか地誌とか人類史とか、巨視的で原理的な志向性だったと思うんですね。一方で『シンフィル』ははもっと日常的でひとに近いものだと思う。大きな変化だと思いました。
蓮沼: すごくいい質問ですね。考えてもみなかった。ひとつにはこのプロジェクト自体、いつまでもつづくものではない思っていたというのはあります。すぐ終わると思っていたんですね。いまはつづいていますし全然ちがう考え方なんですけど、こうやってひとが集まって(音楽を)やるというのはほんとうに一瞬のできごとであり、つづくわけない、そのつどそのつど終わってく。そういうふうにミクロ的に日常で発生する出来事の裏返しというのは、ものすごく大きな問題意識に繋がっているのかもしれないです。
―瞬間が永遠をかねるみたいな。
蓮沼: 音は基本的に記憶だと思うんです。音は出たら消えていく。その考えは変わってなくて、ただ3作目まで行くと仲間と共につくっている自覚があるから。昔は本当メンバーのいうことをまったく聞かないで活動していましたけど、いまは声を聞いてクリエイションに直接的に影響させている。そういうところも日常的な感覚につながるのかもしれません。

―『シンフィル』では視点の面で変化を感じた一方で、『unpeople』と題したインストのソロも出すと聞いて、その両極があってこそ蓮沼執太なのかもしれないとも思いました。『シンフィル』と同時期に『unpeople』もつくっていたんですよね。
蓮沼: ばりばりつくってました。
―やっぱり『失敗しない時間の使い方』を書かないと(笑)。
蓮沼:(笑)ただはじめたのはこっち(『unpeople』)が先なんですよ。作り方が全然ちがうので、同時に作っていたみたいな感覚はいっさいないですけど、でも傍から見たらそれ同時じゃんってことにはなると思うんですけどね。
―『unpeople』はラップトップ上で完結している?
蓮沼: 最初期からやってきたことの延長です。とくに決めごともなく、自由な発想でとりくみました。つくっているうちに、この子たちはいい曲だなと思うようになって、最後には全体感が生まれてアルバムになりたい、という空気感を出してきたので、まとめたということですね。
―もともと曲ごとに発表されていますものね。
蓮沼: そうですね。そもそもずっと個々の素材としてあったんですよ。
―素材というのはなにをさしますか。
蓮沼: 僕のいつもの癖で、いい曲は曲自身が勝手にできあがってくるんですね。あたりまえなんですが、曲がいいと一気に完成してしまうんです。で、完成しないとダメだといって捨ててしまうんです。ゴミ箱に入れちゃうんです。
―もったいない。
蓮沼: でもこの5~6年はそのよさに気づけない自分がわるいんだな、と思うようになりました。良さに気づけない自分が良くない。なので、陽の目を見ないサウンドたちのことを素材と呼んでいるんですね。
―それら素材が語りかけてきたと。
蓮沼: 当然語りかけてこない音もいますよ。語りかけてきた音たちが『unpeople』になっていった。
―インストのアルバムはひさしぶりですよね。そもそもインストのアルバムにしようとしていたのか、それともそう仕上がってしまったのか、どちらでしょう。
蓮沼: インストが好きなんですよ。言葉が乗るとなにがしかのメッセージ性が強くなっちゃうんですね。音楽自体に意味がついてしまうじゃないですか。
―その点でも『シンフィル』と対なのかもしれないですね。
蓮沼: そうですね。『シンフィル』と『unpeople』は双方が共生することで輝く関係性になるとすごいいいなと思っています。同じ2023年に出せてよかったなと、いまは思っているんですよね。
―同じ年に出ているというのは後年、ディスコグラフィをふりかえったときに、なにがしかの符牒になりますからね。それ以前にポップな『シンフィル』と実験的な『unpeople』の対比がすばらしいと思います。
蓮沼: 現代に蔓延るアテンション・エコノミーの世界でいかにクリエイティブなことをやっていくかは難しい問題ですよね。
―音、サウンドということでいえば、私たちがあずかり知らない場所でも音は鳴りつづけているのだと思いますが、ひとに聴かれないかぎり音楽にはなりえないとも思うんですよね。
蓮沼: いや、そう思います。おっしゃる通り、聴かれないと音楽はどんなによくても「ないもの」とされる。それがはたしてよいのかわるいのか、答えもないと思うんです。
―そんななかで、音楽にどのような向き合い方をしますか。
蓮沼: 僕は根が作曲のほうなので作り方をどう更新していけるのか、できるかぎり自分の慣れたことはしないと考えてますね。
―作曲の歴史をふりかえると、方法論なんて20世紀に出尽くしたんじゃないかと思ったりもしますが。
蓮沼: もちろん、そう思います。でも同時に、例えばサウンド・インタレーションのような音のアウトプットも20世紀後半から生まれてきていますよね。一方で、録音や演奏の方法論は固定されていますが、ヒップホップだって50年もの歴史があるのにまだまだおもしろい作品が出てくる。そういうところもふまえて、出尽くしているということがわるいことだけじゃないな、とも思うんですね。