藤井道人

日々映画を作っていく中で忙殺され、失われていく大切なはずの記憶の数々。
映画監督・藤井道人による連載『けむりのまち -Fake town-』は、そんな瞬間・瞬間を記録していくものとして掲載している。吹けば形を変えてしまうように曖昧な記憶の数々を繋ぎ止める記録としての文字列である。
連載は早く第九回。今回は藤井道人と関係のあり、同い年の映画プロデューサー2人を招き、映画業界の現在と未来についてお互いの立場や状況も交えながらフリートークする。
参加したのは、東宝から臼井真之介とスターサンズより行実良。場所は今年の9月にオープンしたばかりの三軒茶屋のchill+drain244 IZAKAYA。
日本映画界の未来は明るいのか否か。

映画業界に携わるメジャーとインディーズの同い年
藤井道人(以下、藤井):連載を続けてきて、そろそろ映画業界自体の話もしたくて面白いメンバーがいないかな? と思っていたら、各々メジャーとインディーズの会社に属しながら映画を作っている同い年がいるじゃないですか。ーーってことでお2人をお呼びしました。まずは自己紹介してもらおうかな、どうぞ。
臼井真之介(以下、臼井):東宝の映画企画部でプロデューサーをやっています。映画だけではなくドラマやアニメーションも作っていて、もう8年ほど同じ仕事をさせていただいていますね。藤井さんとは去年からの繋がりになります。それまで同い年の監督と、いつかは仕事したいと思っていたんですけど、藤井さんは同い年だからこそお話するときにはちゃんと企画を持っていきたいと思っていたんですよ。どこかのパーティなどで挨拶だけを交わすのではなくまずは仕事ベースでお話ししたいと思っていて。その機会がようやく去年ありましたね。
藤井:去年だよね、名前はずっと知っていたけど、そこでタメだって知って。つまり、今は一緒に企んでいるものがあるってことだよね。
臼井:ええ、そこへ向けて急速に動いている状況ですね。
行実良(以下、行実):スターサンズに所属しております。部署はなく企画の発想からポスターの発送まで全部自分たちでやるような会社にいますね。藤井さんとは前社に所属しているときに『新聞記者』を介して出会いました。
藤井:知っている人も多いと思うけど、スターサンズがどういう会社なのかを少し説明してくれる?
行実:創業者は昨年亡くなった河村光庸(映画プロデューサー。『新聞記者』や『ヤクザと家族 The Family』、『ヴィレッジ』などを担当。藤井監督と密接な間柄にあった)で、彼が2008年に設立しました。それで、私が前社にいるときに社内で誰もが担当したがらない『新聞記者』を一緒にやっていたんですけど、そのせいなのか映画公開と同時に異動になったんですよ。
一同:笑。

行実:2019年の公開時、新宿ピカデリーで舞台挨拶をしたときに藤井さんにその話をしたら「今すぐ辞めちまえ」と。そしたら一緒に仕事できるじゃんって言ってくれたんですよね。
藤井:そうだったね(笑)。
行実:ええ。でも、当時は会社を辞めるのが怖くてすぐには行動できなかったんです。で、翌年に『ヤクザと家族 The Family』を劇場で観たら、本気で腹が立ってきちゃったんですよ。『なんでここに自分がいないんだろう?』って。それで2021年の4月1日からスターサンズに移り『ヴィレッジ』でご一緒させていただきました。今はより現場に近い立ち位置で楽しいなぁと思いながら(藤井監督に)ビシバシ鍛えていただいている状況ですね。

東宝は入団テストに近い感じがした
藤井:そんな同い年で中堅に差し掛かる年代の我々なんだけど、今どんなことを考えていて先々この業界がどんな風になっていくと思うのか、自分はどうしていくのかってことを話せればなって思ってさ。まずは僕から見た2社の話をさせてほしいんだけど。
臼井&行実:はい。
藤井:スターサンズは僕のことを引き上げてくれた場所だから河村さんが言ったことがすべてで、彼が白と言ったら黒くても白に変えられるか。どこか一緒に自主映画を作っているような思いでやっていて。一方で東宝の場合はどこか入団テストに近い感じがあった気がするんだよね。1打席目に立ってホームランじゃないにしてもヒットくらい打たないと、みたいな。そうじゃなきゃ次席は立たせないぞって厳しさを感じる部分があった。ビジネス的かつ合理的で、その合理性が僕は好みだったんだよね。20代の頃はメジャー監督、メジャー映画って自分達の居場所じゃないよなって考えていたけど、実際に中の人と接してみると僕たち以上に映画業界について考えている人がいて。森になっているんだけど、中に入り込むと木の1本1本がしっかりしているのが東宝のイメージなの。そう考えるとスターサンズにはそもそも木が2本しか生えてないっていう。
行実:あはは!(笑)。
臼井:その“森力”みたいなのはあるかもしれないですね。いろんな木があって森に見えるというか。僕、最初の作品が李相日監督の『怒り』(2016年公開)だったんですけど、李さん曰く、自分たちはサッカーで言うところのサイドバックだと。つまり、毎回点を獲得するわけではないけど、めっちゃ働くし、その年の中ですごい役割を担って、たまに点も取るかもしれない。そういう気概で作ろうってことを、東宝に対して表現してくれて。そう考えると、フォワード的な監督もいるんでしょうし、各々に役割があっていろんな“木”があってもいいでしょうからね。そうやって先輩方もたくさんの作品を作ってきたと、僕はそう解釈しています。

スターサンズにはインディーズだからいいやっていう負けグセがない
藤井:なるほどね。この間、TikTokの映画祭(TikTokと東宝がタッグを組んだ、タテ型の映画祭『TikTok TOHO Film Festival』)に審査員で参加したんだけど、なんかね。そういう面でも新しい取組みをしているんだよなってことを考えたね。そうなると、逆に臼井くんから見てスターサンズはどう見えているの?
臼井:ちゃんとスターサンズとしてのカラーがあるってことがうらやましいですね。東宝が“森”だとするならば、そこに固定された色はないわけで、河村さんがいなくなった今もそこを大事に続けられているのは強みだと感じました。企画を立てるにしても筋が通っているというか。そこはすごく勉強になります。
藤井:この3年くらいってさ。『新聞記者』、『ミッドナイトスワン』、『ドライブ・マイ・カー』と、ある意味インディペンデントが続いたわけじゃない。(※)この流れって正直どう感じていた? やっぱりもっとも多くの人の心に届くものを作っているのは自分たちなんだって自負みたいなものがあったうえで向き合っていたのかなって。
※第43回以降の日本アカデミー賞において、大手映画制作会社による作品が最優秀作品賞を獲得していた時期のこと
臼井:チームに入っているとそういう思いは少なからず生まれてくるんですけど、東宝としてどうなのか? というのはちょっと難しくて。というのも、『怒り』は公開後、きっと僕たちが(日本アカデミー賞を)獲るって思っていたんですよ。でも、2016年は『シン・ゴジラ』がかっさらっていったんです。同時に『君の名は。』も同年公開で興行成績はダントツでした。(どれも東宝の映画なので)敵はすぐ隣にいたっていう。その後の飲み会は荒れましたよね。
藤井:そうなるよなぁ(笑)。
臼井:当事者としては悔しさは勝っちゃったりもするんですけど、映画好きな人間としては納得する部分もあるし、会社の人間としてではなく個人の判断で向き合うことになるんですよね。

藤井:うんうん。ザネ(行実氏)はどうですか? それこそスターサンズと東宝なんて本当に右と左、その両極にあるものだと思うけど。東宝に対して思うことは?
行実:この業界に入ったときから、東宝さんは王者として君臨しているわけじゃないですか。だから個人的な戦略としては東宝さんができないことをやろうっていうのは常々考えているんですよ。ただ、それを実現することは容易ではなくて、東宝さんにできないことで勝負するためにもスターサンズがよかったというか。普通はやらないだろうなってことをやったりするし、この業界における存在として1つ必要なんじゃないかって思う部分があって、そこは今後も意識していきたいし、より広げていきたい部分としてもあるんです。
藤井:スターサンズのよいところとして、売れなくてもいいやっていうインデーズ集団じゃないってところがあるんですよ。監督が貧乏じゃダメだ、カッコよくあらねばならないっていう。もちろん削れるところは予算をゴリゴリに削るんだけど、スタッフにはお金をしっかりと払いたいっていう思いが先代(河村光庸氏)の考えにあって。インディーズだからいいやっていう負けグセがなかったのが、この躍進の秘訣の1つだったのかなっていうか。『ヴィレッジ』以降もいてくれたら、「うるせぇジジイだな」って言えたんですけど。ここからは僕たちがうるさいこと言わなくちゃいけないのかもしれない。じゃあさ、2人はなんで映画プロデューサーになったのかな? 講演会をやっていても思うんだけどプロデューサーになりたいって学生は少ないんだよね。具体的に何をやるのかもわかりにくい部分はあると思うんだけど。
臼井:なんでなのかが思い出せないんですけど、昔から好きなことを仕事にしたいとは思っていたんですよ。そう思わせてくれた人が2人いて、1人は親父なんです。レコード会社でA&Rの仕事(アーティストの音楽を世に送り出すこと)をやっていてサンプル盤が家にあったりしたんですよね。当時、CDがミリオンで売れたりする時代にサンプル盤を学校に持っていくと、それだけでヒーローになれたんです。そんな風に誰もが憧れるものを作っているんだなって思ってカッコいいなと。ただ、親父と同じ道はイヤで映画の道を志そうとして。もう1人は俳優の市原隼人くんなんです。彼とは地元が同じで中学3年間一緒でめっちゃ仲もよかったんです。そんな彼が、ある日の登下校の帰り道、夕暮れが光る中で本を読みながら歩いていて。何を読んでいるのか聞いたら「これ、台本って言うんだ」って。『リリイ・シュシュのすべて』(2001年公開)の台本だったんです。「これは台詞って言って……」って会話をして、それをスクリーンで観たときにすごく衝撃を受けました。あいつがあのとき読んでいた台詞が映画になっている! って。近くにいた人がすごく遠く行っちゃった感覚もあって。それで、やるんだったら映画会社に入りたいと思いましたね。
行実:僕は出身が山口県長門市ってところで映画館には電車で1時間くらいかけなくちゃ辿り着かないようなところに住んでいたので、映画を観るってことが非日常体験だったんです。大学生になって上京してからは映画館もたくさんあるしレンタルもできるんで、年間300本くらい映画を観て、漠然と自分も映画をやりたいなと思うようになっていったんですね。でも、演出も芝居も脚本を書くこともできない。じゃあ、映画を作るうえで自分に何ができるんだろう? と考えたときにチームや予算を集めたりってことができるんじゃないかなって。それでバップという会社に拾ってもらったのがきっかけになりますね。その映画のクリエイティブに関わりたいというよりも、作品が世に出ていくことに対する喜びが今も大きいですね。そんな中で2015年頃に河村と出会い、映画プロデューサーの形を見せてもらって、現代において自分はどういうプロデューサーになるべきなのかってことを日々、自問自答している状態です。だから、まだ映画プロデューサーになれていなくて志している最中といった感じです。もともと大きな組織にいて今はスターサンズにいるので、いろんな人の気持ちもわかるし共存しながら一緒に業界全体を盛り上げていく存在の1つになりたいと思っています。

若い人は映画業界に憧れているか?
藤井:そういうことも踏まえつつ。5年後とか今後はみんなどうしていこうと考えてる? 三者三様の使命感めいたものが各々にあると思うんだけど。
臼井:僕の場合は、置きにいったら負けだと思っているのでチャレンジできるようなものでありながら、観客の心と寄り添える感情が通った作品に向き合っていくことが、僕らのやらなきゃいけないことなのかなと思っていますね。映画を作るのって時間がかかるじゃないですか。今から3年後にウケる作品を作ろうと思って狙っていくのは本質的には難しいと思いますし。
藤井:そうね。数年後の公開でってことで臼井くんからオファーがきたものが、本当に「え、まじで?」って思った(笑)。だからこそ気になってこうして会話できる仲になったんだと思うけど、東宝なのに、あえて置きにいかずギャンブル性の高い企画に挑戦しようとしている姿勢はすごく面白いと感じたし、僕も成功させたいって思ったんだよね。
行実:先々どうなっているか。スターサンズに関しては資金繰りもちょっとわからないような状況ですけど(笑)。でも、映画も誰が作っているのかって部分がより重要になってくる気がしています。それは監督や出演者はもちろん、制作会社にいる我々のような人間も含めて。というのも、これだけ配信が浸透した現代のライバルって何も劇場公開の新作映画同士だけではなくて旧作や配信のみの作品なども含まれるわけじゃないですか。その中で今生きている我々がどう観客に対して共感してもらうのかを考えたときに、作っている人の顔が見える作品っていうのは1つあるんじゃないかと思うんです。農家じゃないですけどね。
藤井:ああ、逆張りでね。たしかに農家とか言われると、たしかにね。顔が見えるっていうのは重要かもしれない。ドラマの情報解禁のニュースでも監督の名前が乗っていなかったりして、自分もそういう扱いをされていた時期はあるけど、たしかに今って監督の名前で客は来ないよねっていう数式に嵌め込まれた。でも、その逆張りで作家を育てていくっていうのはちょっと面白いかもしれない。
臼井:藤井さんはどう思いますか?
藤井:なんかね、普段から話題にしていることだけど、「今、面白い若い監督って誰?」って。僕たちが自由にやれていた2、30代の頃よりも今の方が自由そうで不自由な気がしていて。なんかこう駒取りゲームというか、そうな感じになっていることに責任を感じてる。なんかさ、この先5年くらいでジョージ・ルーカスみたいなヤツが出てきてくれないと日本映画業界はやばいな、みたいな。そういう存在に僕はなれないけど最大限にサポートして道筋を作ることはできると思って。インディーズとメジャー、そのどっちも飛び越えて天衣無縫にやってくれるような人たちがめっちゃいる時代がくるのを超楽しみに待っちゃうタイプなんだよね。例えばさ、次の新作ゴジラ映画を担当する監督が25歳だとか。そういう奇跡が生まれてもいい時代なんじゃないかと思うんだよね。こんなにデジタルで誰でも映像が作れる時代なのに、自分たち以上の世代に引導が渡されていないのも、映画業界はもしかしたら若い子が憧れる産業になっていないかもしれないから。……でも、実際のところはわからないね。
臼井:僕も質問があるんですけど、藤井さんはどんなプロデューサーが理想なんですか?
藤井:いやー、パターンによるんだよなぁ~。同世代に求めているものは部活感、全員で団結して一緒にやってみんなで悩む。僕がこの数年で慣れていたのは河村さんとのやりとりで、半分合っていて半分違う感じで意見を交換し合って擦り合わせていくような感じ。親子くらいの年齢差があったから違っていてもうまくいっていた部分もあるけど、今後自分たちで時代を切り拓くことを考えるのであれば、古くさく言うと熱血感であったり、ちゃんとパートナーと呼べるプロデューサーと仕事をしたい気持ちがあるね。ストレートにコミュニケーションが取れて意見が異なっているときは普通に言ってくれるような間柄がいいな。
臼井:うんうん。
藤井:これ、臼井くんに聞きたいんだけど。松岡さん(昨年、東宝代表取締役社長に就任した松岡宏泰氏)、以前お会いしたときに国際部だって仰っていたんだけど、そういう部署にいた方が社長になったってことは、東宝は今後グローバルに活動をしていくということにもなるの?
臼井:ああ、そこについては会社全体としての目標が社内に出されていて、それを達成するためには間違いなく海外にも視野を広げなくてはいけないと実写チームの自分としては個人的にも解釈していて、今まで以上に視線が向いています。ただ、具体的なところは現場で考えていかなくてはいけないので、色々とトライアルしながらやっている状態ですね。
藤井:あー、それは面白いね。
臼井:こういう時代ですから国内だけではなくて海外と今だからできる連携を取って面白い作品を生み出すこともできるんじゃないかって思いますね。ただ、国内における業界のことを考えると、やるならちゃんとビジネスとして成功させなくちゃ次が続きにくくなっちゃうと思うので成功例を生み出すことができればと思うんですけどね。
藤井:そこを引っ張ってくれたら面白くなりそうだよね。ちょっと人任せになっちゃうけど、僕たちもそうなりたいと思っているし未来が変わってくるんじゃないかと思う。
行実:じゃあ僕も臼井さんに聞きたいんですけど、社内異動で企画やプロデューサーの立場から離れることになったらどうしますか?
臼井:えーーー……。お行儀良いことを言うと、移動先の部署がどこであれプロデューサーみたいな形が作れるんであれば会社として強くなると思うので、そういうことをやってみようとするでしょうけど。まぁ行実さんのように辞めることも頭をよぎるでしょうね(笑)。

求められるのはメジャーとインディーズが タッグを組んで業界を盛り上げること
藤井:スターサンズって、この5年間、インディーズ界に突如現れた光のように輝いていた気がして。河村さんが亡くなった今、ザネがスターサンズを守るっていう立場になったわけだけど、今後インディーズスピリッツはどこにいくと思う?
行実:これは河村の受け売りでもありますけど、映画は自由であると。それを体現できるのは、自立した存在でもあるインディーズである。それが1番なんじゃないかなと。そんな風に立ち回れなくなるなら会社を畳んでしまった方がいいし、スターサンズらしくあるにはインディペンデントな存在であり続けるしかないのかなと思っています。
臼井:その先代の名前って本当に大きいわけじゃないですか。神格化されている部分もあると思うんですけど、それを背負い続けるのって純粋にプレッシャーを感じませんか?
行実:そうですね、業界における河村の貢献度は絶大なわけですけど、そこは映画の観客にはあまり関係ないところでもあるのかなと。河村の意志も継承しつつ、東宝さんともタッグを組みながら、彼が作ってきたものをちゃんと守りながら時代に合わせて変化させてスターサンズを続けていくことが1番なんじゃないかなと思いますね。
藤井:やっぱり河村さんと市川さん(東宝取締役専務執行役員、市川南氏)との関係性があって、僕たちの作品のメイン館がどんどんTOHOシネマズになっていったと最近思うんだよね。だから、先代はメジャーとインディーズがしっかりと手を組んでやっていくことは望んでいたんじゃないかなって。市川さんもそれを知っていて迎え入れてくれたんじゃないのかなっていうのは肌感として感じるね。あの人たちがそういうことを考えてくれていたんだろうなって。ただ、あんなプロデューサーはなかなかいないよ。だって、死んだのにずっとクレジットに残ってるんだもん。2025年公開の映画とか。何年先まで書かれてるんだろうって思うよ(笑)。
臼井:相変わらずすごい存在感ですね(笑)。
藤井:ね(笑)。だからメジャーもインディーズもゴールじゃないっていうか。作品や状況によってお互いに手を組むことができたり、そういう機会が増えていけば、この業界はもっと面白くなっていくんじゃないかな。なんかメジャーとインディーズって、自分たちで壁を作っちゃうような風習がすごくあるし、各監督も個人戦好きじゃないですか。でも、企画は“個”であってもプロジェクトはみんなでやるべきだなっていうのはすごく思う。この業界というプールをみんなでどれだけ遊べるかってことを考えるのが、我々30代の役目なのかもしれないね。
臼井:それこそ『エブエブ(エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス)』のダニエルズ(監督賞と脚本賞に輝いた)なんて年下ですもんね。彼らはきっとメジャーを意識し過ぎて作っていないし、かといってインディーズ感を出そうとも思っていないだろうし、純粋に面白いことをきっとチームみんなでニヤニヤしながら作っていたと思うんですよ。ああいうことが大事なんじゃないかと思いますね。
藤井:そうだね。そんな風に世代感や立場が行き来自由になっていくっていうのを自分たちからやっていった方がいいなと考えているので、今後は取材を抜きにして定期的にね。監督とかプロデューサーとか、この業界のいろんな人を呼んで話をしたいし、『面白いことをしようよ』の会みたいなのをしていきたいと思っているので。今日はこんな感じでございます。ありがとうございました。
臼井&行実:ありがとうございました。

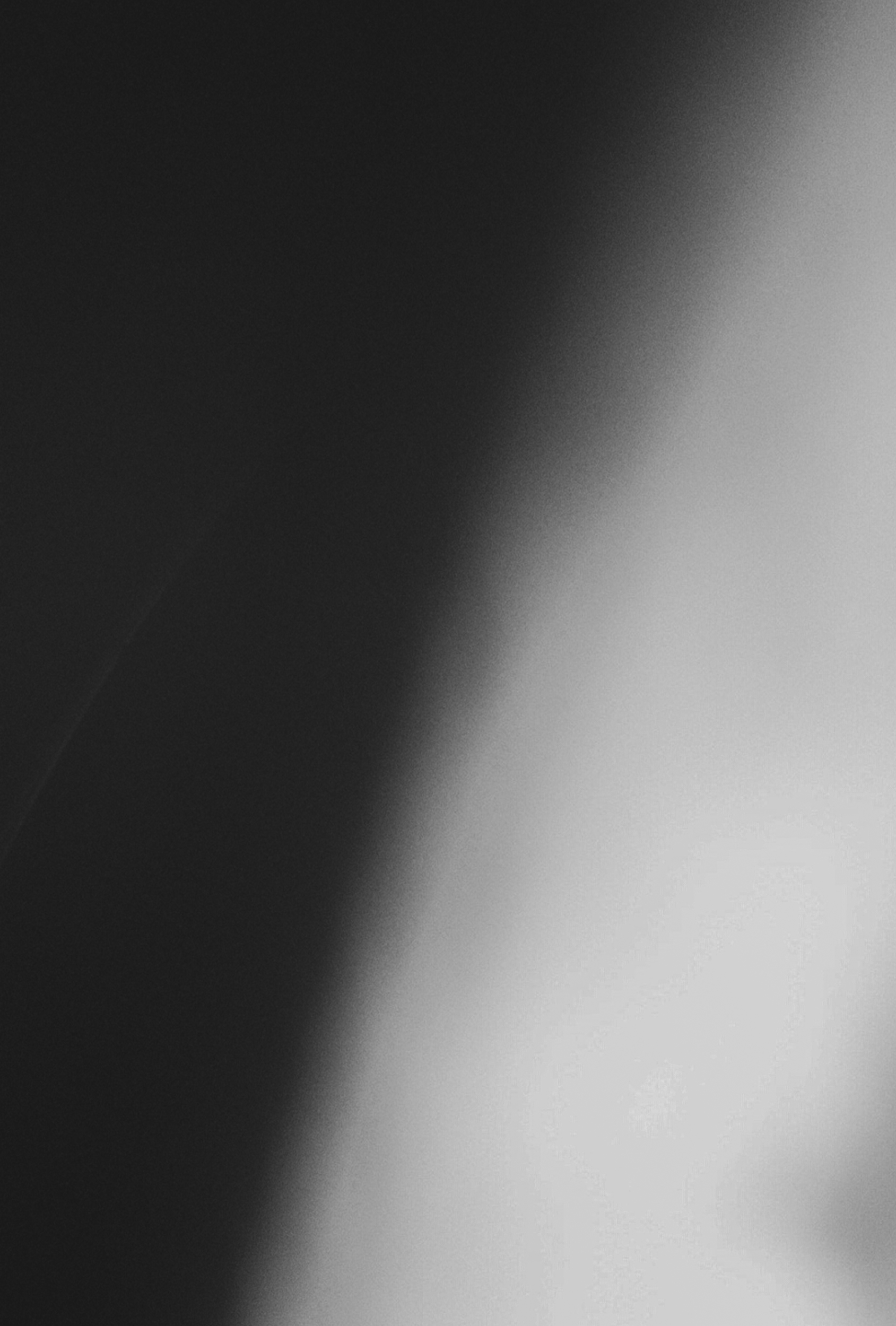
※本連載にて、藤井道人監督への質問を募集。
監督が一問一答形式でお答えするので、
聞きたいことや気になることがある方は、
こちら宛にお送りください。




