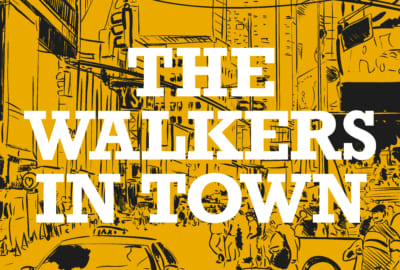ノベリストにスケーターにコラムニスト、はたまたブックストア。
まずは、現代アメリカ作家の頭の中に“日本”を入れてみたら、何が出てくるか。
やれフジヤマだのスシだとは違う、笑いと幻想のゲームが始まる。
a short short story two : 佐々木ハナに尻尾が生える三つの筋書き
“THREE SCENARIOS IN WHICH HANA SASAKI GROWS A TAIL”
from
[THREE SCENARIOS IN WHICH HANA SASAKI GROWS A TAIL : KELLY LUCE STORIES]
Author—Kelly Luce

1
今日は三十歳の誕生日。彼女は独り目を覚ます。右手がもぞもぞと動き、柔らかい毛に当たる。昨日の夜にお風呂に入ったときには、そこに毛はなかった。よろよろと全身大の鏡の前に行き、覗き込む。尻尾は七、八センチほどの長さで、ラベンダーの色合いのある銀色に光り、先は細く体から伸びていて、根元のところではロープくらいの太さがある。その毛は背骨の一番下にある、いびつな黒いボタン形のところから出ている——母親が「アジサイの痣」と呼んでいたところだ。母親はアジサイが大好きだったが、ちょっと派手すぎるとハナは思っていた。チューリップのほうが好きだった。
彼女は尻尾の下に手のひらを回して、親指を毛の上にすべらせる。ほんとうにふわふわしていて、赤ちゃんのピンク色の頬っぺたみたいだ。電話がプルルと鳴る。母親の単調な鼻声が、あきらめちゃだめよと留守番電話に言う。いまどき、三十をとっくに過ぎた女の人だってどんどん結婚しているんだから。
ハナはシャワーを浴びることにする。まだ医者に電話するには早い時間だし、尻尾は変な感じだけど痛みがあるわけではない。それに、時間とお金をかけて救急外来に行くほどのことにも思えない。背中を水が伝い、毛の束を濡らす。濡れると細く、濃い灰色になり、根元の毛は腰から少しだけ立ってからしなだれて、お尻の曲線にぴったりとつく。彼女はためらい、それから手にシャンプーを取ると両手を後ろに回す。泡立てて、洗い落として……やっぱり、コンディショナーもしてしまおう。コンディショナーを三分染み込ませてから、冷たい水ですすぐ。冷水は毛幹を引き締めて、毛をつややかにしてくれる。あとで三つ編みにして、リボンで飾るのもいいかもしれない。自分にしかできない手入れをしていこう。
2
はなちゃんは水疱瘡が治ったばかり。そのお祝いに、親ばかの両親は彼女を連れて上野動物園に行く。地元の動物園にはいないレッサーパンダを見せるためだ。
はなは上野動物園が好きではない。大きくて人がいっぱいだし、動物たちは気が立っているように見える。怒ってガラスを殴っているゴリラの気分は、自分の病気と同じように周りにも感染するんだろうか、と彼女はふと思う。感染するというのは、いらないと思っている人にも嫌なものをあげてしまうことだ。そうして彼女は水疱瘡をもらったのだし、そうやって治した。彼女は母親にしがみついてべそをかく。醜くてしわだらけのおばあちゃんに近づきすぎると、自分も不細工で年寄りになってしまうのではと心配になる。
三人は動物園を出る。父親は贅沢をしてタクシーをつかまえることにする。三人で歩道に立って空車を待っていると、ドブネズミが一匹ゴミ箱から出てきて、はなの赤いスニーカーの上を走っていく。はなは帰り道はずっと落ち込んでしまい、父はタクシーの運転手にお金を渡して家までずっと送ってもらう。
次の日、はなの思っていた通りのことが起きる。ピンク色で皮だけの、毛のない尻尾が、伸縮性のあるパンツからちょこんと突き出ている。彼女は歯ぎしりし、感染を召喚する。
3
はなはミスタードーナツ浅草駅前店でもう三年ほど働いている。お客が少ないときには、頭の中で、ほんの二歩で行ける場所がどれくらいあるのか数えてみることもある。一歩目で電車に乗り、二歩目で降りる。プラットホームが三十五あって、それぞれに二本か三本の路線が乗り入れ、それぞれの電車は季節と週と曜日に応じて十から二十の駅に停まる。でも、はなが行くのは二十三番ホームだけだ。そこで茶色い電車に乗って、降りる。両親と住んでいる、壁の薄いマンションから通勤している。
朝、注文する顔はどれも溌剌としているが、夕方になると元気がなくなり、太陽が傾くころには人々がそろって歳をとるような気がしてくる。だが次の朝になると期待に満ちた顔が戻ってきて、また燃料を補給しようとしている。前の日の自分たちの修正版といったところか。彼女も変わるのだろうか? その気配はなさそうだ。ときには、彼女にとってだけ時間が止まっていて、相対性宇宙のなかの一つだけの盲点が自分なのだと思えることもある。自分を遥か彼方から眺めているような感覚。
彼女は店の特製ドーナツを並べる。いつもの円形に、コーヒーに浸すために焼いた突起をつけてある。ドーナツに尻尾がついている、と彼女は思う。
スーツ姿の男性がドーナツを四個注文し、カウンターの上、分厚い封筒の上にお金を乗せて渡してくる。彼女はお釣りを出す。顔を上げると、男性の姿はない。お金だけでなく、封筒も置いた
まま行ってしまった。それを手に取ると、写真が何枚もすべり出てくる。彼女自身の写真が。
彼女はよく見てみる。写真の角が手のひらに当たってちくちくする。どの写真でも、彼女はまさに今いるカウンターの後ろに立っていて、今と同じ赤いエプロン姿で、今と同じように髪の毛は耳の後ろにたくし込んでいる。
彼女はぴくりと動き、腰のあたりをぴしゃりと叩く。ウエストバンドの中に何かが入った。ノミかもしれない。

PROFILE
Kelly Luce
ケリー・ルース
米・イリノイ州出身。大学卒業後に日本で3年間働いたという経験を持ち、2013年のデビュー短編集『THREE SCENARIOS IN WHICH HANA SASAKI GROWS A TAIL: KELLY LUCE STORIES』ではすべての主題が“日本”。現代作家の持ち味である童話・寓話のテイストを、日本を舞台に展開する作風で高く評価され、短編のひとつは岸本佐知子の訳で読むことができる。
“Three Scenario in Which Hana Sasaki Grows a Tail” by Kelly Luce Copyright © Kelly Luce, 2013, All rights Reserved first published in Shenandoah, later published in the collection called THREE SCENARIOS IN WHICH HANA SASAKI GROWS A TAIL published by A Strange Object Permissins granted by Kelly Luce c/o Farrar, Straus & Giroux, Inc., New York via Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo