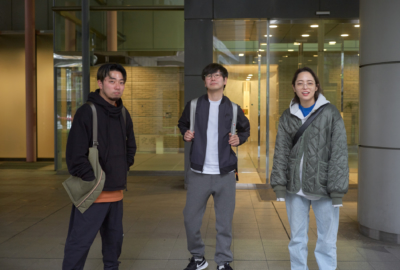DJを軸にマルチに活躍するLicaxxxとWONKのリーダー/ドラムスである荒田洸の二人が、リスペクトする人を迎える鼎談連載。第二十二回は、ポピュラー音楽研究を専門とする慶應義塾大学教授の大和田俊之を迎える。Licaxxxが体調不良で急遽不参加となったが、二人が通っていた大学の教授との音楽談義は、過去から未来まで行き来する興味深いものとなった。
EYESCREAM誌面には載りきらなかった部分も含めて完全版でお届けします。

音楽のパブリックな領域とパーソナルな領域
荒田:いま、大学で教えて何年目くらいですか?
大和田:15年くらいかな。
荒田:クラシック音楽の研究って研究対象がめちゃくちゃ細分化してるじゃないですか。譜面の筆跡からそれは誰が写したのか、くらい。ポピュラー音楽研究はどこまで細分化されているんですか?
大和田:日本のポピュラー音楽研究の学会には400人くらい学者さんたちがいるけど、バックグラウンドは音楽学、文化人類学、民俗学とさまざま。そういったいろいろな学者さんが、たまたま対象に音楽研究を選んでいる。そのなかで僕は文化史のアプローチですね。
荒田:大学で授業を受けていたとき、すごく面白かったです。大阪のおばちゃん論がとくに印象に残っている。
大和田:ミンストレル・ショーね。19世紀アメリカで、白人の芸人が顔を黒塗りにして面白おかしく黒人のモノマネをして笑いをとるという、かなり差別的な芸があった。それと同じように、大阪の芸人が大阪のおばちゃんのモノマネをするときに、そこに本当の部分と作り上げた部分がある。その虚実入り乱れる感じが19世紀アメリカの黒人の表象につながるんじゃないかという。ちゃんと本当の大阪のおばちゃん見たことある? って(笑)。
荒田:10年くらい前ですけど覚えています。
大和田:それでいうと、アメリカには中産階級出身のアフリカン・アメリカンのラッパーもいるわけ。だけど売れるためにギャングスタ・ラップに近いイメージで打ち出していくことがある。それは郊外に住むティーンの白人の聴衆が「ワルい黒人」みたいなものをどこかで求めているから、戦略的にそれに寄せるということ。そこには、社会に流通する黒人のステレオタイプに自分をどこまで合わせていくのかという戦略と、でもやっぱり本当の自分を出したい、というアーティストとしての表現欲との葛藤がある。

荒田:どういう心持ちでWONKとして音楽をするかという問題は常に考えます。自分たちは小さい頃からブラック・ミュージックを聴いて育ってきたから、自然とその影響が音楽には出る。でも、そのバックボーンにはブラック・カルチャーというのがあるから、どういう向き合い方でものづくりをすればいいのかなという。
大和田:それは、日本人の音楽家がずっと問い続けてきた問題でもある。たとえば60年代のジャズミュージシャンが、「自分たちのジャズはどうあるべきか?」つまり、日本っぽさを付け加えるべきなのか、それともアフリカン・アメリカンが中心になって作り出してきたジャズに、より軸を立たせて勝負するのか。そこはずっと問い続けてきた。加えて、世界の中での日本人のステレオタイプもあるから。僕は帰国子女なんだけど、外国で母親がパーティーに出るときに必ず着物を着ていたことに近いというか。外国人がイメージする日本人を演じるほうがウケがいいから。でもそういうステレオタイプを利用することは必ずしもダメではなくて。
荒田:J-POPもまさにそうですもんね。ステレオタイプに合わせていったほうがセールスは伸びる。
大和田:セールスでいうと「売れるのが悪」みたいな時代もありましたからね。山下達郎や吉田美奈子が「ニューミュージック」と呼ばれていた1970〜80年代にしてもそう。ああいうのは軟弱だ、みたいな。そういった感覚は、昔に比べたらいまはなくなってきている印象はある。
荒田:最近、そういうのはなくなってきている気はします。
大和田:そうだよね。たとえばアメリカでも、(USインディーを代表するバンドである)ザ・ナショナルのメンバーがテイラー・スウィフトを絶賛するとか。昔はそんなこと考えられなかった。わりとみんな、好きなものは好き、というか。いまの大学生を見ていると、一人ひとり音楽の趣味があって、それを共有しない感じがする。
荒田:たしかに。音楽関係者だと、SpotifyとかApple Musicのプレイリストやライブラリを普通に見せてくれるんですけど、一般の方はライブラリをマジで見せてくれない(笑)。
大和田:そう、大学生も、みんな音楽好きなんだけど、それを仲のいい友達とも共有していない気がする。それってちょっと僕の世代では考えられなくて、面白いなって。
荒田:「へえーそれ聴いてんの?」ってやりとりしたいのに、絶対に見せてくれない。自分のことを知られたくないのか。
大和田:音楽のパブリックな領域とパーソナルな領域のうち、パーソナルな領域のほうがすごく大きくなっているのかもしれない。パブリックな領域として、お互いがコミットしていくという感覚は薄れてきているのかなと感じる。

どこまで妥協しないでポピュラーになっていくか
荒田:教授から見た、近年の日本のヒップホップ熱はどう感じますか?
大和田:ものすごい盛り上がりですよね。だけど、僕らの世代、40〜50代のヘッズではない、いわゆる音楽ファンが本当にヒップホップを丸ごとスルーしちゃったんだなと思いますね。当時の日本のジャズファン、ブルースファンって、すごくコミットしていた。メディアでも「日本のジャズはどうあるべきか?」って喧々囂々と言い合っていたんだけど。ヒップホップに関しては、ネイティブ・タンをちょっと聴いて、それ以降は聴かないという人が多すぎる。
荒田:なぜそうなったんでしょう?
大和田:90年代あたりから音楽も映画もカルチャー全般がドメスティックになっていって、洋楽自体を聴かなくなったことが一因。もっとも顕著に現れているのが、いまの日本のアイドルって、アメリカやイギリスのヒット曲を参照しなくなったでしょ? 80年代までの日本のアイドルって完全に参照していた。
荒田:完全に参照していましたよね。
大和田:だから、K-POPは安室奈美恵以降に日本の音楽界がやらなくなったことをやっているだけなんですよ。新しい曲が出たら、このビートを使ってどうやってアイドルグループの曲に落とし込むか? みたいなことをK-POPはずっとやっている。筒美京平だとか、当時の日本の作曲家はそれをやってきていた。ビルボードのTOP 40のレコードを全部買って、「ここは使える、使えない」とやっていって、その3ヶ月後にはたとえば小泉今日子の曲として使っていた。だけど、だんだん外国の文化になんとなく触れなくなっていった。それが、アメリカのポピュラー音楽史でいうと、ヒップホップが一番盛り上がっていた時代と重なっている。僕らの世代の日本人は、ヒップホップ好きしかヒップホップを聴いていない。ポップスやインディーロックは聴くんだけど。

荒田:いまのヒップホップのリスナーは10〜20代が多いですもんね。
大和田:(音楽ライターの)渡辺志保さんが言っていたのは、いまの日本のヒップホップリスナーは、アメリカのヒップホップは聴かずに日本のヒップホップしか聴かない人も多くなってきていると。
荒田:日本のリスナーにとっては、わざわざ言語のわからないアメリカの音楽を聴かなくても、日本に十分いっぱいいるというのもあるかもしれないですよね。
大和田:海外への関心の低さは不景気が原因でもあるんですけどね。それと日本の音楽シーンの成熟が時期的に重なったのはあるかもしれないですね。でも、WONKがコロナ禍以前にシンガポールでライブしたりしていたじゃないですか。それを見て、これだ! と思っていた。
荒田:というと?
大和田:WONKのような洗練された音楽で、どこまで妥協しないでポピュラーになっていくか。それを想像したときに、日本のパイを増やすんじゃなくて、アジアのリスナーを増やすほうが近道で、はるかに理にかなっている。
荒田:僕もそう思います。コロナ禍も落ち着いてきたのでここから再スタート。10年目にして1年目って感じです。新しいアルバムを作っているんですけど、各国の人を呼んで作れればと思っています。海外のアーティストが、なにを思っているのか、普通に友達になって話してみたい。
大和田:いまの時代、アジアと親密になっていくのはいいと思います。楽しみにしています。

大和田俊之
慶應義塾大学教授。専門はポピュラー音楽研究。『アメリカ音楽史』(講談社)で第33回サントリー学芸賞受賞。他に『アメリカ音楽の新しい地図』(筑摩書房)、長谷川町蔵との共著『文化系のためのヒップホップ入門1、2、3』(アルテスパブリッシング)など。
荒田 洸
“エクスペリメンタル・ソウル・バンド”を標榜するWONKのバンドリーダーであり、ドラムスを担当。
@hikaru_pxr
Licaxxx
DJを軸にビートメイカー、エディター、ラジオパーソナリティーなどさまざまに表現する新世代のマルチアーティスト。
@licaxxx