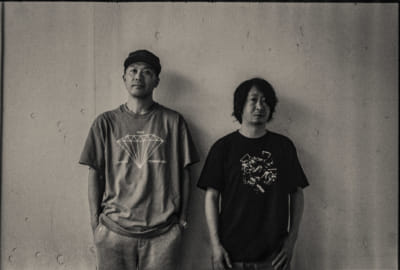カルチャーにまつわるあれこれをテンション高く書き散らかすライター、木津毅が各分野で活躍する映画好きと気ままに話す対談連載がスタート。
第1回の対談相手は、漫画家・田亀源五郎。多数の賞を受賞した『弟の夫』で一般的にも知られるようになった田亀氏だが、彼は何よりも、それ以前から30年以上にわたってハードなポルノ作品を描き続けてきたゲイ・エロティック・アートの巨匠である。木津が編集した田亀源五郎の語り下ろし本『ゲイ・カルチャーの未来へ』では自身の生い立ち社会やアートに対する見解まで話してもらったが、プライベートで会うときはだいたい映画の話かヒゲの男の話をしているわけで……。
ということで、今回話すのはフィンランドが生んだ偉大なゲイ・エロティック・アーティストの半生を描いた『トム・オブ・フィンランド』。日本ではあまり知られていないが、本国ではいまや公的に切手のデザインになるほどの知名度を誇る人物である。レザーに身を包んだマッチョな男のエロスを描き続けた彼の半生を知ることは、同時に激動のゲイ・ヒストリーを知ることでもある――。そんなトム・オブ・フィンランドと海を隔てた同志とも言える田亀氏は、『トム・オブ・フィンランド』をどんなふうに観ただろうか。
“国の誇り”となったトム・オブ・フィンランド
映画『トム・オブ・フィンランド』予告
木津:映画『トム・オブ・フィンランド』の話をするなら、「日本のトム・オブ・フィンランド」とも呼ばれる田亀源五郎さんを置いて他にいないということでお呼び立てしたんですけど(笑)、まずは、映画の印象はいかがでしたか?
田亀:うん、おもしろくて、よくできている映画だと思いましたね。感動もするし……とくにラストにわたしはぐっと来ましたし。
木津:そうなんですよね。すごく観やすい、ウェルメイドな作品ですよね。僕の第一印象は、身も蓋もないですけど、しっかりお金かかっているなって(笑)。アカデミー賞の外国語映画賞のフィンランド代表作品に選ばれたことからもわかるように、フィンランドが国を挙げて作っている感じがするというか。でもそれって、冷静に考えればすごいことで。トム・オブ・フィンランドって、もとはアンダーグラウンドのゲイ・エロティック・アーティスト――要はポルノ作家ですから。
田亀:そうだね。ここ数年、フィンランドはトム・オブ・フィンランドの存在を世界に知らしめていますからね。記念切手を販売したときも世界から注文が殺到して、郵便局のサーバーが落ちたなんてニュースもあったぐらいに(笑)。
木津:そうだったんですね。
田亀:空港なんかでも普通にトム・オブ・フィンランドのプリントのトートバッグとか売っているぐらいですからね。東京レインボープライドのフィンランド大使館のブースでトム・オブ・フィンランドのグッズを売ったりだとか、近年フィンランドは本当に彼をプッシュしている。
木津:とくに欧米で、ここ数年のトム・オブ・フィンランドの再評価はすごいなと僕も感じていたんですけど、何かそのきっかけはあったんですかね?
田亀:彼の作品をアートとしてオーバーグラウンドでしっかり評価したいという流れが、アメリカを中心にここ20年ぐらいあったんですよ。私の知っているニューヨークのコンテンポラリー・アートのギャラリーがすごく推していたりだとか、そういう動きがあった。
木津:ええ。
田亀:とくに、2013年にMOCA(ロサンゼルス現代美術館)でトム・オブ・フィンランド展が行われたというのは大きな節目になったと思います。
木津:なるほど。フィンランドでも2014年にトム・オブ・フィンランド展が開かれたそうですしね。それもやっぱり、とくに2010年代における世界的なLGBTQライツの高まりとも同期しているわけですけど。でも、そのなかでトム・オブ・フィンランドが特別なのは「エロ」がその作家性の中心にあることですよね。
田亀:ただ、フィンランド的には逆輸入って感じだったと思いますよ。アメリカでそれだけ知られていると言っても、じゃあフィンランドで有名かといえばそうでもないですし。
木津:ああ、なるほど。だから、映画としてもグローバルにアピールするような作りになっていますよね。
田亀:そうだね。「国の恥」であったことを「国の誇り」に変える、という。同性愛という恥とされていたことを彼はアーティストとして表現に変えていくけれど、映画もまた、そうした「国辱」とされていたものが「プライド」というものへ変えていくという流れになっている。そこがうまく重なる作りになっていると思いましたね。
木津:フィンランドは同性婚も認められていますし、いまでこそLGBTQライツが進んでいる国だという印象がありますけど、1971年まで同性愛行為が禁じられていたそうですね。映画はその前の時代をしっかり描いていますね。
田亀:うん。オスロ・オリンピックのときにハッテン場の浄化があったみたいな描写がありますけど(笑)、ああいうことって1964年の東京オリンピックのときもやっぱりあったみたいで。
木津:へえー! その辺もアンダーグラウンドの歴史にきちんと触れているという。
田亀:ですね。
木津:映画では彼の下積み時代というか、まさにトム・オブ・フィンランドが世に出るまでも描かれているんですけど、田亀先生もそのあたりは共感するところがあったんじゃないですか?
田亀:私が一番「これこれ」って思ったのは、自分の知らないところで作品が複製されているというところですね(笑)。自分に対するビジネス的な利益をまったくもたらしていないという。それで、周りのスタッフが動いてくれることによって自分の利益になっていくというのは、エロティック・アート界隈ではよくあることですね。
木津:ああー。それはポルノが下に見られているということもあるんでしょうね。
田亀:あると思いますよ。それは消費物という観点しかないということで。作品であると思われていない。私は『日本のゲイ・エロティック・アート』という本を編集するなかで、そうした価値観に抵抗してきました。だから、アーティストとしてというよりは、アーティストに対する扱いという点で『トム・オブ・フィンランド』に共感するとことはありましたね。
木津:なるほど。僕がこの映画で一番感動したのは、トム・オブ・フィンランドがアメリカに呼ばれて、個展を開く場面で。そこではアートをシェアしていると同時に、ある種のコミュニティが生まれているじゃないですか。いまでこそ国を挙げてプッシュするアーティストになりましたけど、そこに至るまでにはどこまでもインディペンデントな繋がりがあって、そのネットワークでこそ歴史が前に進んできたという。
田亀:ですね。あと、クライマックスで出てくるのもインターナショナル・ミスター・レザー・コンテストでしょう。あれも、知らないひとからすると単なるフェチのお祭なんだけど、実際はゲイ・ライツ的な観点でもすごく重要な動きでもあるし。だから社会的な意味合いがちゃんとあるんですよね。
木津:そうですね。
田亀:それは日本だけでなく世界でも欠けている視点だと感じるので、重要なポイントだと思います。
ポップな絵のなかで実現するゲイのハピネス
木津:これは素朴な疑問なんですけど、トム・オブ・フィンランド以前からレザー・カルチャーはゲイ・コミュニティのなかでも一般的だったんですか?
田亀:どうなんだろうね。そこら辺は私も都市伝説的にしか知らなくて。いまのレザー・カルチャーのフォーマットはトム・オブ・フィンランドの絵によって生まれたというのは定説ではあるんですよ。
木津:やっぱりそうなんですね。
田亀:でもそれ以前にレザー・カルチャーがなかったかというと、私はそうとは思えないんですよ。それはいろいろあったんだと思う。だから私の推理では、世のなかにあったそうした欲望にくっきりとした形を与えたのがトム・オブ・フィンランドなんじゃないかなと。
木津:なるほど。さっきのコミュニティの話で言うと、レザーがひとつの制服というか、コードになっている。
田亀:というか、コミュニティのなかではレザーがアイデンティティなんですよ。どうも“レザーマン”というのがアイデンティティとしてあるようで、海外では私も「お前はレザーマンか」と訊かれて、「うーん、好きではあるけど、そこまでどっぷりではなくって……」みたいな感じになってしまうんだけど(笑)。
木津:はははは!
田亀:それぐらいアイデンティティと結びついてはいるんですよね。それはレザーがバイカーと結びついて反逆やアウトローのイメージだったことが、ゲイが同様に犯罪と見なされていたことと重なっているとは考えています。
木津:なるほど。
田亀:ただ、トム・オブ・フィンランドの絵を見ていると必ずしもレザーだけでなく、カウボーイとかアーミーとか水兵とか、男っぽい男のセクシーなモチーフがわりと満遍なく入っているんですけど、イメージとしてレザーがピックアップされやすい。で、ご本人もそれに同化していったところがありますね。私の印象だと、後期になるにしたがってコミュニティに根づいたレザーの描写が増えている気がします。
木津:そうなんですね。映画でうまいのは、トム・オブ・フィンランドの作品に幾度となく登場する“Kake(カケ)”というキャラクターが視覚化された状態で現れるところですよね。彼の理想の男像であり、分身でもあるという存在ですけど。トウコ(トム・オブ・フィンランドの本名)の人生の重要な局面で、彼と出会い、そして自身のアイデンティティを確立していく姿が映画的に描かれている。
田亀:そこはやっぱり、映画ならではだよね。Kakeっていう存在が一種のアイコンだとしても作家の全人生にわたって存在していたということはないだろうけど、それを要所要所で視覚化するのは綺麗な構成だなと思いました。
木津:Kakeがまず象徴するものってゲイ・エロティシズムなりゲイのリビドーだと思うんですけど、やがてゲイ・プライドの象徴のようなものに映画のなかでなっていくんですよね。要するに、エロとアクティヴィズムの結びつきがトム・オブ・フィンランドをモチーフにすることによって自然と示されている、という。そこら辺は田亀先生のポリシーと共鳴するところですよね。
田亀:そうだよね。私がトム・オブ・フィンランドに惹かれるのはそこがやっぱり大きいです。ただ、彼が映画で描かれたほどアクティヴィズムと不可分だったかは、私にはわからないですけどね。そこは映画のフィクション要素なのかなという気もしますね。
木津:それもやっぱり、いまトム・オブ・フィンランドをどう語るかという視点ですね。
田亀:ですね。彼の精神性の核の部分からはまったくズレていないと思いますしね。その上でフィクションでどうやって味つけしていくかという……たとえば、アメリカで彼をバックアップしてくれるゲイ・カップルが登場しますけど、あれはフィクションなんですよ。
木津:そうだったんですね。
田亀:実際はひとりで、性的にすごく奔放な人で。私も個人的に知っている方なんですけど。で、おもしろいのは、彼のルックスと役割があの映画ではふたつに分けられている感じがするんですよ(笑)。
木津:へえー! それは田亀先生ならではの裏話ですね(笑)。
田亀:そういう印象を私は受けましたね。そういう形での史実のエッセンスはあちこちに入っているんだと思いましたね。
木津:あらためてですが、田亀先生にとって、トム・オブ・フィランランドの魅力ってどういうところにあると思いますか?
田亀:うーん、最初に出会ったときは何が魅力かという以前にこんなの見たことないというインパクトのほうが大きかったから(笑)。
木津:(笑)
田亀:ぶっちゃけた話、私の性的な好みとはトム・オブ・フィンランドはズレてるんですよ。私はサドマゾヒズムにオブセッションがあるけれど、彼の作風はそうではないので。ただ、ドローイングとしての完成度がここまで高いとやっぱり圧倒されますよね。しかも、原画を見るとすごく小さいんですよ。
木津:そうなんですね! あ、でもたしかに、映画でもそう描かれていました。
田亀:うん、A4判ぐらい。私がトム・オブ・フィンランド・ファウンデーションと関わりを持つようになった縁で原画を見ることができたんですけど、それがとにかくすごかったんで、なおさら好きになったというのはありますね。
木津:なるほどー。僕はそれこそ21世紀以降に彼の評価が確立してから知ったクチなんですが、いまの感覚で見てもすごくポップなんですよね。切手やバッグになるのもすごくわかるというか。不思議な明るさが彼の作品の魅力のひとつだな、と。
田亀:それは本人の言葉でも残っていて、「現実の世界でつらいことがいっぱいあるんだから、自分の絵のなかではゲイたちはみんなハッピーでいてほしい」ということは言ってましたからね。
木津:それは本当に彼の精神性ですね。映画のなかにも出てきますが、エイズ禍の時代のコンドーム・キャンペーンのイメージも、悲愴感はなくてポップなんですよね。
田亀:うん。あれが面白かったよね。画集を出すために印刷所を探していたらユダヤ系のところしか見つからなかったっていう。あれも、マージナライズされた人たち同士が出会うというニュアンスでしたね。
木津:そうですね。あそこは試写室でも笑いが起こっていました。トム・オブ・フィンランドを知らない人も観やすい映画になっているので、これで新たに彼の表現に出会う人が増えたらいいなと思いますね。とはいえ日本の観客にとっては遠い外国の作家の話でもあるわけですが、田亀先生は日本の観客にこの映画からどういったものを受け取ってほしいと感じられますか?
田亀:そこはやっぱり、この人の生き方がポジティヴなメッセージになればいいなと思います。自分の性欲の赴くままにエロ絵を描いて、それで名声を得ることにもなり、最終的にはこうやって全世界的な評価を受けることになるという意味では、とても稀有な存在なので。そういうことがあったこと自体がポジティヴなことして伝わってほしいなと思いますね。
『トム・オブ・フィンランド』関連作品3選
『トールキン 旅のはじまり』
『トム・オブ・フィンランド』で監督としてのたしかな力量を証明したドメ・カルコスキの次作は、『指輪物語』で知られる作家J・R・R・トールキンの伝記映画。田亀源五郎はトールキンの作品に絶大な影響を受けているので、カルコスキ監督とは何か不思議な縁があるのかもしれません。それはともかく、トールキンのおもに第一次世界大戦頃の青春期を描いた本作では、彼の創作の背景にかけがえのない友情があったことを丹念に示していく。それこそが、彼の闊達なファンタジーに普遍的な力を与えたのだと。2019年8月日本公開。
『恋するリベラーチェ』
ド派手な衣装とステージ、凄まじいテクニックのピアノ演奏で人気を博したエンターテイナーであるリベラーチェの半生を描いた一本。彼がゲイであることは世間的には知られていたが、本人はエイズで死ぬまで隠し通していた。世代的にトム・オブ・フィンランドとほぼ同じなので、あの時代にゲイの表現者として生きるとはどのようなものであったかを探る貴重なサンプルだ。あるいは、エルトン・ジョンの半生をロック・オペラ化した『ロケットマン』と比べて観るのもおもしろいかも。
『ノーマル・ハート』
ゲイ・ヒストリーを描いた映画ではHIV/エイズは非常に重大な出来事として語られるが、もしかすると若い世代にはピンと来なくなっているかもしれない。そんな時代のことを感じるためには、このドラマがオススメだ。1981年、広がりつつあったHIV/エイズを取材するジャーナリストの姿を通して、当時のゲイへの差別や偏見、その苦境、そして生き様を強い筆圧で描き出す。カミングアウトの問題や政治・運動の現場もリアルに語られており、じつに多層的な人間ドラマになっている。配信にて観賞可。
PROFILE
田亀源五郎
ゲイ・エロティック・アーティストとして1986年よりゲイ雑誌にマンガ、イラストレーション、小説などの発表を続ける。国内外で個展を開催するなど美術家としても高い評価を得る。コミックの単行本や画集の刊行のほかにシリーズ『日本のゲイ・エロティック・アート』(ポット出版)などの編著がある。一般誌連載『弟の夫』で第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、アイズナー賞最優秀アジア作品賞を受賞。現在、「月刊アクション」(双葉社)にて『僕らの色彩』を連載中。
木津毅
ライター、編集者。2011年ele-kingにてデビュー、以降、各媒体で音楽、映画、ゲイ・カルチャーを中心にジャンルをまたいで執筆。「ミュージック・マガジン」にて〈木津毅のLGBTQ通信〉連載中。紙版「EYESCREAM」では〈MUSIC REVIEWS〉ページに寄稿。編書に田亀源五郎の語り下ろし『ゲイ・カルチャーの未来へ』(Pヴァイン)。