
ストリートから生まれたアートや、ストリートからの影響を感じさせる表現の数々を広義のアウトサイダーアートとして紹介するこの企画。第二回目に紹介するのは、LAを拠点に活動するグラフィティーライターのREMIO。グラフィティークルー、VTSのファウンダーの一人でもあり、人気スケートブランド、HUFのアーティストアンバサダーとしても活動していることから、アンダーグラウンドのシーンのみならず、ストリートファッションのシーンからのプロップスも高い。彼のこれまでのストーリーについて、昨年の夏、代官山のJINKINOKO GALLERYで行われた彼の個展”Cereal Milk“の際に話を聞いた。


ー地元はどこなんですか? どんな街で育ったのか教えてください。
僕はノルウェーの小さな島の出身なんだ。本当に小さいところだよ。何にもなかったし、今でも本当にローカルな人たちがいるだけみたいな街だよ。街っていうか、ただ木とビーチがあるだけで、超チルな場所かな(笑)。グラフィティーのシーンも勿論無かったし、グラフィティーも無くて、本当に自然だけがあるような感じ。
ーどんな子供時代を過ごしたんですか?
最高だったよ。釣りをしたり、ビーチ沿いの木陰で裸でぼーっとしたりね。本当に最高だったんだ。
ーグラフィティーに関する最初の記憶はなんですか?
あれは6歳のときだったかな、ノルウェーの首都のオスロから来たっていう子がBeastie Boys、ブラックブック(※1)、スケートボードを見せて来たんだ。同時にね。衝撃だったよ。そっから夢中になったんだけど、15歳くらいまでは、他にグラフィティーをやっている人に出会えなかったから、兄貴と連んでることが多かったな。僕と兄貴はB-Boyでもあったんだ。Adidasのセットアップを着たりしてね。
※1:グラフィティーライター同士がお互いのピースやタグを描きあうスケッチブックのようなもの
ーブレイクダンスもやってたんですね。
そうだよ。
ーでは、どのようにグラフィティーカルチャーにのめり込んで行ったんですか?
その、Beastie Boys、ブラックブック、スケートボードを同時に知ったことが切っ掛けだったよ。一気に魅了されたんだ。Hazeがジャケットをやっていた『Check Your Head』と『Ill Communication』だったかな。あれで最初に見たんだ。本当にクールだと思ったよ。ブラックブックは、グラフィティーのスタイルのピースが描かれたいわゆるブラックブック。その後自分もオスロに行く機会があったんだけど、スケートランプにグラフィティーがペイントされているのとかを見ることが出来たんだ。本当に凄い格好良くて、自分もやりたいって思ったね。それから、語学を勉強する為にモントリオールに引っ越して、英語とフランス語を学んだんだけど、そこでは沢山のグラフィティーを見ることが出来たよ。90年代のね。凄いドープだったな。
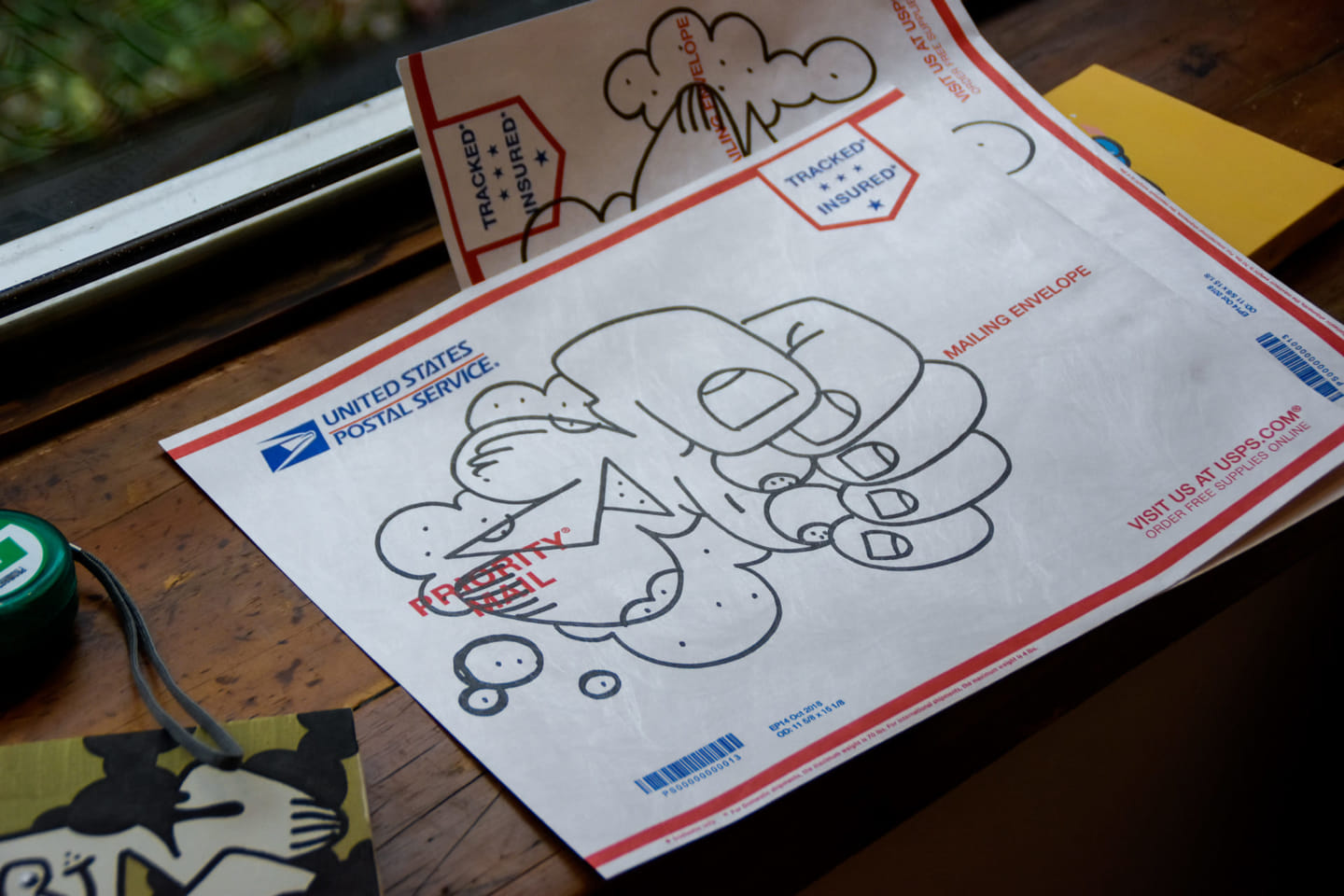
ーその頃、何歳くらいだったんですか?
10歳かな。引っ越したとき、僕と兄はギャングに入ったんだけど、ギャングが何かもよく分かってない小さい子供だったんだ。だから、歳上の奴らにこういう服を着ろって言われたりして。痩せっぽっちの小さなギャングだったよ。
ー自分自身がどんなカルチャーから影響を受けていると思いますか?
グラフィティーとスケートボードだね。スケートボードにも凄いハマってたんだ。
ー今もスケボーはしてますか?
やってるけど、ちょうど日本に来る前にお尻を怪我しちゃったから、いまはユルい感じでやってるよ。
ー最初のペイントを覚えてますか?
最初に誰かとペイントに行ったのは、学校の帰りに行ったトレインヤードだったんだ。それまでは兄貴と一緒に、自分たちで作ったスケートランプとかにペイントしてたんだけど、他人と初めて行くってなったタイミングは電車でさ。川沿いで橋の下のところだったよ。そこで高校の他のグラフィティーライターに出会って、一緒に電車にペイントしたんだ。ペイントした電車が街を走ってクールだったよ。電車が動き出したら飛び乗ったりしてね。
ー初めてのペイントが電車だったんですね! 夜中にですか?
昼間にだよ。キッズだったね。

ーHUFとの関係はどのように始まったものなんですか?
僕はTWISTと一緒に働いていたことがあるんだけど、彼がadidasとコラボした時にインストールを手伝ったんだ。その時にHUFのボスのKeith Hufnagelと出会って、そこから連絡をとるようになったんだよ。彼のお店用にアイテムを作って、それを彼は売ってくれたりしたね。彼がLAに引っ越すタイミングでたまたま僕もLAに引っ越したんだ。その後に、彼のオフィスの中に自分のスタジオを作ったりと、今も良い関係が続いてるよ。
ーソフビやスカルプチャーなどの立体の作品も作っていますよね。普段のペイント作品を作るときとで、製作時のスタンスにはどのような違いがありますか?
自分は自分の作品を常に2Dでしか考えていなかったんだけど、ソフビはHAROSHIが作るのを手伝ってくれるんだ。僕はこういう風に3Dで描いたりしないし、いつも2Dだから。HAROSHIはペイントしたキャラの横側や裏側がどうなってとかを考えてみなよって言ってくれるんだけど、裏側がどうなってるとか一度も考えたことなかったから。それで1つ頑張って粘土で作ってみて、HAROSHIに送ってみたんだ。彼には2Dの作品が3Dで想像できるんだ、クレイジーだよね(笑)。


僕が送ったものに対して、HAROSHIが少し手を加えて送ってくれて、それにまた僕が手を加えてっていうのを繰り返して、満足できるものが完成したんだ。変な感じだよね(笑)。


ーJINKINOKOで行った個展”Cereal Milk”では、様々なスタイルの作品を披露していましたよね。より抽象的なペインティング作品なども製作されていましたね。
そうだね。僕は常に異なるスタイルの作品に取り組んでいるんだ。自分のベースになっているグラフィティーのスタイルのものもあれば、より自分の頭の内側を表現しているものもあるっていう感じかな。


ーグラフィティーのカルチャーは昔と比べて、様々な意味で大きなものになって来ていますよね。アメリカではBEYOND THE STREETSのような大きな展示が行われたり。この状況をどう思っていますか?
そうだね。クールなことだと思うよ。もっと沢山の人達がグラフィティーを始めたら、もっと沢山の人達が自由になれるからね。だって、普通の人達でも、マーカーさえあれば誰でもグラフィティーは出来るんだよ。だろ? みんなグラフィティーをやってるときは笑顔になるんだ。楽しいことだからね。
ー日本のグラフィティーカルチャーをどう思いますか?
クールだと思うよ。好きだね。日本におけるグラフィティーの存在っていうのは、日本の普通の社会とは全く違う存在だろ。グラフィティーを日本でやるっていうのは、凄いプレッシャーのかかることだと思うんだ。社会に完全に逆らうっていうことだからね。そういう状況の中でグラフィティーをやることで自由になれたと感じたら、本当に自由になれたってことだよ。
ーこの先やりたいことは?
グラフィティー。
ーあなたにとって、グラフィティーの最も魅力的な点はなんですか?
Freedom.
REPORTER PROFILE
From the Every Outside
From the Every Outside Vol. 1:SECT UNO by Maruro Yamashita
Interview&Text_Maruro Yamashita







