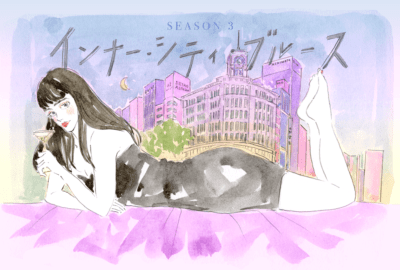毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の連作短編シリーズ「インナー・シティ・ブルース」。混乱を極める東京の今と過去をつなぎながら、シーズン2には新たな登場人物たちを迎え、さらに壮大なナラティブを紡ぐ……。
【あらすじ】
2020年のある夏の土曜日の朝、丹念潮は、中央区明石町にある聖路加国際病院に呼び出されていた。呼び出した相手は、空津勇。第一機械工業の会長である彼は、ここへ検査入院して過ごしており、秘書を通じてなぜか平社員の潮に病室まで来るよう命じてきたのだ。潮は大体の予想はつけていたが、長い前置きの後、空津勇は予想通り、海舟おじいちゃんの話をはじめた……。
2020年8月15日 午前9時
「丹念君はこの病院は初めて?」
「はい。豪華でびっくりしました。オフィスビルが隣にあるんですね」
「聖路加ガーデンのことか。君は総務部だから、汐留の電通には行ったことがあるよね?」
「ええ」
「汐留シティセンターができるまで、電通はあそこに入っていたのだよ。移ったのは2002年だったかな」
「電通が入っていただけあってオシャレですね。隅田川にも面しているし」
「私はね、このあたりで生まれ育ったんだ」
老人はおだてるに限る。
「えーっ、こんな東京の真ん中でですか」
「でも何故か東京大空襲では焼夷弾がひとつも落ちなかったんだ。これについて噂があるのは知っているかな?」
90年代生まれの自分に、いきなり太平洋戦争トリビアを訊かれても困る。
「いいえ」
「あれを見なさい」
老人が指さしたガラス窓の外にキリスト教会らしきものがみえた。
「聖ルカ礼拝堂。竣工は昭和11年。設計したのはフランク・ロイド・ライトの弟子だったアントニン・レーモンドだ。アメリカに帰国したレーモンドは、太平洋戦争が始まると空軍のコンサルタントになった。日本建築に詳しかった彼は、どうすれば効率よく東京を焼け野原にできるかの研究に協力させられたんだ」
「はあ」
「しかし彼は、自分が精魂を傾けた建物が燃やされるのが嫌だったんだろうな。上層部にかけあってこの一帯を目標から外してもらったらしいのだよ。おかげで私の実家は燃えずに済んだというわけだ。だから海舟さんと比べると子ども時代は恵まれていたといえるかもな。もっともしょっちゅう腹はすかしていたけどね、ハハハ」
マスクをしたまま高らかに笑う老人の名は空津勇。第一機械工業の会長である彼は、新型コロナのせいで海外視察の予定が無くなったため、2020年の盆休みを検査入院して過ごすことに決めた。ところがその最中に何を思い立ったのか、秘書を通じて僕に土曜の朝イチに病室まで来るよう命じてきたのだ。平社員の僕が断れるわけがない。
会長が入院していたのは、中央区明石町にある聖路加国際病院だった。建物は明るくて清潔そのもの。なにより変な匂いがしないのがいい。
アルコールとアンモニアが混じった病院特有のあの匂いを嗅いでいると、生気を奪われていく気がするのは僕だけじゃないはずだ。でも入院するのがここなら、自分の死を想像しなくて済むだろう。だからセレブ御用達の病院と言われるのかもしれない。
ホテルのようなインテリアの病室中央に据えられた巨大なベッドの上で胡座をかいている会長は、僕を立たせたまま、コロナ後の日本経済の展望から延期された東京オリンピック、昨日亡くなった渡哲也の思い出まで早口で喋り続ける。
この世代の人間は何か重要なことを話すとき、あえてなかなか本題に入らないものだ。社内で大っぴらにしたくない事柄なのは間違いない。そうでなかったら会社が休みの日に僕を呼ぶ理由がない。海舟おじいちゃんに関する話だろうことだけは想像がついた。
「ところで丹念君は、私と君のおじいさんの争いについて、どの程度知ってるのかな?」
やっぱりそうだった。「空津サーガ」を書くためにネットで色々調べてはいるけど、下手なことを言うのはよしておこう。
「正直いうとよく知らないんです。まだ小さかった頃の話なので」
会長が「嘘をつくな」という表情をする。
「空津本家の当主だった海舟さんは、社長就任確実と言われながら緊急取締役会のあと突然会社を辞職した。代わりに社長になったのは、大した実績もあげていないのに常務になっていた私だ。今では、婿養子でありながらカリスマ性を発揮していた海舟さんを妬んだ分家の私が仕掛けたクーデターというのが定説になっている。でも実をいうと私は海舟さんを兄のように慕っていた」
「そうなんですか」
「海舟さんの件はやむを得なかった。これは内密にしてほしいんだが、彼は会社を兵器製造から撤退させることを目論んでいた。戦災孤児らしい正義感だな。しかし軍事部門に携わっているからこそ得られる利権がある。海舟さんの考えを知って慌てた株主がかついだのが私だったというわけだ」
知らなかった。今では中国や韓国の悪口ばかり言っているおじいちゃんが、そんな格好いいことをしようとしていたなんて。
「君に頼みがある」
ようやく本題に入った。
「これはまだ役員以上しか知らない機密事項なのだが。我が社は造船部門を切り離すことにした。ビッグ・ヒット・グループと合弁会社を設立して、事業移管する予定だ」
造船業は、第一機械工業が創業してまず最初に手がけた事業だ。海外とのコスト競争に巻き込まれて、巨額の赤字を長年垂れ流していたけど、会社が意地で支えているという話だった。
「ビッグ・ヒット・グループって韓国の財閥ですよね? 対等の立場で船を作るんですか?」
「残念ながら、新会社への出資比率は向こうが60%、こちらが40%だから実質的には事業売却だ。しかし十年間は日本側の雇用に手を付けない特約条項を飲ませることに成功した。これ以上良い条件をつけられるチャンスはもう来ないだろう」
「新会社に行く人は給料も福利厚生も当分は今のままなんですね」
それなら話に乗らない手はない。新会社に移籍する社員からの反発も抑えられるし、なにより会社のバランスシートが劇的に向上する。
「ところがだ。交渉の最終段階で向こうが言いだしてきたのだ。海舟さんの『千駄ヶ谷オヤジのご意見無用』とかいうポッドキャスト。あれを止めさせろ。そうでなければ特約は飲めないとね」
「あのポッドキャストをおじいちゃんがやっていることが、ビッグ・ヒットに知られちゃったんですか」
「あそこにはKCIAのOBがたくさん天下りしているからね」
「でもおじいちゃんは会社とはもう無関係じゃないですか」
「向こうにしてみたら海舟さんは今も創業家の当主で大株主なのだよ。もしこの件が韓国のマスコミにすっぱ抜かれたらビッグ・ヒットもこれ以上動けなくなる。だから私は提案を受け入れることにした。ということでお願いしたいのだ。海舟さんにポッドキャストを止めさせてほしい」
「ちょっと待ってください。僕もあの放送内容は酷いとは思いますよ。でも会社の側からおじいちゃんに頼むわけにはいかないんですか」
「そんなことをやったら海舟さんはこの計画もポッドキャストで話してしまうんじゃないかな。そうなったらどうなると思う?」
日本中のネトウヨが黙っていないだろう。合弁事業は頓挫間違いなしだ。
「会長のお考えはわかりました。でも正直言って僕には自信がありません。実はこれまでも父や叔父が何度も説得してダメだったんです。なのに自分に出来るとは思えないんですよ。そもそも僕、本当の孫でもないですし」
会長が僕を睨んだ。
「君の自信のある無しなんて関係ないんだ。これは社命だ。それに君の方にもやらなければいけない理由がある」
「というと?」
「ビッグ・ヒットとの交渉責任者は小樽君なのだ。君のご家族は何かと彼の世話になっているだろう? これがうまく行ったら役員に昇進するのに、彼のキャリアを潰したいかね?」
小樽部長か。海舟おじいちゃんの元側近、僕にコネ入社を手配してくれた恩人。お母さんの元カレ。そして澪姉ちゃんの父親でもある。
「わかりました。やるだけやってみます」
会長の表情が和らいだ。
「なにも君に責任を全部押し付ける気はない。私も失敗したくはないからね。だからある人に君のサポートに入ってもらうことにした。もうじき来ると思うんだが……」
会長がそう言い終わるか終わらないかのタイミングで、病室のスライドドアが勢いよく開いた。
「こんにちはー、会長。遅くなってごめんなさい。着付けに手間取っちゃって」
病室に入ってきたのは、囲間雨だった。ピンクのマスクにピンクの留袖。赤と白の格子柄が入った帯を絞めて家紋が入った黒い羽織をはおっている。友達の披露宴にこの格好で行ったら、花嫁よりもチヤホヤされて恨まれそうな可愛さだ。
「おお、雨さん。今日はいちだんと綺麗ですな。お仕事は元気にやっておられますか?」
「ええ。順調です」
ポンコツOLが嘘を言った。
「囲間さんが僕をサポート? この件が総務部案件だからですか?」
会長は首を振って否定する。
「いや、それはちがう。海舟さんは大学時代にジャズ・バンドでピアノを弾いていたそうじゃないか。そんなモダンボーイがあんな差別的なことを話しているのがずっと不思議でね。ここのベッドに寝ているとき、ふと思ったんだよ。もしかすると彼は幽霊に取り憑かれているんじゃないかと」
「幽霊?」
「海舟さんの最初の奥さんは岬さんという人だったんだが、とても霊感が強い人でね。私はあの人の霊が海舟さんに取り憑いているんじゃないかと思ったのだよ。雨さんに相談してみたら、その可能性もあるとのお答えだったから……」
「待ってください。なんで会長が事務職に相談するんですか? しかも敬語?」
「丹念君。雨さんに失礼だぞ。囲間家は東京が江戸だった頃からこの街を護ってきた陰陽師の一家のお生まれだ。江戸時代には徳川御三家と同等にあたる……」
「会長、うちは御三家より格下です。前田家よりは上ですけど」
囲間さんが訂正する。
「ああ、そうですか。失礼しました。それはともかく明治の創業以来、我が社は折につけ助けていただいてきたのだ。雨さんもその力を受け継いでおられる」
囲間雨が社内で特別扱いされている謎がようやく解けた。
「会長、姉さんたちと比べないでくださいね。わたし正式な修行はしていませんし」
「ご謙遜を。素質はあなたが一番と伺っていますよ」
「ちょっとした霊なら、わたしでも除霊くらいは出来ますけど。でも……」
「でも?」
「ひとつ条件があります」
囲間雨の瞳が妖しく輝いた。
「その条件とはなんですか?」
「今日は土曜だから休日勤務扱いにしていただけます? わたし、振替休日って一回取ってみたかったんですよね」
2020年8月15日 午前10時
千駄ヶ谷の空津家を訪れるのは久しぶりだった。いつものように勝手口から入ろうとすると、死んだ母さんそっくりの人がぼっと立っている。まさか岬さんの幽霊?
「潮ちゃん、とつぜん何の用?」
よく見たら澪姉ちゃんだった。僕らが来るのを外で待ってくれていたらしい。囲間さんを紹介しようとしたら、彼女は僕の横をすり抜けて澪姉ちゃんに近づいていった。
「空津澪さんですね。お話は丹念君からうかがっていました」
そう言って囲間さんは自分の右の手のひらを澪姉ちゃんの左頬にあてた。動揺する澪姉ちゃんをよそに囲間さんは目に涙を浮かべて感極まった表情をしている。
「感応者の血を受け継がれているのですね。お辛かったでしょう」
「なんすか、感応者って?」
僕は尋ねた。
「己の運命を知り、他人の想いを感じとる人のこと。古代の日本には結構な数がいて、神社の巫女さんには必ず感応者の女性が選ばれていたそうよ。今では秘境といわれる場所にしか居ないと聞いていたんだけど、東京にもいたなんて」
澪姉ちゃんの件について、囲間さんにもっと早く相談しておくべきだったと僕は後悔した。
「姉ちゃん、調子はどう?」
澪姉ちゃんは答える。
「ようやく立ち直ってきたところかな」
無理もない。記憶喪失中の彼女にとっては、母だと思っていた人が赤の他人で、姉だと思っていた人が母だったことをつい最近知らされたばかりなのだ。しかも深遠な意味を帯びていると信じていた記憶喪失も、酒に酔った勢いで運河に飛び込んだときに頭を打ったためだったことが判明していた。
「おじいちゃんは?」
澪姉ちゃんは肩をすくめて皮肉っぽい笑みを浮かべた。
「わたしとちがって絶好調って感じ?」
僕らは勝手口から家にあがると、台所の向こう側にあるおじいちゃんの部屋に静かに近づいていった。襖の隙間からしわがれ声が聞こえる。ポッドキャストの収録中のようだ。
「2002年にオーストラリアの作家がネット上で発表したある小説が、コロナ騒ぎを予言していたと言われているんです。今は消されてしまったんですが、コロナ騒動の裏にある真の計画をリークしていたからという説があるんですな。背後にいるのは勿論ディープステートです。奴らはマスゴミを通じて「ニューノーマル」や「新しい生活様式」を押しつけてきている。しかし我々はそれを無自覚に信じていいのでしょうか? いや、数値を故意に膨らましている日本政府を信用してはいけません。今やディープステートの手に落ちつつありますからな。何よりの証拠がムーンショット計画なんですよ。それを阻む意味でも今度のアメリカ大統領選ではトランプさんに何としてでも勝ってもらわないといけない。みなさん分かりますよね?」
さっぱり分からない。ていうか、トランプに「さん」をつける時点で生理的に無理。僕は囲間さんにひそひそ声で話しかけた。
「あのー、おじいちゃん、単純にボケちゃってるんじゃないかと思うんですけど。もう80歳だし」
囲間さんは僕の方を見ずに独り言を言った。
「思っていたのと違う」
そして「失礼します」と言って襖を開けると、海舟おじいちゃんに近づいていき、右の手のひらを彼の左頬にあてた。
「やっぱり違う」
呆気にとられているおじいちゃんを残して囲間さんはこちらにスタスタと戻ってくる。
「丹念君、あなたのおじいさまはボケてない」
「じゃあ岬さんの霊に取り憑かれている?」
「いいえ。取り憑いているのはもっと邪悪な何か。でもお祓いはできない」
「さっきは除霊できるって言っていたのに」
「除霊できる対象は、特定の人格を持つ悪霊に意思を乗っ取られている場合。でもこの邪悪な何かは空気のような薄いもので、おじいさまの心に入り込んで不安を増幅させているの」
たしかにおじいちゃんが不安を抱く理由はいくらでもある。会社からの追放、ひとり娘が最初の妻と同じように亡くなったこと。二番目の妻との離婚。義理の息子との不仲。そして孫娘の荒れた私生活。
「おじいさまはいつを境に今みたいなお考えになったのかしら」
囲間さんが尋ねてくるけどわからない。
「うーん、物心ついたときはもうこっち系だったからなあ」
澪姉ちゃんが口を挟んできた。
「お兄ちゃんによると、サッカーの大会があったときみたい」
「2002年の日韓ワールドカップの時ね。確かにあの頃から急にそういう人が増えたって聞いたことがある。丹念くん、これはあなたのおじいさまだけの問題じゃないかも。すぐに出かけないと」
囲間さんはハンドバッグからスマホを取り出すと勝手口から飛び出していった。タクシーを拾うつもりなのかもしれない。その姿を見送りながら澪姉ちゃんが言った。
「なんだー。お昼を食べていってもらおうと思ったのに。昨日の夜、たくさんキュウリちくわを作って残っちゃったんだよね」
「お母さん、料理に困るとよくあれ作っていたよね。懐かしいな。僕は食べてこうかな」
「潮ちゃん、なに言ってんの。あの人についていかないと」
澪姉ちゃんはそう言うと、冷蔵庫から大きなキュウリちくわがパンパンに入った大きなタッパーを無理矢理僕に手渡した。
「あとで食べて」
「ありがとう」
「それと」
澪姉ちゃんは玄関前でタクシーを待つ囲間さんが聞こえないように声をひそめた。
「触られたときに分かったんだけど、あの人、わたしと同じように人の感情を感じ取っていると思う。しかもわたしなんかよりずっと強く。もし本当に悪霊なんてものがいたら耐えらないよ。だから潮ちゃん、あの人を守ってあげて」
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク