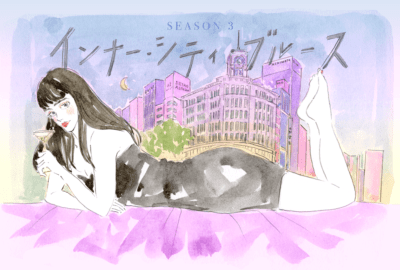毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の連作短編シリーズ「インナー・シティ・ブルース」。混乱を極める東京の今と過去をつなぎながら、シーズン2はついに大団円を迎える。
【前回までのあらすじ】
池袋で襲いかかってきたBボーイたちの手を逃れ、丹念潮と囲間雨は、サンシャイン60から拡散されていた妖気の流れを止めるミッションに成功する。しかしそれで潮の祖父・空津海舟が完全にネトウヨでなくなるわけではなく、彼の魂を救うには家族の愛が必要だと雨に諭されるのだが……。空津家の人々のその後は? 人生は運命で定められたものなのか? 澪は自分のいるべき場所へ帰れるのか? 空津家サーガ、いよいよ最終話!
「『これだけ長い間、国立競技場のそばに住んでいたんだ。東京オリンピックを見届けてからじゃないと、死んでも死にきれない』故人はそう申しておりましたが、残念ながら想いを果たせずに逝くことになりました」
空津澪がぎこちなくカンペを読み上げる声が広い会場に響き渡る。
彼女の祖父であり、実質的には父親だった空津海舟の告別式が行われたのは、2021年のホワイトデーだった。
一緒に暮らしていた澪に加えて、海舟にとっては義理の息子である湊と洋、義理の孫にあたる潮が足繁く訪れるようになった2020年の夏以降、千駄ヶ谷の空津家にはかつての和やかさが戻ってきていた。
しかし年明けに体の不調を訴えた海舟が医師の診察を受けた時には既に全身ががんに蝕まれていた。一旦は聖路加国際病院に入院した海舟だったが、3月に入ると桜が観たいと言って千駄ヶ谷に戻ってきた。そして10日未明に、静かに息を引き取ったのである。80年の生涯だった。
勤務先だった第一機械工業から追放されて久しかった海舟だったが、告別式は社葬として執り行われた。海舟の、韓国のビッグ・ヒット・グループとの造船部門合併交渉への貢献に、会長の空津勇が感謝してのことだった。会長は取締役たちにこう語ったという。
「さすが海舟さんだよ。マイナスをあっさりプラスにひっくり返した。ネット右翼的言動について、きっちり謝罪しただけでなく、あちらさんの気持ちをこちらにぐっと引きつけちゃったんだから」
コロナ禍の中、告別式に招かれた政財界のVIPたちは、会場の壮麗さよりも受付を務めたある女性の溢れ出る気品と所作の美しさを口々に褒め称えた。中には逆に深々とお辞儀する者までいたらしい。
その女性とは、総務部からスタッフとして駆り出されていた囲間雨だった。交通整理や香典を扱うことは到底無理と判断された彼女は、上司からお辞儀することだけを命じられたのだが、そのお辞儀だけで告別式のMVPに輝いたのである。
こうした式の一切を仕切ったのは総務部長の沼水ではなく、もとは海舟の秘書だった小樽取締役だった。彼は家族以外ではただひとり、渋谷区の西原にある代々幡斎場まで同行した。
「死は必ず等しく訪れる」とよく言われる。澪はこれまでその言葉がぴんと来なかったが、海舟の棺が炉内に入った瞬間に理解した。これから1時間も経てば、海舟が抱いていた夢や理想を形作っていたあらゆるものは灰と化し、骨壷に収められるほどの大きさになってしまうのだから。
遺言によって、海舟の遺骨は空津家の墓所ではなく、青山霊園にある堺家の墓に収められることになっていた。
待合室の隅で放心状態になっている澪を見て、小樽が近づいてきた。
「おつかれさまです。大丈夫?」
「ええ、大丈夫です。小樽さんこそ、色々ありがとうございます」
「怪我で記憶を一部失っていると、聞きましたが」
小樽は、澪にとって血縁上の父である。年齢がさほど離れていないのは、小樽が澪の母親の満を妊娠させたのが中学生のときだったからだ。しかし満の強い意志によって、澪は海舟と渚の娘として育てられた。
自分の生い立ちを澪が知ったのは、澪が中学二年生のとき満が亡くなったことがきっかけだった。以来、澪と小樽は何度か顔を合わせてはいたが、親子として接することは無かった。澪は視線を合わせないようにしながら小樽に答えた。
「はい。でも生活に支障はありません」
実のところ、澪は記憶を取り戻しつつあった。しかしいざ思い出してみると、忘れていた方がましな記憶の方が多かった。
満が死んだ責任が自分にあると考えた澪は、他人の邪念を感じとる力が極端に強かったにもかかわらず、精神的・肉体的に邪念を浴びる仕事に進んで就いた。だがそのせいで身近な者がストレスのはけ口になった。
怒りは家族だけでなく、第一機械工業に就職して海舟に下僕のように仕えていた小樽にも向けられた。「やり逃げ野郎」と、彼を罵倒したこともある。しかし彼が結婚しなかったのも、澪の出生の隠蔽も、満の強い要望によるものだった。小樽の責任ではない。それでも空津家の近くにいようとする彼について、澪はずっと満に未練があるのだとばかり思っていた。しかし最近はこう考え始めていた。
「小樽さんは自分を罰するために、わざと辛い境遇に身を置いていたんだ」
自分を責めて痛めつけがちな澪の性格は、明らかに父譲りのものだったのだ。彼女は視線を小樽に向けた。
「小樽さん、今までごめんなさい」
澪の表情で何かを察したのか、小樽は言った。
「落ち着いたら、ぜひ私の家族とも会ってください」
「あ、はい」
小樽は満の死後に、結婚してふたりの子どもをもうけていた。腹違いのきょうだいにあたる彼らに澪はこれまで会ったことがなかった。この後会ったところ意気投合して、彼らと生涯にわたる親交を結ぶようになる。
「小樽さん、おつかれさまー」
小樽の背中ごしに、空津湊が声をかけてきた。喪服を着ているが、明るい茶色のロン毛を後ろに束ねたヘアスタイルなので、なにかステージ衣装のように見える。
「ああ、湊さんですか。朝ドラ見てましたよ」
湊は、イケメン俳優クルーズ・ミナトとして、昨秋までNHKで放映されていた朝ドラ『オーエス、オーエス』で、関町桜扮する主人公アッコの兄貴分ハリー星野を演じて、知名度をあげていた。
「いま忙しいでしょう」
「そうでもないっすよ。最終回直後は「ハリー・ロス」とかネットで言われていましたけど。でも朝ドラファンなんて薄情なもんですよ。みんな今やっている『おてもやん』に夢中で、俺のことなんかとっくに忘れちゃっていますからね」
「そんなものですか」
「まあ、『ファミリーツリー』に出たのは、オヤジへの親孝行になったから良かったですけど」
「あの番組も見ました。素晴らしかったです」
NHKの有名人ルーツ探訪番組『ファミリーツリー』で、クルーズ・ミナトを取り上げた回がオンエアされたのは、2020年のクリスマス・シーズンだった。それまで漠然とアメリカ人と日本人のハーフと思われていた彼に、いわゆる日本人の血が入っていなかったことが明らかにされ、ちょっとした話題になったものだ。
それ以上に話題になったのが、湊の性格や嗜好を形成したのが血筋ではなく、他人同士が集まった空津家での生活だったことを強調した番組内容だった。すべてを血筋で説明しようとする『ファミリーツリー』という番組への自己批判にもなっていたこの回は、ギャラクシー賞を獲得し、敏腕ディレクター、奥脇奈那の初期代表作として語られるようになる。
番組のエンディングは、空津家の四人によるジャズ演奏だった。曲目は海舟の提案による「My Foolish Heart」。若い頃プロのジャズ・ピアニストを目指した海舟がピアノを弾き、湊が高校時代から続けているベースを、潮はこの収録のために練習させられたドラムスを演奏した。
ヴォーカルを務めたのは澪で、味わいのある歌声が評判になった。オンエア直後に「金蔵」と名乗るドルオタが、彼女が失踪した地下アイドル、堺マリーナなのではないかとツイッターで呟いたものの、リツイートも「いいね!」の数も一桁台に留まった。
「そういえば母さんが話したいって」
湊は手に抱えていたタブレットを小樽に手渡した。画面の中には湊の母親である渚が映っていた。新型コロナの影響で来日できなかった彼女は、息子の湊に持たせたタブレットごしに前夫の告別式にバーチャル参加していたのだ。
「小樽さん、おひさしぶり」
渚が日に焼けた顔で笑みを浮かべている。70代半ばとは思えないくらい若々しい。彼女の背後の開け放たれた窓の外からは鬱蒼とした熱帯特有の木々が見える。
「おひさしぶりです。今もハワイ島にいらっしゃるんでしたっけ」
「そうよ」
「悠々自適ですか。うらやましいです」
「あら、ひとを隠居のおばあちゃんみたいに言わないで。コロナが流行るまでは、すごく忙しかったんだから。わたし、マウナケアのご来光ツアーのガイドをやっていたのよ」
「マウナケアって、天体観測用の望遠鏡が設置されているところですか」
「そう。夜中の2時頃にワゴンでホテルを回って、観光客をピックアップしていって山道をドライブするの。標高が4200メートルくらいあるから、ハワイなのに山頂では気温が氷点下になる日もあるのよ。そこで寒さに震えながら日の出を待つの」
「それは素晴らしいでしょうね。どこから来た観光客を案内されているんですか?」
「そうね、日本とアメリカ本土からが殆どだったけど、韓国語も少し話せるようになったから、韓国からのお客さんも案内していたのよ」
渚が、自分のルーツの一部が韓国にあると知ったのは、四十代に入ってからである。それから言語をマスターしたことに、小樽は感銘を受けた。
「コロナが収まったら、ぜひ伺わせていただきます」
「家族のみなさんといらっしゃって。澪も連れてきてよ。あの子にはね、こっちで仕事を手伝いなさいって言っているの」
「それは澪さんにとっていいかもしれませんね。もっとも彼女はあくせく働かなくてもいい身分なわけですが」
渚は表情を曇らせた。
「まだ洋さんから話を聞いてないのね。悪いけど彼の相談に乗ってもらえないかしら」
海舟は遺言で丹念洋を遺産執行人に指名していた。
「わかりました。またご連絡させていただきます」
小樽はタブレットを湊に返して礼を言うと、丹念洋に声をかけて廊下の外へと連れ出した。
「丹念さん、海舟さんの遺産に問題があるようだと、渚さんから伺ったのですが」
洋は困惑したような声をあげた。
「それが、お義父さんの口座にお金が全然ないんです。それどころか借金だらけで……」
近年の不動産高騰に、オリンピック会場の至近だったことも加わって、千駄ヶ谷の空津邸の評価額は跳ね上がっていた。それでも海舟が持つ現金や第一機械工業の株式を売却すれば、相続税は支払えるはずだったが、銀行口座を調べてみると預金は底をつき、株式も売却できる状態ではなかったのである。
海舟は会社を辞めたあと、持ち株を担保に銀行から借金して投資会社を立ち上げていた。しかし2008年のリーマンショックの際に大きな損失を出していたのだ。その損失は、相続人である澪が持株を売却しても到底埋められる金額では無かった。
小樽が社内に働きかけて、彼女の持ち株は相場よりかなり高い額で買い取ってもらえたものの、澪は千駄ヶ谷の邸宅を売却せざるをえなかったのである。第一機械工業創業ファミリーである空津本家は、こうして歴史の舞台から姿を消したのだった。
空津家の人々のその後について記しておこう。
空津湊は、俳優クルーズ・ミナトとしてはその後もパッとしなかったが、アメリカと日本を行き来しながら気ままな人生を送った。行きつけのハモニカ横丁のビアホールで酔うたび、「俺の最高の演技はさ、日本映画の中にはない。あの作品にこそあるんだよねー」と遠い目をしながらアメリカで製作されたというインディ映画のタイトルを挙げたが、ソフト化も配信もされていなかったので、実在の作品なのか出まかせなのか確かめようがなかった。
丹念洋は、第一昭和建設工業会社を定年まで勤め上げると、故郷に帰った。そして高校の同窓会で再会した女性と再婚した。人生の終盤に、三度目にしてようやくまともな結婚生活を送ったのである。それは善良さの塊である彼への神様からの贈り物だったのかもしれない。
洋の息子、丹念潮(つまり僕)は、新型コロナの後遺症と戦いながら「空津サーガ」を書き上げたが、投稿サイト「小説家になりたい」での反応はさっぱりだった。地方格差、コンプレックス、ルサンチマンの要素が欠如していたことが災いしたのだろう。
激しく落ち込んだ彼だったが、資質とズレているはずの勤務先でなぜか出世した。代表取締役社長になった小樽涼太と懇意だったために、分不相応な重職を任されたのである。
「今の東京は、感応者には向いていません。お引っ越しをお勧めします」
囲間雨から受けたそんなアドバイスを聞き入れて、空津澪は東京を離れた。移り住んだ先は、空津家唯一の財産として残った伊豆下田の別荘だった。みすぼらしい建物で荒れ果てていたが、千駄ヶ谷の邸宅を手放したことは結果的に正解だった。新国立競技場は年間24億円もの維持管理費に耐えきれずにすぐに廃墟と化し、千駄ヶ谷周辺は野犬の巣窟になったからである。
澪は、別荘をDIYで改装し、庭の畑を耕す日々を過ごした。気がむくとハワイ島に渡って渚の仕事を手伝った。そしてそこで習ったフラダンスを伊豆で教えることで、ようやく経済的に自立できるようになった。
週末や長い休みになると下田の家には、湊や洋、そして潮がそれぞれの家族や友人と訪れ、大いに賑わった。小樽や彼の家族、遠い親戚であるカリスマ・プログラマーの長崎舷とその母の奈美、親友の田畑論や赤城凛といった面々もしばしば姿を見せた。やがて彼らは大きなひとつの家族となった。
感応者としての鋭敏すぎる感覚は澪を悩ませ続けたが、次第に制御できるようになった。
今や彼女は、物心ついてから死ぬまでの全ての時間を平行して生き、それぞれの瞬間を楽しんでいた。こうした時間はその時々の彼女の選択によって数えきれない数の平行宇宙を形成していた。人生が運命で定められたものではなく、ひとつの選択肢であることを澪は体感していたのである。
そして月日が過ぎ去っていった。
ある年の7月24日の明け方、澪はひとり目覚めると直感した。
「今日がその日なのだ」
彼女は水着に着替えると、別荘のバルコニーから直接繋がった階段で誰もいない砂浜へと降りたった。澪は海水に浸かると、ゆっくり泳ぎ始めた。そして浜辺から見えなくなるまで沖へと出ると、その場で目を閉じた。
身体に振動を感じる。しばらく経つと、それは音を伴ってやってきた。大きい。これまでにないほど大きい。
そして澪のもとに遂にやってきた「それ」は、彼女のすべてを押し流していった。
一瞬にも永遠のようにも思えるブランクのあと、澪がゆっくり目を開けると、痩せた老女に覗き込まれていた。視線を横に動かすと、そこは巨大な室内空間になっていて、片側の壁を座席が階段状に埋め尽くしていた。
老女の隣に立っていたライフガードが話しかけてくる。
「大丈夫? 君、なにをやったか、覚えている?」
「えーと」
「プールで溺れたんだよ」
老女が口を挟む。
「私はあれだけ『あぶないわよ』って大声で注意したのに」
「そういうことか!」
素っ頓狂な声を聞いたライフガードは顔をしかめた。
「うーん、この調子だと念のために医者に診てもらわないと駄目だな」
「ぜ、ぜんぜん大丈夫ですから!」
ライフガードは澪を疑いの目で眺めた。
「あとで別の場所で倒れられたりすると、困っちゃうんだよね。本当に大丈夫か、いくつか質問するから答えてくれるかな?」
「はい、わかりました」
「あなたの名前は?」
「空津澪」
「今日は何日ですか?」
「2000年7月24日」
「ここは?」
「東京体育館です」
「今の日本の総理大臣は?」
「森喜朗。のちに東京オリンピックの大会組織委員会会長になります」
「は?」
「ごめんなさい。聞かなかったことにして」
澪はタオルを掴んで、老女と指導員にお辞儀をすると、ロッカーへと走り去り、鏡で自分の姿を確認した。鏡の中には縮れた毛を濡らした13歳の少女が立っていた。
「わたし、帰ってきたんだ」
澪はタオルで水滴を拭き、服に着替えると、カブトガニのような形をした屋根を持つ体育館の外へと出た。そして外苑西通りを千駄ヶ谷駅とは反対方面に駆け出した。ホープ軒を通り過ぎ、千寿院の交差点の向こう側に鬱蒼とした林が視界に入ってくる。茂みの中には懐かしい鉛色の瓦屋根が見えた。
「この家は来年、火事で燃えちゃうのかな? それと東京オリンピックはどうなるんだろうか?」
澪はふとそんなことを思ったが、気にしないことにした。あれはパラレルワールドの未来のひとつでしかない。選択肢は無限にある。そこからなるべく良い選択を行なって、一瞬一瞬を楽しもう。
そして彼女は勝手口の引き戸を勢いよく開けた。あの人が驚いている。
「あらっ、もう帰ってきたの?」
驚くその人に、澪は笑顔で、ずっと言いたかった言葉を言う。
「おかあさん、ただいま」
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク