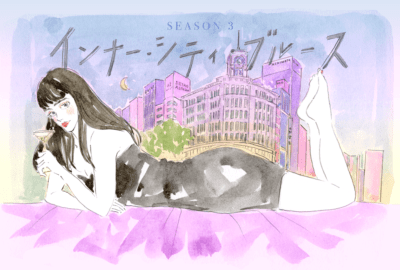毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の連作短編シリーズ「インナー・シティ・ブルース」。混乱を極める東京の今と過去をつなぎながら、シーズン2には新たな登場人物たちを迎え、さらに壮大なナラティブを紡ぐ……。
【あらすじ】
丹念潮と囲間雨は、任務を全うするためコロナ禍にもかかわらず賑わう池袋へと移動し、サンシャイン60を目指した。そこはかつて「巣鴨プリズン」と呼ばれた場所。そして雨はそのビルが地中からの“妖気の煙突”の役目を果たしていたことを見抜く。その真実に気づいた時、ふたりは大勢のBボーイに包囲されていた。しかしなぜか彼らはマスクをしていない……。
僕らを遠巻きに取り囲んだBボーイたちはヒューマン・ビートボックスを奏で続けた。「ブッブ、パッ! ブッブブッ、パッ!」
ビートはノリが良くてご機嫌だったけど、彼らがマスクをしていないのが気になってしかたがない。それ以上に気になったのは、Bボーイたちの瞳がこぞって虚ろだったことだ。
囲間さんが悔しそうに言った。
「わたしミスっちゃった。今日は8月15日。しかも正午ちょうどじゃない」
終戦記念日の玉音放送の時間だ。
「そんな特別な時間に、妖気の流れを正そうとわたしがやって来たもんだから、気配を察した残留思念の塊が妖気をいつも以上に噴き出したばかりか、わたしを妨害しようと人間に取り憑いて操っているのよ」
「でも何故Bボーイにばかりに取り憑いてるんですか?」
囲間さんは答えた。
「きまってるじゃない、残留思念は、生前の自分と形がよく似たものに取り憑くのよ。ほら、生前は日本軍の兵士だったわけだから……」
「Bボーイといえば、坊主頭、キャップ、ブーツ、迷彩のアイテムを着がち……そういうことか!」
Bボーイたちはじりじりと僕らに近づいてくる。囲間さんは僕を見つめて言った。
「丹念君、お願いがあるの。新型コロナのせいでみんなの心は弱っているでしょう? サンシャイン60からの妖気の流れをこれ以上放っておくと大変なことになるわ。ここに空津家のために用意していたお札が四枚ある。あなたにはサンシャイン60の展望室まで行って、東西南北四方の壁にお札を貼ってきてほしいの」
囲間さんから和紙の封筒を手渡された。
「えーっ、僕がですかー?」
「あなたは見たところ霊感ゼロだから、残留思念も手荒な真似はしてこないはず。幻影で惑わすくらいはするかもしれないけど」
僕は「そんな大事なミッションを素人の僕にぶん投げるんですか? 囲間さんが行けばいいじゃないですか!」と叫びたくなったけど、脳裏に澪姉ちゃんの声がこだました。
「あの人、わたしと同じように人の感情を感じ取っていると思う。しかもわたしなんかよりずっと強く」
囲間さんは、常人では耐えられない恐ろしいほどの激痛に耐えながら、今この場所に立っているのだ。
「Bボーイたちはわたしがここで引きつけておくから」
「引きつけるって? 陰陽師だけに、手から聖なる光なんか放ってBボーイを吹っ飛ばすとか?」
「まあ、そういう感じね……あ、でもやっちゃダメか」
「ダメじゃないですよ。ガンガンやっちゃって下さいよ」
「ここ池袋でしょう。しかも土曜日の昼間。そんな場所で大立ち回りをしたら騒動になっちゃう」
そうこうしているうちにBボーイたちは僕らを取り囲んだ。20人以上はいる。
「ブッブ、パッ! ブッブブッ、パッ! ピキピキ!」
ヒューマン・ビートボックスの吐息が顔にかかるくらいの近さに彼らが詰め寄ってくる。このまま僕らはBボーイたちの餌食になってしまうのだろうか。安いスーツを着た僕はともかく、訪問着でおめかしした囲間さんは可哀想というほかない……あっ! 彼女の立ち姿をあらためて見て気がついた。ピンクの留袖、赤と白の格子柄が入った帯、そして家紋が入った黒い羽織。イケるかもしれない。
「囲間さん、暴れまくっても大丈夫です。騒動になんかなりません。池袋でも、いや池袋だからこそ大丈夫なんです」
「どうして?」
僕は説明した。
「池袋といえば、今や秋葉原を凌駕するオタクの聖地と言われているんです。そしてオタク向けのショップは駅の東側に集中しています。つまりこのへんを歩いている人の殆どは老若男女を問わずオタクだと言っても過言ではありません。今日の囲間さんの格好、某大人気マンガのヒロインに偶然そっくりなんですよ。だから大立ち回りをしても皆、コスプレイヤーのパフォーマンスと受け取ってくれるはずです」
「嘘じゃないよね?」
「信じてください。あ、そうだ」
僕はリュックから、澪姉ちゃんが作ったちくわキュウリのパックを取り出した。
「これを口にくわえながら戦ってください。そうすればなおさら皆、信じると思います」
「えーっ、マスクを取るの?」
「これがないと、みんなコスプレイヤーとは信じないんで」
「わかった。やってみる」
そう言うと彼女はちくわキュウリをくわえて臨戦体制に入った。
僕は大声で叫んだ。
「えーっ、K-BOOKSが提供するトップ・コスプレイヤー、雨ちゃんのスペシャル・パフォーマンスです!」
するとどこからともなく人々がわらわらと集まってきて、僕らを取り囲むBボーイたちをさらに包囲する形になった。
Bボーイのひとりが僕の肩に手をかけた。すると囲間さんの右手から放たれた光が、Bボーイを凝固させる。すかさず彼女はキックを浴びせた。ギャラリーは大喝采だ。隙をうかがって僕はBボーイたちが作っていた輪から外へと抜け出した。
サンシャイン通りを全力疾走する。左右に並ぶショップの原色看板が、目に入った瞬間に左右へと流れて消えていく。白木屋、大黒屋、マツキヨ、ABCマート、そしてハードパンク池袋東口店。心臓がバクバクいっている。
「SUNSHINE CITY」と英語で書かれた看板が見えたので、エスカレーターを駆け降り、動く地下歩道を立ち止まることなく走りぬけた。歩道の先にあったインフォメーションセンターの左側に「展望台行き」というサインと扉が見えてくる。扉の奥には展望台直結のエレベーターがあるはずだ。
ところがようやく扉の前にたどり着くと、普通のスチールドアではなく鉄格子が嵌め込まれていることに気がついた。あまりの不気味さに引き返そうとはしたけど、いつのまにか自分以外の客の姿はいなくなっていた。僕は、扉の先に進む以外の選択肢がないことに気がついた。
観音開きのドアから息を殺して中へと入る。そこはどこまでも奥へと続く細長い空間だった。天井にはガラス天窓が設けられていて、床の一部はそこから降り注ぐ光をさらに下階に届かせるようにグレーチング仕様になっていた。両壁には幾つもの鉄格子の入った扉が並んでいる。興味にかられて鉄格子からそっと中を覗くと、背中に「P」と書かれたグレーの作業着を着た男たちがうずくまっているのが見えた。
「P」とは「PRISONER(囚人)の略にちがいない。ここは巣鴨プリズンなのだ。おそらく囲間さんが言っていた「残留思念が見せる幻影」にちがいない。とりあえず一旦、地上に出なくては。
僕は一番近くの非常階段をワンフロアかけあがった。しかしそこは窓もなく、コンクリートの高い壁が左右にそびえているだけだった。壁沿いを歩いていくしかない。ジメジメした床をどれだけ歩いたことだろう。ようやくドアが見つかった。鋼鉄製で扉の中央やや上部に数字で「13」と書かれている。
ドアをおそるおそる開けてみると、木製の階段が左右に三つ並んでいた。階段の段数は「13」。階段の上にはそれぞれ先が輪になったロープがだらりと垂れ下がっていた。そこは処刑場だったのだ。
「落ち着け。幻影に惑わされるな」
いくら自分にそう言い聞かせても、視界から絞首刑場は消えなかった。どうすればいいんだ? ふと思った。妖気が傷ついた心に忍びこむならば、「傷ついた心」の正反対の概念を思い浮かべれば妖気は退散するんじゃないだろうか。頭に浮かんだのは、ぼんやりした記憶の中にある空津家の幸せな晩餐のイメージだった。まだ生きていた頃の母さん、父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、湊兄ちゃんに澪姉ちゃん、そして猫のマイロ。僕はそのイメージをディテールまで思い描くことに集中した。
すると目の前が急に真っ白になった。正確に言うといきなり体が屋外に転送されたため、真夏の太陽で目が眩んだのだ。気がつくと僕は高木が生い茂る広い公園にいた。家族連れやお年寄りがベンチで一休みしている。ふと傍を見ると、花やワンパック大関が供えられている巨大な石があった。近づいて確認すると石にはこう描かれていた。
「永久平和を祈って」
石の裏に回ると説明文のようなものが書かれていたけど、読まなくても内容はわかる。この公園こそが、さっき幻影で見た絞首刑場の跡地なのだ。
それにしても霊感ゼロの僕ですらこんな目に遭うのだ。囲間さんが心配でならない。一刻も早く展望台に登らなくては。僕は公園の隅にある階段からサンシャイン60の中へと戻ると、非常階段でワンフロア下に降りた。すると案内板が見つかった。「スカイサーカス サンシャイン60展望台はこちら」。これだ。
家族連れでいっぱいのエレベーターに、ただ一人のおひとりさまとして乗り込む。最上階にたどり着くと、受付に並んで料金1200円を支払った。サインに従って進んでいくと大きな窓があった。外を覗いてみると遠くに新宿の高層ビル街が見える。新宿は池袋の「南」にあたる。封筒からお札を一枚取り出すと、人目を盗んで窓の右上の壁に腕をそっと貼り付けた。
そしらぬ顔でその場を去って、次のポイントを探す。すると足元から天井までガラス窓になったスペースがあった。ガラスぎりぎりに近づいて恐怖を楽しんでいる女子高校生グループに紛れて外を眺めると、遥か彼方に東京スカイツリーが見えた。スカイツリーは東京の「東」部に広がる下町エリアのシンボルだ。足元のガラスにお札を貼り付けた。
スマホがバイブで振動する。囲間さんからの電話だ。
「囲間さん、大丈夫ですか?」
「平気、平気。そっちはもう終わったよね?」
「ごめんなさい。幻影を見せられたせいで、ビルの中で迷子になっちゃって。でもあと二箇所貼れば終わりです」
「急いで。一応全員撃退したんだけど、二、三人がサンシャインの方角に逃げていったのが見えたから。もしかしたら丹念君を止めにくるかも」
「わかりました。急ぎます!」
順路を進んでいくと、歩行スペースの幅が急に狭くなり廊下状になった。スーパースローで歩く付き合い始めのカップルをかわして先へと進んでいく。
廊下の奥の窓には、手前に高層マンション、奥には平地がどこまでも広がる景色が見えた。埼玉は平地が多い。だからこちらが「北」だろう。窓の横の壁にお札を貼りつけた。あと一箇所だ。その時、遠くから女の人の声が聞こえた。
「あのー。お願いです。マスクをしていない方は入場をご遠慮いただけますか」
明らかに動揺している。そして悲鳴。囲間さんが取り逃したBボーイたちが押し入ってきたのだ。するとイカしたヒューマン・ビートボックスの音が徐々に大きくなってきた。
「ブッブ、パッ! ブッブブッ、パッ!」
三人のBボーイがこちらに向かって駆けてきた。さっきの女子高校生グループやカップルが突き飛ばされて吹っ飛んでいる。マズい。僕も残る力を振り絞って廊下を走った。
廊下の行き止まりには、床が階段状のステップになっていて、体をまるごと乗り出せる出窓があった。そこからは池袋駅と西武百貨店が見えた。東口から駅を背にして歩いてきたのだから駅は「西」側にあたるはずだ。そう思った瞬間、リュックをBボーイに掴まれた。
「ブッブ、パッ! ブッブブッ、パッ! ピキピキ!」
熱い吐息がうなじへと吹きかかる。慌てて手で振り払うと僕はステップを駆け上がり、お札を勢いよく窓に貼り付けた。すると、バチン!と電気のブレーカーが落ちるような音が響き渡った。振り返るとBボーイ・トリオが呆気にとられた表情で互いを見合わせている。彼らは正気にかえったみたいだ。つまりミッションは成功したのだ。
僕は囲間さんに電話した。
「いま完了しました」
「よかったー。ありがとう」
「これで妖気が拡散されなくなるんですね」
「うーん、ちがうんだよね。これはあくまで応急処置にすぎないから。新しい鎮魂の方法が見つかるまでは、お札を定期的に張り替えてしのぐしかないかも」
ということは逆に言うと、お札が貼られなくなったら鎮魂が完了したことになるのか。これから定期的に展望台にチェックしに来るとするか。
「いずれにしてもおじいちゃんはネトウヨじゃなくなるんですよね」
「ごめんなさい、これ以上は悪化しないってだけ。空気中の妖気が薄まるまでは長い時間がかかるから。それにあなたのおじいさまはすでに相当な量を吸い込んじゃっているし」
「えーっ、もう治らないんですか」
「治るとは思う。でもそのためにはおじいさまの傷ついた心を癒さないといけないのよね。妖気は単なる触媒であって、本当の問題は人の心の中にあるわけだから」
「どうすればいいんですか? このままだと合弁会社の話はポシャるし、僕もクビになっちゃう」
「今おじいさまに必要なのは、信頼できる人のケアなんだよね。だから丹念君は面倒くさいかもしれないけど、千駄ヶ谷の家になるべく通っておじいさまと交流して。愛されている自覚がないと、人の心は弱っていくものだから……きゃっ!」
「囲間さん、また誰かに襲われているんですか?」
「ちがうのよ。さっきの戦いを見ていた人たちから『一緒に写真撮ってください』とか色々頼まれちゃって。しかもどんどん押し寄せてくるの。ひょっとするとこの人たち、Bボーイよりも手強いかも」
「わかりました。すぐ助けに行きます」
そう言って電話を切ると、僕は窓から外をあらためて見た。眼下には東京の景色が広がっている。数え切れない数のマンションや一軒家が見えた。この東京でなんとか日々を暮らしている人たちがこれほどいるのだ。そのうち心の癒しが必要な人は一体何人いるのだろうと、僕は思った。
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク