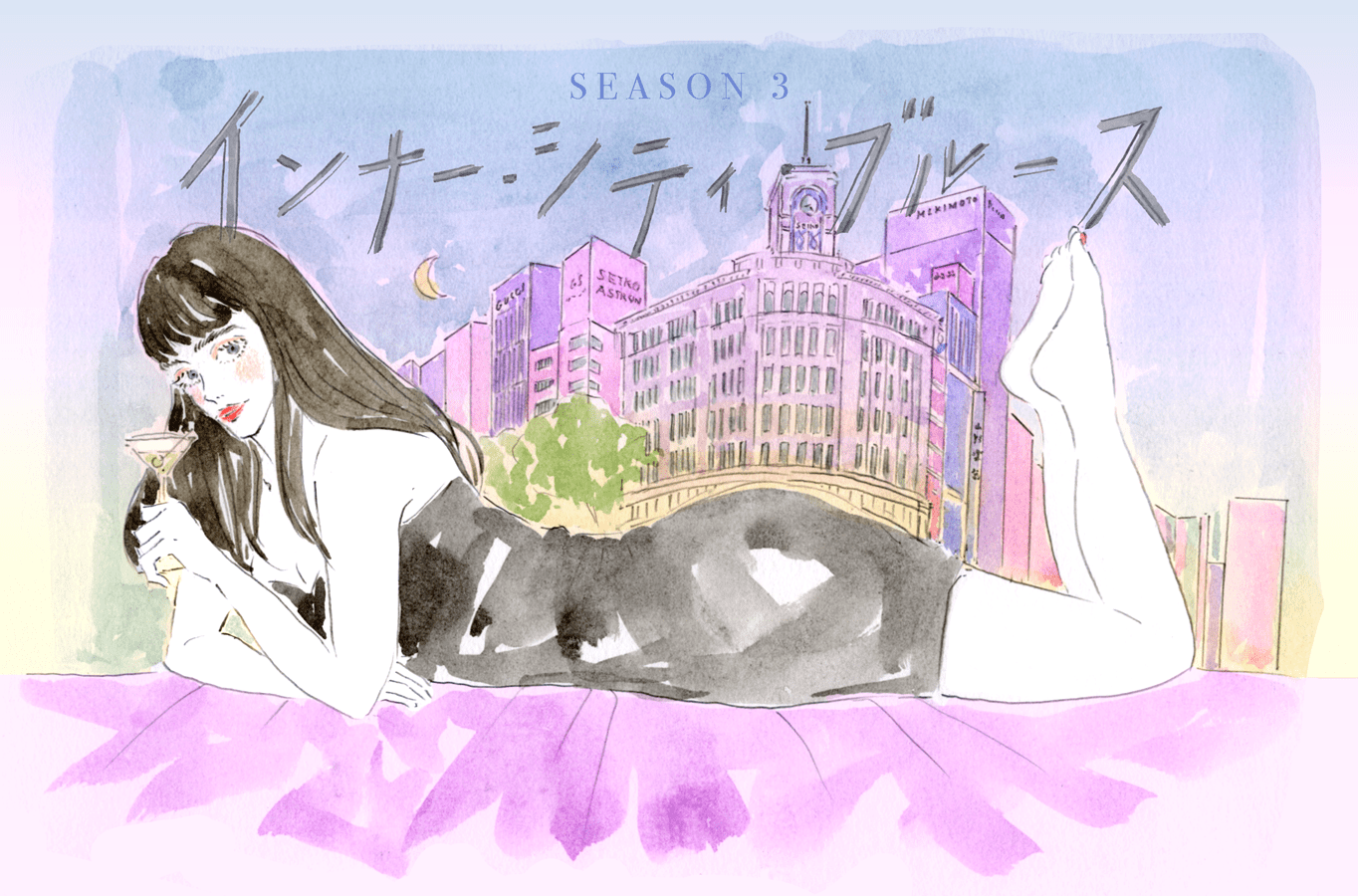毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3がスタート。新たな幕開けは、銀座を本拠地に繰り広げられる探偵物語? ディストピア感が増す東京を舞台に繰り広げられる、変種のハードボイルド小説をご堪能ください!
【あらすじ】
主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)は29歳のフリーター。銀座の外れにあるかつての行きつけのバー「アルゴンキン」でのツケが500万円以上という衝撃の事実が発覚し、借金返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収するという仕事を引き受けるはめに。最初の仕事は、ピン芸人・地雷原フミヤのツケ回収となったが、彼は現在、消息不明。しかし過去の地雷原フミヤの何本かの動画に、同じ色白の女性が映りこんでいることに気づく……。
「いいか。お客様がお食事しているときは、ガイドは決して物を食べちゃいけない。何か物を食べていると、どうしても感覚が少しそっちに持っていかれちゃうだろ? そうするとお客様からのサインを見落とす可能性があるんだ」
カウンター席に座り、ホットケーキやピザトーストの色褪せた写真が載ったビニール製のメニューブックを手に取った瞬間、旅行代理店時代に仕事のイロハを教えてくれた先輩、久世野照生(くせの・てるお)の声が俺の脳裏に蘇った。
バーの未収金回収屋に転職して一ヶ月経っていたが、俺は久世野さんの教えを守ることにした。午前10時にブランチ代わりに食べたミラノサンドA以来、何も食べていなかったから空腹感は半端なかったけど、名波玲からのサインを見逃すわけにはいかない。
「ホットコーヒーをください」
俺が今いる場所は、青梅街道から一本北に入った通りに立つ鄙びた喫茶店「森林珈琲」。アパートの部屋を出た名波玲の後をつけていくと、ここに入っていったので、俺も少し間を置いてから足を踏み入れたというわけだ。
「森林珈琲」の店内に入った途端、スーツを着てきたことを後悔した。普段の回収相手はそれなりの地位にあるサラリーマンや経営者なので、俺は舐められないようにスーツ姿で通してきた。今日も朝から企業回りをしていて、そのままここまで来てしまったわけだが、この格好だと場違いなことこの上なかった。
壁にはフィッシュマンズのドキュメンタリー映画のポスターが貼られ、棚一面に備え付けられた本棚には「ロッキンオン・ジャパン」や「QJ」のバックナンバーが並んでいる。その棚の上に横倒しで置かれた小さなスピーカーからはシュガーベイブの「今日は何だか」が流れていた。いかにも城西的なサブカル喫茶店だ。
店内には、俺と彼女のほかにはカウンターの後ろに立つマスターと、ソファーに常連客らしき男がひとり座っているだけ。マスターは日焼けした気の良さそうな中年男で、常連客はスキンヘッドでボーダーシャツを着ている。ふたりとも元バンドマンか元お笑い芸人、もしくはその両方のように思われた。
俺から少し離れた場所で同じカウンターに向かって座っている名波玲の前に、明太子スパゲッティが盛られた皿とコーヒーカップが差し出された。しかし彼女は一瞥すらしない。目的は夜食ではなく、マスターとの世間話のように思われた。
「マイコーさん」「ナナミン」と呼び合っているところからすると、名波玲もここの常連のようだ。猛烈な早口でマスターと話をしている彼女は、霞が関で見たときとは別人のようにイキイキとしていた。大きく見開かれた瞳は輝き、頬は上気してピンク色に染まっている。楽さんから見せられた地雷原フミヤのネタビデオに映り込んでいたときと同じ表情だ。
「そういうわけでね、もうわたしはボロボロなんだよー」
「でも土日は休みなんだよね? ゆっくり寝坊しなよ」
マスターの気遣う言葉に彼女が答える。
「明日は休むけど、日曜は働かないと。週明けに大臣向けのブリーフィングがあるんだけど今日、突発案件が入っちゃって資料作りどころじゃなかったんだよねー」
「そういう面倒くさい作業を押しつけといて、今頃あいつらこっそり料亭で飲んでるんだろ。こっちは酒が売れないから売り上げが壊滅状態。廃業寸前なのにさ。本当ブン殴ってやりたいよ」
マスターが大袈裟なジェスチャーで店の窮状を嘆いていると、ボーダーシャツハゲがソファーから合いの手を挟む。
「ナナミン、資料なんか作る必要なんかないって。だってあいつらさ、資料を棒読みすら出来ないんだから。ああ、ガースーが辞めてせいせいしたわ。かといって、次の首相もロクでもない奴なんだろうけどさー」
保守層の多いエリアに住む人ならビックリするかもしれないけれど、こうした反政府的言動は「森林珈琲」だけでなく、城西の飲食店によく見られるごく一般的な現象である。ちなみに東京のほかのエリアではこれほどではない。なぜ城西だけそうなのか。
前職の旅行代理店で、マニアックに東京を楽しみたい観光客向けに行っていた「ディープ中央線沿線 半日探訪ツアー」で、俺はそのルーツを16世紀まで遡って説明していた。大体こんな感じだ。
ときは戦国時代。織田信長が甲斐、今の山梨県に本拠を置く名門、武田家を滅したとき、武田家の旧家臣の多くを庇護したのは東海一の弓取りこと徳川家康だった。しかし信長が倒れて天下が豊臣秀吉に移ると、家康は本拠地を東海から関東へと移されてしまった。それでも家康は、自分を慕う旧武田家家臣を見捨てなかった。彼らに、甲斐の国と街道で結ばれた城西エリアを居住地として提供したのだ。
彼らはそのまま土地に根付いて農民になったものの、侍の魂は持ち続けた。「大恩ある徳川家に何かあったときは、命懸けで恩義に報いろ」と代々言い伝え続け、田畑を耕すかたわら寺子屋で読み書き算術を、道場で剣の腕を磨いたのである。こうした鍛錬が幕末に花開いた。江戸幕府打倒を目指す薩長の志士と斬り合った新撰組の中心メンバーは旗本ではない。城西エリアの農民出身だったのだ。
戦いが薩長連合の勝利に終わり、江戸時代が終焉を迎えた後も、城西エリアの住民たちは薩長主導の明治政府の政策に反抗し続けた。そして戦前は自由民権運動の根城に、戦後は市民運動の中心地になったのである。
もちろん現在の城西の住民の多くは他のエリアから引っ越してきた人たちで、武田家にルーツを持つ人間なんて殆ど住んでいない。しかし反権力のDNAが、このエリアにはいまだに息づいているのだ。ひょっとするとマスターもボーダーシャツハゲも自由意志というより、こうした「土地の記憶」に衝き動かされているのかもしれない。
マスターがぼそっと口にする。
「こういうときこそ、フミヤのネタを聞きたいよなー」
地雷原フミヤに話題が及んだ。俺は何気なく耳に入ったフリをして、会話に分け入った。
「あのー、フミヤって、もしかして地雷原フミヤさんのことですか?」
名波玲の顔が華やぐ。
「えーっ、知っているんですか?」
まんまと引っかかった。さて、どういう風に彼女と会話しようか。こういう時は演技と悟られないように、嘘は極力言わないに限る。
「最近、YouTubeで見て知ったんですよ。日本離れしたノリがマジヤバいなって思ってファンになって」
「えー、嬉しいなー」
「自分のことみたいに喜ぶなんて、もしかしてカノジョさんとかですか?」
「うーん」
名波玲がモジモジしていると、マスターがガヤを入れる。
「またまたナナミン、十年近い付き合いのくせに。夫婦だったらアルミ婚だよ」
やっぱり地雷原フミヤのカノジョだったんだ。
「十年前って、大学生の頃からですか?」
「ええ。こんな面白い人が世の中にいるんだって驚いちゃってー」
「地雷原さんも同じ大学なんですか?」
「あ、地雷原は芸名。本当は池間(いけま)って言うんですけど。フミヤは放送関係の専門学校に通っていて、バイトで一緒になったんです」
マスターがまた口を挟んでくる。
「ナナミンはフミヤよりずっと頭がいいんだよ。何せ大学は早稲田だからね。しかも現役で政経だよ」
名波玲のバイオは、あらかじめ楽さんから聞かされていたけど、一応驚いておこう。
「うわー。凄いですね。ひょっとして東西ブルーの影響とか?」
アラサー世代には一般常識の部類だけど、一応説明しておこう。
『地下鉄戦隊メトロンジャー』とは、2004年(平成16年)2月15日から2005年(平成17年)2月6日までテレビ朝日系列で毎週日曜7:30 – 8:00に全50話が放送された、特撮テレビドラマ、および作中で主人公たちが変身するヒーローの名称である(ウィキペディアより)。
地底人と戦うスーパー戦隊を描いた同作は、東京メトロの全面協力で製作されたため、ヒーローは丸の内レッド、東西ブルー、銀座オレンジ、千代田グリーン、半蔵門パープルといった地下鉄にちなんだ名前だった。
東西ブルーは、<ラーメンとカレーと麻雀が生きがいのワセジョ>という斬新な設定のキャラで、当時からカルト人気を博しており、彼女の影響でその後、早稲田大学を受験する女子が激増したという都市伝説でも知られている。
名波玲が笑う。周りの人間を引き込むような磁力を伴った笑顔だ。
「みんな、それ言うんですよねー。でも、当たっているかもしれません」
「ブルーを演じていた人って、今は女優を辞めてNHKでディレクターをやってるらしいですね」
「それ、わたしも聞いたことあります。最近何かの賞を貰って話題になったみたい」
もう少し名波玲本人についての話を聞き出すか。
「ナナミンさんはどちらにお勤めなんですか?」
「経済産業省です」
「エリート官僚なんだ。しかし随分堅いところに入られたんですね」
名波玲が恥ずかしがる。
「子どもの頃から、母が国家公務員になりなさいって、うるさくて。もし結婚しても産休や育休制度が充実しているからって。母は昔バリバリ働いていたんですけど、わたしを産んだら元の職場に戻れなくなっちゃったんですよね。だから世の中への復讐をわたしに託したのかも」
今度はボーダーシャツハゲがガヤを入れる、
「だからさ、ここではこんな感じだけど、ナナミンって本当は俺たちの敵なわけ」
名波玲が笑顔で怒る。
「ティップさん、マジ敵とか言わないでよねー。わたくしども公僕は、国民の皆様のために血と汗を流しながら頑張ってまーす。うまくいっているかどうかは別にして。あ、うまくいってなきゃ意味ないか、ハハハ」
自分でフリとオチ、ツッコミまで超高速で入れてみせる名波玲を見て、俺は疑いを覚えた。地雷原フミヤがネタにしていた「コントロールフリークのガールフレンド」って本当に目の前にいる彼女なのだろうか? それにしてはサバけているし、ノリが良すぎる。もしかするとフミヤには別のガールフレンドがいて、今回の失踪にはそちらの女性が糸を 引いている可能性があるのかもしれない。そろそろ話題を彼氏の消息に変えてみるか。
「あのー、フミヤさんって今どこにいるんですか?」
名波玲の表情が曇る。
「いや、フミヤさんってSNSとか全然やってないじゃないですか。お笑いを辞めちゃったのかなって思っていて」
名波玲は少しの間黙っていると、口を重たそうに開いた。
「フミヤは去年の暮れに久しぶりに里帰りしたんですけど、そこでコロナを発症しちゃって」
「ナナミンさんは大丈夫だったんですか?」
「ええ。わたしは大丈夫。でも彼はそのまま地元に足止めを食っちゃって」
足止め?
マスターが俺の方を見て言った。
「なんだー。俺は兄さんのこと、てっきり福井から来たスパイかと疑ってたんだよ。うちは常連客しか来ないしさー」
「福井?」
「フミヤの実家は福井県なんです」
名波玲が説明する。でもなぜ地雷原フミヤと同郷の人間が、この店までスパイしに来るんだろう。とにかく奴が今は実家にいることは分かった。そろそろ自分の正体を明かすか。
「実はわたし、こういうものでして」
名波玲は名刺を受け取ると読み上げた。
「バーアルゴンキン マネージャー 町尾回郎?」
俺は事情を説明した。
「銀座の交詢ビルの向かいのビルの中にあるバーなんです。一時期、フミヤさんが通われていたんですけど、少々ツケが溜まっていまして」
「いくらくらいなんですか?」
俺はスマホのメモアプリを呼び出して読み上げた。
「えーと、73万6218円です」
ボーダーシャツハゲ改めティップさんがキレた。
「どうせぼったくりガールズバーなんかだろ。そもそもお前が偶然ここに居合わせるなんておかしいよな。あっ、さてはナナミンを尾行してきたんだろ?」
ティップさんが俺に掴みかかってくる。小柄で痩せていたので甘く見ていたけど、全身が筋肉なことがわかった。シャツの襟を締め上げる力がハンパじゃない。もし元バンドマンなら、パートはドラムだったにちがいない。
「ティップさん、やめて! アルゴンキンって超一流どころだよ。うちの事務次官も打ち合わせに使っていたはず」
手が緩められたので、俺はほっとした。
ティップさんがバツの悪い表情をしながら俺に問いかけてきた。
「悪かったな。でも普通のバーだとしたら、高すぎると兄さんも思わねえか?」
「たしかに個人的にはわたしも高すぎるとは思いますけど……」
俺は正直な感想を述べたけど、500万円以上のツケが溜まっているせいで、未収金回収屋をやっているとまでは言えなかった。
名波玲は俺の目をじっと見つめると言った。
「わたしが立て替えします」
嬉しい申し出ではあるけど、それはおかしな話だ。
「でもナナミンさん、あなたとフミヤさんは結婚していないんですよね? 払う義務は正直ないですよ」
「でも責任はわたしにもあるんです。フミヤから、アルゴンキンのネタ見せ会に誘われたけど出ようかどうか迷っているって相談されたことがあるんです。そのとき彼、何だか気が進まなかったみたい。でもわたしが『アルゴンキンに出入りするテレビ関係者なんてお偉いさんに決まってるんだから絶対やった方がいいよ』って無理矢理勧めちゃったんです」
「わかりました。では請求書を週明けにお送りしますから、送付先を……」
俺が事務手続きに移ろうとした瞬間に、「森林珈琲」の出入り口扉に取り付けられたチャイムがけたたましい音で鳴り響いた。
扉の前には、さっき霞ヶ関で名波玲を脅していたジャージ男が仁王立ちになっていた。
「おい、さっきはヒデえことしてくれたな」
ジャージ男の全身から怒りのオーラが放射されている。名波玲に何をするかわからない。もしかしてこいつが福井から来たスパイ?
マスターが俺に耳打ちをする。
「俺とティップであいつを食い止めとくから、ナナミンを連れて裏口から逃げてくんないかな」
果たしてこれが正しい選択なのか自信がなかったけど、俺は名波玲の手を取ると、ティップさんが指さした方向にある勝手口から外へと逃げ出した。
やれやれ、追っかける立場だったはずなのに追われる身になっちまった。
(後編に続く)
小説『インナー・シティ・ブルース』シーズン3
イントロダクション:ファウンド・ア・ジョブ(銀座)
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク