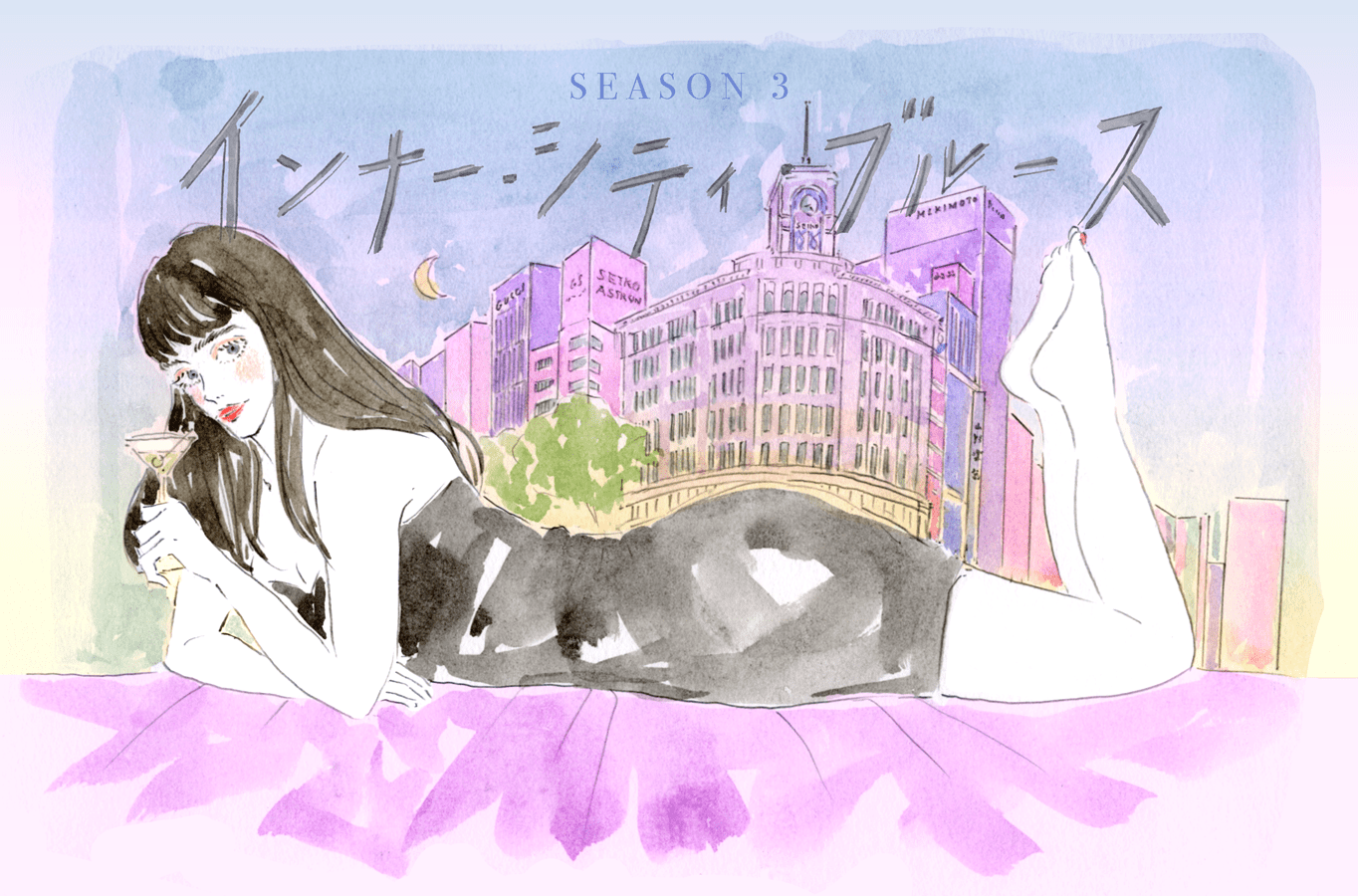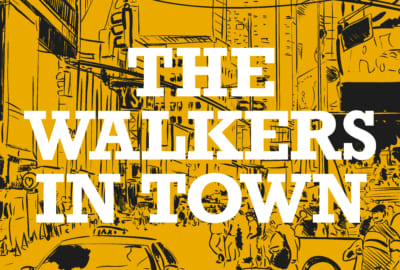毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の連作短編シリーズ「インナー・シティ・ブルース」。賛否両論の中開催された東京オリンピックが終了したタイミングに、満を持してシーズン3がスタート。新たな幕開けは、銀座を本拠地に繰り広げられる探偵物語? ディストピア感が増す東京を舞台に繰り広げられる、変種のハードボイルド小説にご期待ください!
【あらすじ】
2021年8月某日の夕刻。東京の新型コロナ新規感染者が4000人を超えたニュースが流れる中、町尾回郎(まちお・まわろう)は気温30度超えの銀座の街中を歩いていた。政府や東京都が在宅を呼びかける中、銀座の街は人でごった返している。回郎は飲みながら愚痴をこぼせるバーを求めてブラブラしているうちにある店を思い出す。やっとそこへたどり着くと、カウンターにはマスクをしていない美しい女が立っていて……
「だから深入りはやめとけって言ったのに」
奴はそう言うと、ショルダーバッグの中から慎重に何かを取り出して、こちらへと向けた。夜の闇ではっきりと見えなかったけれど、おそらく銃だろう。
これが小説の世界だったら、奴はコートの内ポケットからさっと取り出したはず。でもピストルは種類によって1キロくらいの重さがある。ペットボトル2本の重さの物体を片方のポケットに入れて動き回るなんて非能率この上ない。だから現実世界では、ピストルをショルダーバッグで持ち運ぶのだ。
やばい。こんな時に余計なことを考えてしまうのが、俺の悪い癖だ。
確かに俺は深入りしすぎた。調子に乗って何でもやれるって思いあがっていた。そもそもあの時、あの店に行かなければ、こんな事にはならなかったのに。
賛否両論の中、東京オリンピックが開催されていた2021年8月へと話は遡る。俺はその日、銀座の街中を晴海通り沿いに有楽町方面に向かってトボトボと歩いていた。時間は午後6時をすぎていたが、気温はまだ30度を下回っていなかった。汗で湿ったせいでスーツが重く感じる。あとで知ったのだが、この日初めて東京の新型コロナ新規感染者は4000人を超えたらしい。政府や東京都は「オリンピックを家で楽しみましょう」と呼びかけていたけど、みんな深刻な状況に麻痺していたのか、銀座の街はごった返していた。
「バカばかりだな」
そう心の中で呟いた俺も、一直線に部屋には帰らずに近場で酒を飲みたくなった。コンビニでビールとおつまみを買って、ソニービル跡地の公園で飲むのが最もコスパが良いはずだ。でもその時の俺は誰かに愚痴をこぼしたかった。
「『アルゴンキン』ならやっているかも」
俺はアルマーニのビルの手前で左折すると、西五番通りを新橋方面へと歩き出した。もし機会があったら晴海通りから御門通りを結ぶ400メートル四方くらいのこのエリアをブラついてほしい。あたり一帯を埋め尽くすように雑居ビルがぎっしり建並んでいて、そのどれもが通りから見えるように沢山の小さな看板を出しているのを見て圧倒されるはずだから。
看板に書かれた文字を読み上げてみよう。「風」「雅」「蛍」といった漢字一文字。「ルルド」「Paradiso」といったエキゾチックな響きを持つ言葉。そして「春香」や「純子」といった女性名。種類は様々だが、ようするに全部がカウンターバーの看板なのだ。
「アルゴンキン」もそうしたバーのひとつだった。店はバーニーズ・ニューヨークが入っている交詢ビルの向かいに建つ、今にも崩れ落ちそうな古いビルの中にあった。俺はコンクリートのたたきが部分的に陥没しているエントランスから中へと入ると、エレベーターの扉の横にあるパネルで「UP」ボタンを押した。
ロープを軋ませながら降りてきたエレベーターに乗ると、「7」のボタンがを押した。エレベーターのカゴの中は雨とニコチンの臭いが染み付いている。目的のフロアーに到着して扉がゆっくり開くと、俺の前には見慣れた景色が広がっていた。白とベージュのモザイクタイルを扇形状に敷き詰めた床に、ウッディ調の合成パネルを貼った壁、そして天井からぶら下がった大して価値があるとは思えないシャンデリア。昭和の人間が考えるゴージャスさの結晶体のようだ。そしてその結晶体は、過ぎゆく歳月に負けて随分と痛んでいた。
7階のフロアーのエレベータに近いところには、「アルゴンキン」とは別のバーがテナントとして入っている。しかしそのバー「蘭」のドアには流麗な筆ペンで次のように書かれた紙が貼り付けられていた。
「緊急事態宣言により休業要請が発令致しました。7月12日〜8月22日まで休業させていただきます。ご了承の程、何とぞお願い致します。皆様とお逢いできますこと心待ちしております。」
この分だと「アルゴンキン」もやっていないかもな。そう思いながらも俺は薄暗い廊下の行き止まりまで進むと、「アルゴンキン」のドアレバーを手前に引いた。ドアは抵抗無しにゆっくりと開いた。
最後にここに来たのは新型コロナが流行り始める直前だから、1年半ほど前だろうか。でも「アルゴンキン」の店内はひとつの点を除くと全く変わっていなかった。ヘリンボーン柄のフローリングは、こぼれたウィスキーが付着したせいか黒く輝き、正面には流木を二つに切ってそのまま無造作に置いたような長いカウンターが広がっている。壁一面に備え付けられたガラス棚には年代物のスコッチやワインが並び、その1/4ほどには常連客のネームタグがくくりつけられていた。
唯一の違いは、カウンターに立っていた美しい女だった。「アルゴンキン」の女主人、通称ドロシーママも美女だったが、相当な高齢である。でもこの女はまだ若い。たぶん自分と同年代だろう。黒いドレスを痩せた身体に纏ったその女は、左手にマティーニグラスを持ったまま、右手のスマホで暇をつぶしているようだった。どこかで会った気もするのだが。
女が視線に気づいたのか、こちらを振り向いた。真紅の口紅をさした唇が見えたので少し動揺する。マスクをしていない女を肉眼で見るのは久しぶりだった。
「あれっ、ママは今日休みなんですか?」
俺がわざと軽い調子でそう尋ねると、女は低い声でこう言った。
「店の看板をよく見て」
俺は扉の外に一旦出て看板を確認した。看板自体は昔のままだ。でもよく見ると、「アルゴンキン」という筆記体のロゴの下にテプラが貼られている。テプラにはこう書かれていた。「囲間インテリアデザイン事務所」
インテリア事務所? パソコンも製図台も置かれていないのに? でもこちらが間違えたのは確かだ。店内に再び入ると、とりあえず謝った。
「すみません。知らない間にテナントが変わってたんですね」
「ううん、完全には変わってない。ちょっと前からここをまた借りしているだけだから。でもお酒を飲みたくて来たんでしょう? あるものでいいなら飲ましてあげる」
でもマスクをしていない人間のそばでは飲みたくない。俺が黙ってその場に立ちつくしていると、こちらの考えを察したのか女は天井を指差してこう言った。
「コロナ対策は完璧だから。ほら」
見上げると、天井には円形のスピーカーが仕込んであって、彼女の声がそこから流れている。もう一回、女の姿を見たら、バーカウンターの上から天井まで、俺と彼女を隔てるようにガラスの壁が設けられていたことがわかった。その途端に、女が水槽の中でゆらゆら泳ぐ黒い金魚のように見えてきた。
「口紅しないとなんだかテンションがあがらなくてねー。仕事に支障が出ちゃうから、こういうものを作ってもらったんだよね」
どう見ても、酒を飲みながらSNSをチェックしているようにしか見えないのだが。
俺がビールを頼むと、女は冷蔵庫から「これしかない」と言いながらヒューガルデン・ホワイトの缶を取り出して、ガラスの壁のそばに置いた。すると、壁の一部が自動で小さく開き、ビールがベルトコンベアのようなものでこちら側に運ばれてきた。
「いただきます」
俺は缶のプルトップを開けると一気に半分くらい飲み干した。
「いつからここを借りているんですか?」
「半年前くらいかな。コロナが広まってからもドロシーママは頑張っていたんだけど病気になっちゃって。店を畳むって言い出したんだけど、こういう店ってさ、クローズするのにもお金がかかるんだよね」
知っている。厨房機器や家具を運び出して部屋を原状回復しようとすると新しく開店するのと同じくらいお金がかかるのだ。
「しかも病気を治すのにいくらかかるかわからないでしょう? だから私がしばらくの間は、また借りしてあげるって言ったわけ」
「もしかしたらママの親戚とか?」
「赤の他人だよ。娘のように可愛がってはもらっているけどね。ここにも通っていた」
見覚えがあるのはそのせいだったのか。
「わたし、囲間楽(かこいま・らく)。楽って呼んでいいから。あなたは?」
「町尾回郎(まちお・まわろう)。回転の回に太郎の郎って書きます」
「歳は?」
「もうすぐ三十です」
「じゃあわたしの方がちょっと年上だ。マワローって呼ばしてもらうから」
そう言うと、楽さんは初めて笑みを浮かべた。薄い唇の隙間から白い歯が見える。
「どうやって『アルゴンキン』を知ったの?」
「新人時代に会社の先輩が連れてきてくれたんですよ」
「ふーん、その人の名前は?」
楽さんが詰問調になる。
「久世野照生(くせの・てるお)っていいます」
「今も付き合いある?」
「いや、あの人、そのあとすぐに会社を辞めちゃったから。SNSもやってないみたいだし。ここに通っていればそのうち会えるかなって思っていたんだけど、姿を見せないんですよね」
「でもマワローはここに通い続けていたんだね。理由はわかってる。タダ酒が飲めるからでしょ」
その通り。それこそが「アルゴンキン」に通っていた理由だった。でも最初の頃は帰り際に勘定を頼んではいたのだ。でもドロシーママはいつも決まって「今日はいいから」と言うので、何も言わずに帰るようになったのだ。
「どうしてタダになるなんて考えたの?」
「ママに気にいられたからフリーパスをもらったのかなーとか思ったんですよ。でもさすがに会社の仲間は連れて来なかったですよ。いつもひとりで来てました」
楽さんはマティーニを飲みほすと、自分でおかわりを作り出した。
「久世野って人も知らなかったのか、わざと説明しなかったのかはわからない。でもここのお酒はタダじゃない。勘定は出世払いなの。『アルゴンキン』はずっと赤字で、常連客で出世している人たちが多めに払って経営を支えていたんだよね」
確かにこんなオンボロビルのバーなのに金回りが良さそうな客がいたっけ。楽さんは話を続ける。
「それだけの価値が『アルゴンキン』にはあった。日経新聞は読んでる? ほら時々いきなり大企業同士の合併や異業種間のコラボレーションが発表されたりするでしょう? あれって結構な確率でここのお客同士が意気投合したのが発端になっているんだよね」
何も知らずに俺はトップシークレットなサロンで飲んでいたのか。
「全然知りませんでした。じゃあ俺も将来どうなるか分かりませんけど、出世したらツケにプラスアルファして支払いますよ」
楽さんがマティーニのおかわりを注いだグラスを手に持って、俺を睨んだ。
「その制度はもう終わりにしたいんだよね。ドロシーママは重病なんだから。そういうわけでこれまでのツケをぜんぶ払って」
そんなこといきなり言われても困る。
「ちょっと待ってくださいよ、楽さん。コロナが収まって、ママが復帰すれば店は元通りになるかもしれないじゃないですか」
「元通りになんかならないよ。マワローだって気がついていたでしょう? 『アルゴンキン』の常連客でアラサーの人なんてわたしとあなたぐらい。それ以外だと一番若い客でも二回りは年上だって」
たしかにアラフィフの人でも若い方だった。
「ここだけじゃない。銀座のバー全体がそう。銀座のバーの全盛期は昭和30年代から40年代にかけて。お客として支えていたのは戦前生まれの人たちだった。そのあと通っていた団塊世代も今ではほぼ全員が引退してしまった。バブル入社組の中に団塊世代の遊び方に憧れていた連中も少しいるけど、彼らだってもう五十代半ばなんだよ。つまりあと十年くらいで銀座のバー文化は消滅するの。新型コロナのせいでそれは早まったかもね」
「えーっ、通ってみたら結構楽しい感じなのに。SNSでイイ感じで宣伝すれば若い奴らも来るようになるかもしれないですよ」
「マワローみたいな人がもっといればいいんだけどね。わたしには信じられないけどさ、お酒が嫌いな人が年々増えてきているし、酒が好きな連中も通っている街は六本木や恵比寿でしょう? だから銀座のナイトライフそのものをどう店じまいするか考えるフェーズに入ってるってわけ」
楽さんの言っていることは正論だ。でもマズイ。
「払えって言われても、そもそも正確なツケの金額なんてわかるんですか? だってママはいつも客とお喋りばかりしていたし、バーテンさんもメモしている様子なんてなかった」
楽さんはたしなめる口調で言った。
「写真記憶って知ってる? 物事を映像として覚えるから絶対忘れないって人が一定数いるんだよね。ドロシーママはその写真記憶の持ち主だった。もちろん客のオーダーはぜんぶ覚えていた。この業界の人って、写真記憶を持っている人がすごく多いんだよね。フツーの人からすると『そんな能力があるんならサラリーマンになれば出世できるのに』って思うかもしれないけど、能力の代償としてカタギの仕事をどうしてもやれないって人が実際は多いんだよね」
そういえばママは客全員の顔と名前はもちろん、誕生日やペットの名前、この前に店に来たときに話したことまでぜんぶ覚えていた。
「ドロシーママが若い頃にニューラテンクオーターのホステスだったって知ってる?」
「聞いたことがあります。赤坂にあったキャバレーですよね。たしかデヴィ夫人もそこで働いていたって」
「それはコパカバーナ。ドロシーママは間違われると『一緒にしないで』ってよく怒っていたよ。とにかく、彼女はそこで人脈を築いて、この店をオープンした。ママは人のオーラを見る力があって、これぞと見込んだ客は出世払いにしていたみたい。あなたもそのひとりみたいだね」
オーラ?
「わたし、そういう力がある人に興味があってさ。最初は噂を聞いてドロシーママに会いに行ったんだよね。そうしたら逆に気に入られて常連になっちゃったんだけど」
そう言いながら楽さんはカウンターの下から、分厚い大学ノートを取り出すとページをパラパラとめくり出した。
「ここにあなたへのツケの合計額が書いてあるはず。このノートって、人に読まれないようにわざと暗号みたいな字で描いていて、解読するのが大変だったんだよねー。あ、あった。町尾回郎。うわー、結構飲んでるんだね。532万4649円だって」
全身の毛が逆立った。
「ごひゃくさんじゅうにまんえん? それって桁が違わないですか?」
「そんなことないよ。メニュー表を見たら、さっきマワローに出したビールも4800円だったし」
「それって、まるでボッタクリ・バーじゃないですか?」
「ちょっとそれはママに失礼なんじゃないの? ビジネスチャンス込みのサロンなんだから、激安なくらいよ」
これは真実を語って泣き落とすしかない。
「532万なんて払えませんよ、無理。だって貯金もないし俺、先週会社をクビになったばっかりなんですから」
楽さんは表情も変えずに訊ねてくる。
「へー。どういう会社?」
「旅行代理店です。ツアーの企画が勝負の小さい会社だったから、このコロナ騒動で経営がキツくなっちゃって」
「でもマワロー、今日暑かったのにスーツなんか着てるよね」
「ああ、これっすか。一年くらい前に仕事で付き合いがあった仕出し弁当の会社の社長から熱心にヘッドハンティングされたことがあったんですよ。その時はお断りしたんだけど、雇ってもらえないかなと思って今日、東銀座のオフィスに会いに行ってみたんですよ」
「結果はダメだったんだね」
「鋭いですね」
「このご時世だと仕出し業者も大変だものね」
「『まあ、お盆はゆっくりしなよ』とかのらりくらり言われて帰らされちゃいました」
「それはご愁傷さま」
楽さんはそう言うと、冷蔵庫からヒューガルデン・ホワイトをもう一本取り出して「これはわたしの奢り」と言いながらこちらに差し出した。
俺は黙ってプルを開けてビールを喉に流し込んだ。やけくそ気味の俺をよそに、楽さんは自分の計画を話し始めた。
「わたし、ここを借りはじめた時には、ドロシーママの代わりにツケの回収をやってあげようかなと思っていたんだよね。でもコロナのせいで自分の仕事が忙しくなって、それどころじゃなくなっちゃって」
どう見てもヒマそうにしか見えないのだが。
「だからマワロー、ツケの回収を代わりにやってくれない?」
「あのー。借金してる身で申し訳ないんですけど、そんな時間ないですよ。一刻も早く次の仕事を探さないと部屋代も払えなくなるし」
楽さんはマティーニを飲み干すと提案してきた。
「マワローの報酬として回収額の15%を払うよ。そこからあなたの生活費を払って、余ったお金で『アルゴンキン』への借金を返していってくれればいいから」
もし俺と同じような奴からツケを全額回収できれば、報酬は80万円。悪くない……ていうか、美味しい仕事だ。
「えっ、いいんですか。楽さん、こちらこそよろしくお願いします」
その時気づいていれば良かったのだ。債権回収の弁護士費用の相場は未回収額の15%程度。つまりそれだけの金を支払う気があれば、プロの弁護士を雇えたってことだ。それなのに楽さんは敢えてズブの素人を雇った。それは回収先が弁護士では歯が立たないワケアリの連中だって知っていたからだ。それなのにオファーに飛びついてしまうとは、何てバカだったんだろう。
とにかく、こうして俺の新しい仕事が始まった。
小説『インナー・シティ・ブルース』シーズン3
イントロダクション:ファウンド・ア・ジョブ(銀座)
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク