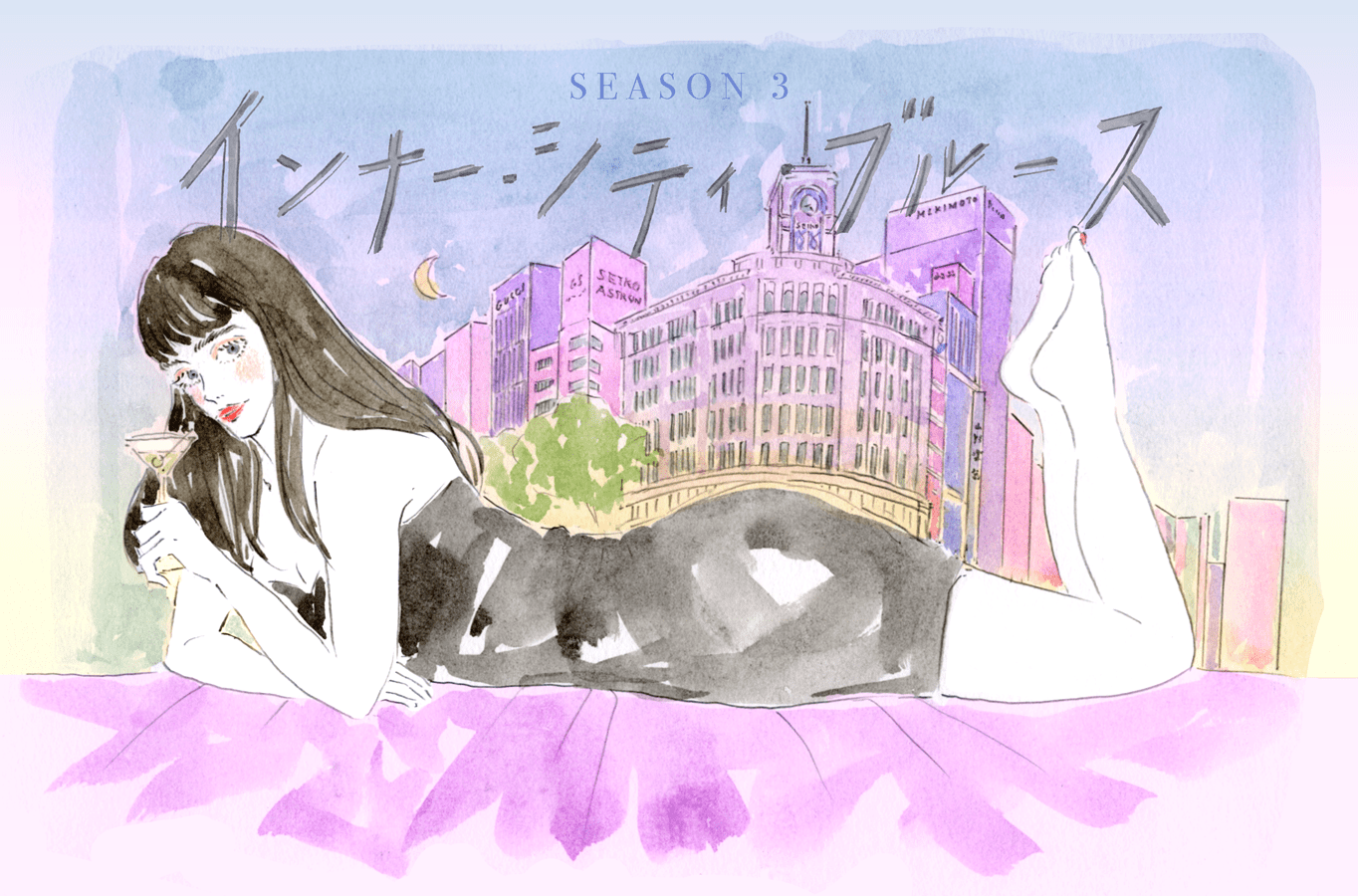毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3がスタート。新たな幕開けは、銀座を本拠地に繰り広げられる探偵物語? ディストピア感が増す東京を舞台に繰り広げられる、変種のハードボイルド小説をご堪能ください!
【あらすじ】主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)は29歳のフリーター。銀座の外れにあるバー「アルゴンキン」での過去のツケ返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収する仕事を引き受けている。まずは芸人・地雷原フミヤのツケ回収となったが彼は消息不明。そこでフミヤに最も近い謎の女性、名波玲へ近づくことに成功したものの、彼女と一緒に凶暴なジャージ男に追われるはめに……。
新中野駅で乗ったばかりの丸の内線を、名波玲は二駅だけで降りた。俺も慌ててついていく。新高円寺駅の改札をくぐって階段を登ると、目の前を左右に走る青梅街道の向こう側に「高円寺阿波おどり応援! 商店街セール!」と書かれたのぼりが下がった通りが見えた。高円寺ルック商店街だ。
この一帯にはちょっとした思い出がある。旅行代理店時代、西新宿や渋谷のホテルに宿泊している外国人客のオプション・ツアーをよく任されていた。彼らから「トーキョーのダウンタウンを見たい」と頼まれても、俺はあえて浅草には連れていかなかった。副都心エリアから浅草に行くには東京の中心部を通過する必要があるので、タクシーでも電車でも時間がかかる。しかも彼らが指す「ダウンタウン」とは、「下町」でなく「庶民が暮らす街」のことだ。浅草はそうした期待に応えるにはあまりに観光名所すぎている。
そんなオーダーを受けたとき、俺は車を浅草とは反対方面の西側へと走らせ、この一帯で降ろしたものだ。そして高円寺ルック商店街、パル商店街、純情商店街、そして庚申(こうしん)通り商店街と2キロにわたって延々と続く通りを歩かせるのだ。彼らは喫茶店や床屋、豆腐屋に金物屋、そしてもちろん古着屋といった個人経営のショップを見て、人々の暮らしに間近に触れて大喜びしてくれた。
新型コロナのパンデミックさえ無ければ、今も旅行代理店の社員として外国人たちにこの街を案内していただろう。でも今夜の俺は謎を抱えた若い女とともに、凶暴なジャージ男に追われている。
緊急事態宣言下の高円寺ルック商店街の人通りはまばらで、この時間に営業している店は殆ど見当たらなかった。
「あのジャージ男は何者なんです?」
俺の質問に、名波玲は歩きながら答えた。
「あの人はフミヤの弟さんなんです」
「なんで付きまとわれているんですか?」
彼女は黙ったまま商店街を2〜3分ほど歩くと、木造アパートの前で立ち止まった。青い瓦屋根の庇(ひさし)からはランプが吊るされていて、「ガスライト」と彫られた銅製の看板を照らしている。その看板がかかった木製扉を押して彼女と俺は店内へと入った。店はカウンター席のほかに丸テーブルが3つほど置かれていたが、客は誰もいない。
「あら、ナナミンじゃない」
近寄ってきたオーナーらしき小柄な女性は、名波玲の深刻そうな顔を見ると、何かを察したのか「もう遅いから閉店にしちゃった方がいいわね」とひとり事を言いながら、扉の鍵をかけ、オーダーを取った。アルコールを出す店を取り締まる立場にある官僚でありながら、名波玲がジンフィズを頼んだので、俺も中ジョッキをオーダーした。本当は何か食べたかったのだけど辛抱だ。
彼女と俺はカウンターに並んで座った。
グラスに口をつけると、名波玲は落ち着いたのか、彼氏の弟に付きまとわれている理由を話し始めた。
「去年の終わりに、里帰りしていたフミヤからコロナにかかったって電話があったのを最後に連絡がなくなっちゃって。でも元々マメな人じゃないし、わたしも自分が感染していないか検査したり、忙しく仕事していたから、そんなに気にしていなかったんです。でも休み明けにいきなりLINEが送られてきて」
「どんな内容だったんです?」
「『芸人を辞めることにしたから、東京を引き揚げる。荷物はナオユキが取りに来る』って」
「ナオユキって、フミヤさんの弟の名前ですか」
「笑っちゃうでしょ。名付け親の人がチェッカーズのファンだったみたい」
「芸人引退は、ナナミンさんにとっては突然だった?」
「はい。だってフミヤ、ものすごく頑張っていたんですよ? しかもそのLINEを最後に携帯が通じなくなって、SNSもぜんぶ止めちゃって。家族から脅されて無理矢理芸人を辞めさせられたとしか思えないんですよね」
池間フミヤは実家で軟禁されているわけか。LINEを送ったのもフミヤではなく、ナオユキなのかもしれない。
「それで福井からナオユキさんがやって来た。でもあなたは断った」
「それなのに『アニキのものだから俺が自由に荷物を持って帰る』って聞かなくて。あんまりしつこいんで管理会社に頼んで、鍵を取り替えてもらったんです。だからあの人が持っている合鍵では中に入れなくなっています」
ナオユキが「鍵を貸せ」って怒っていたのはそのせいなのか。
「ナナミンさん、見かけによらず過激ですね」
「でもわたし、フミヤ本人が直接来るのなら荷物を渡すって話したんですよ。でもナオユキさん、全然聞いてくれなくて」
俺はビールをからっぽの胃に流し込みながら、「ガスライト」の店内を見渡した。照明が落とされているので今まで気がつかなかったけど、丸テーブルが置かれたエリアの奥に一段上がった小さなステージが見えた。おそらくコロナ以前は弾き語りのステージが行われていたのだろう……いや、弾き語りだけじゃないはずだ。だって見覚えがある景色だから。
俺は名波玲に尋ねた。
「もしかしてこの店、フミヤさんとの思い出の場所ですか?」
「なんでわかったんですか? よくあのステージで、フミヤがネタをやらしてもらっていたんです」
やっぱり。楽さんが俺に見せてくれた動画は、「ガスライト」で録られたものだったんだ。
「芸人デビューの場所もここなんですよ。もう十年前になるかな、JRから丸の内線に乗り換えるために、フミヤとこの商店街通りを歩いていたんです。高円寺駅と新高円寺駅って離れているし、ふたりとも酔っ払っていたから、結構時間がかかっちゃったんですけど、その間フミヤのおしゃべりにずーっと笑いっぱなしで。こんな面白い人、マジ初めてってくらい笑ったんですよね」
俺はまだ十代だった頃の名波玲の笑顔を想像した。
「そうしたら急に土砂降りになっちゃって。それでしばらく雨宿りしようとこのお店に入ったら、あそこにステージがあるじゃないですか。だから「ステージあがっちゃいなよー」ってフミヤをけしかけたんです。それが地雷原フミヤのファースト・ステージ」
「ウケたんですか」
名波玲は笑った。
「ぜんぜんっ。でも逆に頑張る気になったみたい」
オーナーが口を挟んできた。
「彼、どんどん巧くなっていったのよー。ネタも社会派になっていったし。わたし、ああいうお笑いは今こそ必要だと思うんだけど」
森林珈琲のマスターと同じことを言っている。テレビはともかく、城西エリアのクラブでなら需要はありそうだ。それなのに引退とは、やっぱり家族から無理矢理辞めさせられたんだろうか。
俺が引退の真相に想いを巡らしていると、店内に低く鈍い音が響きわたった。その音はいつまでも止むことなく続いた。店の扉が力強く叩かれているのだ。なぜ、フミヤの弟はこんな場所まで知っているんだろうか? 俺は名波玲の横顔を見たけど、彼女は何かを悟った表情をしていた。
オーナーが騒音に耐えられなくなって扉を開けた。すると案の定、フミヤの弟、池間ナオユキが憮然とした表情で店内に足を踏み入れてきた。しかし彼に続いて入ってきたのは予想外の人物だった。そう、地雷原フミヤ本人だったのだ。
彼は、動画で見た自信満々の様子からかけ離れた弱々しい声色で、名波玲に話しかけてきた。
「玲、いい加減、逃げ回っていないで鍵を貸してくれよ」
「逃げ回っていたのは、フミヤの方でしょう」
フミヤが言い終わるか終わらないかの絶妙なタイミングで、名波玲がツッコミを入れる。俺はようやく気がついた。彼女は、芸人引退が地雷原フミヤ本人の意志であることを察していたが、どこまで本気なのか確認したかった。だから鍵を交換するという荒技を使ってまで、ふたりしか知らない思い出の場所に呼び寄せたのだ。
「なんで直接会おうとしないのよ。わたし無理やり芸人を辞めさせられたんじゃないかって疑ってたよ」
フミヤは十年以上一緒だったガールフレンドの目も見ずに、自分の足元を見ながら呟くように答えた。
「れ、玲は天才的に口がうまいじゃないか。俺、これまでも何度も芸人を辞めようとしたのに、その都度お前に説得されて、ズルズルここまできちゃった。気づいたらアラサーだぜ。でもコロナで寝込んでいるときに、わかったんだよ」
「何をよ?」
「俺、部屋に閉じこもっている間、コロナから治ったら何をしようって色々考えたんだ。でも芸人としてウケまくっている姿を一回も思い浮かべなかった。一回もだぜ! それでわかったんだよ、本当はもう芸人なんかやりたくないんだって」
「でもフミヤ、才能すごくあるし」
地雷原フミヤは自嘲めいた笑みを浮かべた。
「その根拠は、いつも話していたアレだろ。高円寺から新高円寺まで歩く間、俺がずっと玲を笑わせていたって話」
「そうだよ。こんな面白い人に会ったことないって思ったもん」
「お前は勘違いしていたんだよ。あの晩、俺が言った「イライラする!」とか「整いました!」ってギャグ。あれ全部あの頃流行っていたお笑いのパクリだから。玲は中高ずっと勉強漬けだったから、お笑いに免疫がなかっただけなんだよ」
前橋女子から早稲田の政経学部に現役合格。たしかに民放のお笑い番組なんか観るヒマがなくてもおかしくはない。
「で、でもフミヤ。一生懸命ネタを作っていたじゃない。それでアルゴンキンに出入りするレベルまで行ったし」
それまでオドオドしていたフミヤの声のトーンが硬い調子に変わった。
「社会派ネタを作ったのは、玲だろ!」
えっ、どういうことだ? 名波玲の顔を見たら血の気が引いている。
「た、たしかにアイデアは出したけど……」
「ネタだけじゃない。言い回しを含めてぜんぶ玲が作ったんじゃないか。思い出してみろよ。仕事で溜まったストレスを発散させるためだと思うけど、玲は帰ってきてから寝るまで、俺にむかってずっとペラペラ喋ってただろ。その場の思いつきなのに、フリからオチまで全部つけてさ。それが考えられないくらい面白かったから、あとでそれを思い出しながらスマホに打ち込んだだけ」
名波玲は消え入りそうな声で反論した。
「でも社会派ネタ以外もあったよね……」
「『なんでも仕切りたがるガールフレンド』だろ。あれは玲が話していたお母さんの悪口が面白かったから、母親をガールフレンドに設定変更しただけ」
俺の脳内で、森林珈琲で名波玲が母について語った言葉が脳内再生された。
「子どもの頃から、母が国家公務員になりなさいって、うるさくて」
地雷原フミヤの動画を見たときにボンヤリ感じた、穏やかなルックスとネタが乖離している違和感の正体がようやく分かった。圧倒的な知性と知識を持つ、尖りまくったスタンダップ・コメディアン、地雷原フミヤの正体は池間フミヤではなかった。名波玲だったのだ。
黙り込む彼女に、フミヤが穏やかなトーンに戻って話しかける。
「俺、思ったんだよ、お笑い番組なんて全然観たことないのにあれだけのネタを作れる玲は天才だって。俺はさ、テレビに出て有名になりたかっただけ。でもそんな気持ちもコロナのせいでなくなった」
名波玲はもう反論しなかった。そしてトートバッグの中を探って鍵を取り出すと、フミヤに手渡した。
「朝までに荷物を運び出して。鍵はポストに入れといてくれればいいから」
「ありがとう。玲もあんまり無理すんなよ。落ち着いたら連絡するから」
関係が続きそうな口ぶりだけど、ふたりは事実上これでおしまいなんだろう。地雷原もとい池間フミヤは弟に目配せをすると、外に出ていった。俺はしばらく呆然としていたけど、それではマズいことに気がついた。慌てて池間兄弟を走って追いかけると、「「バーアルゴンキン マネージャー 町尾回郎」と書かれた名刺を手渡した。
「実は店のツケが溜まってまして」
「いくらっすか?」
池間フミヤが訊ねてきたので、俺は正直に金額を提示した。
「73万6218円です」
弟は「ああん?」と言ってキレかけたけど、フミヤは制止した。
「銀座の一流バーだから、そのくらいするって」
そしてポケットを探ると、俺に名刺を手渡してきた。
「……わかりました。何とかします。こちらに請求書を送っていただけますか」
名刺には「株式会社池間眼鏡 取締役 池間フミヤ」と書いてあった。
「月末までに送っていただければ、翌月末には振り込みますから」
「ありがとうございます」
一括払いは久しぶりだ。再来月末には手数料15%の約11万円が振り込まれるはずだ。これで俺もクリスマスを祝える。池間兄弟の姿が見えなくなるまで待ってから、俺は楽さんに電話をかけた。
「もしもし楽さん? なんと地雷原フミヤの未収金回収の目処がたちました」
「すごいわねー。どうやったの? でも……」
「でも?」
「マワロー、全然嬉しくなさそう」
囲間楽はぜんぶお見通しのようだった。
電話を切って、「ガスライト」に戻ろうとしたら、名波玲が外に出てくるのが見えた。思いのほか落ち込んでいなさそう……ていうか、なぜか笑顔だ。彼女は俺に向かって走ってくるとこう宣言した。
「いま『ガスライト』でわたしの芸人デビューの日を決めてきちゃったんです」
「芸人デビュー?」
「フミヤがやらないんなら、自分でやっちゃおうかなと思って。10月1日金曜日の夜なんで、町尾さんもよかったら見にきてくださいね!」
「でも緊急事態宣言が延期されるかも……」
そう言いかけながら気がついた。彼女はエリート官僚だ。間違いなく解除されるとの情報を掴んでいるにちがいない。
「ナナミンさん、芸名はどうするんです?」
「地雷原玲(じらいげん・れい)にしようかなー」
「それなら地雷原ゼロの方がいいんじゃないですか?」
「あ、それ頂きます!」
彼女の言葉に応えるようなタイミングで、俺のお腹が鳴ってしまった。
「もしかしてお腹減ってます? わたしも朝まで外で暇を潰さないといけないんで、丸の内線で荻窪まで行って、ラーメンでも食べません? 朝までやっている店を知ってるんです」
そう言って微笑む彼女の頭上から、雨が降りはじめた。
『インナー・シティ・ブルース』発売記念
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク