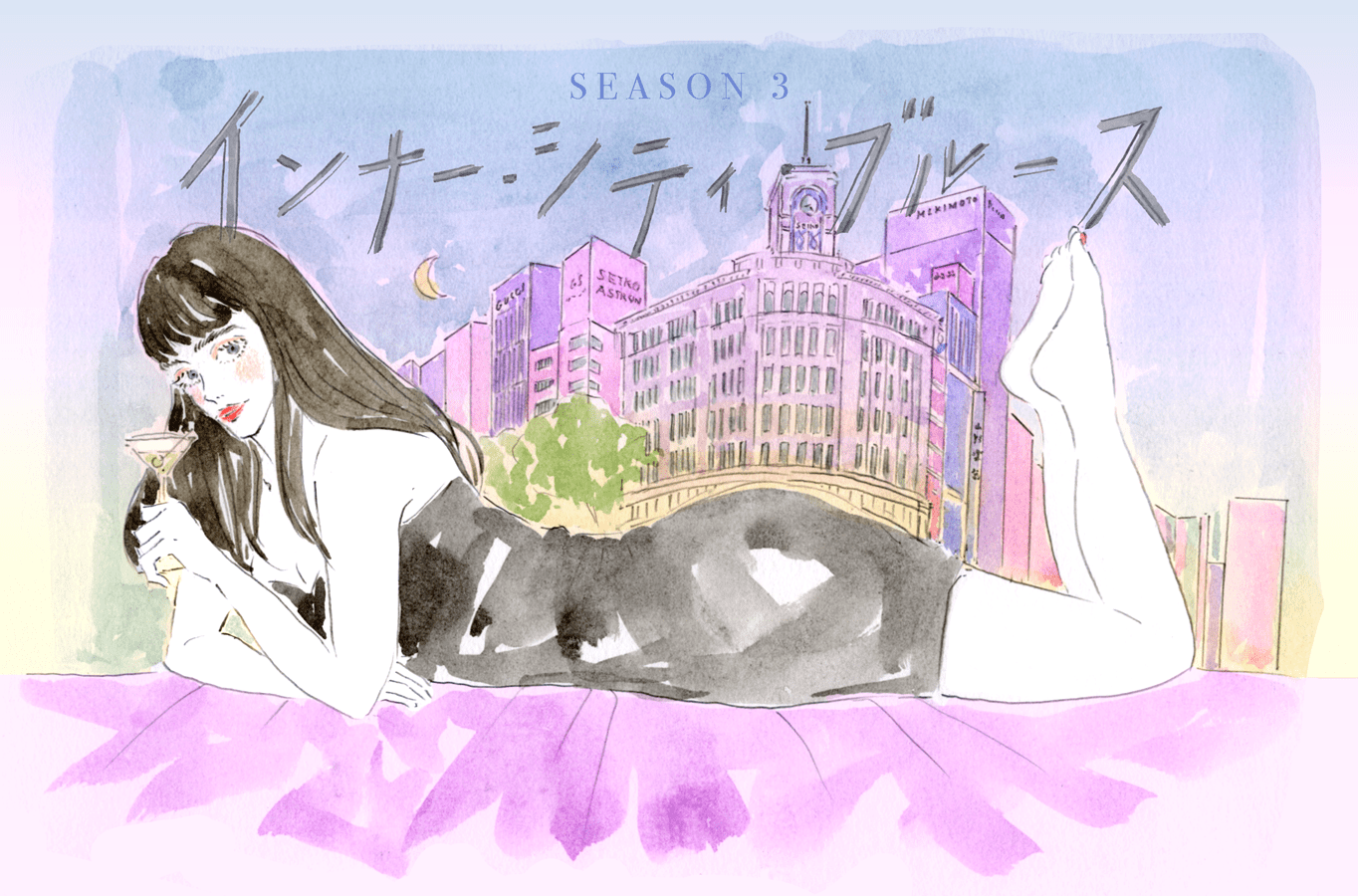毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3がスタート。新たな幕開けは、銀座を本拠地に繰り広げられる探偵物語? ディストピア感が増す東京を舞台に繰り広げられる、変種のハードボイルド小説をご堪能ください!
【あらすじ】
主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)は29歳のフリーター。銀座の外れにあるかつての行きつけのバー「アルゴンキン」へ行くと、店は様変わりし、見知らぬ若い女が一人そこにいた。彼女の名前は囲間楽(かこいま・らく)。新型コロナとママの病気で店が立ち行かなくなったため、楽がスペースをまた借りして現状に至るようだ。 しかし回郎の「アルゴンキン」でのツケは500万円以上という衝撃の事実が発覚し、借金返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収するという仕事を引き受けるはめに……
「アルゴンキン」の未収金回収を始めて1ヶ月くらい経ったある晩、俺はこの仕事を引き受けたことをはじめて後悔していた。
それまではそれなりに順調といえた。少なくとも勤務先である旅行代理店が崩壊していくのを眺めていただけのそれ以前より、遥かにやりがいがあった。
普段の仕事は大体こんな感じである。アルゴンキンのオーナー代理である囲間楽(かこいま・らく)から不定期にメールで送られてくる顧客リストをもとに、連絡先を調べて彼らの勤務先へと押しかける。そこで未収金の明細が書かれた請求書と「アルゴンキン・マネージャー 町尾回郎(まちお・まわろう)」と印刷された名刺を渡し、「アルゴンキン」の伝説の女主人ドロシー・ママの窮状を訴え、支払いを求めるのだ。
相手の多くは法外な金額に驚き、若干の抵抗を示し、時には声を荒げながらも、最終的にはこちらの求めに応じてくれた。大概は分割払いの条件付きだったが。
高額の請求に応じられるのは、ドロシー・ママが見込んだ通りに彼らが出世して、交際費がふんだんに使える身分になっていたからだ。支払わなかった場合、「アルゴンキン」を紹介してくれた取引先に迷惑をかけてしまうのではないかという、ビジネスマン的な判断も働いたのかもしれない。
でも世の中には、交際費枠を持てるほど出世せず、ビジネス上の礼儀なんか知ったこっちゃないという人間の方が遥かに多い。俺もまさにそっち系だったし、その夜の相手はそういう意味で俺の仲間だった。
時計の針を5時間ほど戻してみよう。その日の夕方、「アルゴンキン」あらため「囲間インテリアデザイン事務所」に顔を出すと、いつものようにマティーニグラスを右手に持ったまま、楽さんが話しかけてきた。
「マワロー、地雷原(じらいげん)フミヤって知ってる?」
「誰ですか、それ?」
「ひとりでお笑いやってる人をピン芸人って言うんだっけ? そういう人らしいんだけど」
楽さんは、コロナ対策用に設けられたガラス壁越しに、タブレット端末の画面をこちらに向けた。ネットにアップされた動画がそこにあった。小さなクラブで行われたお笑いライブの様子を客席から撮影したもののようだ。ステージ上ではアラサーらしき男がひとり、マイクの前で猛烈な勢いで喋っている。好青年っぽい穏やかなルックスとは対照的に、話している内容は毒気に満ちたものだった。
「どう思う?」
楽さんが尋ねてくる。
「どうって……日本のお笑いっぽくないっすね。なんだかアメリカっぽい」
ネタは「東京オリンピック パラリンピックが経済的に大きなプラスになる」との政府の主張や、デマゴーグ的なユーチューバーたちを完膚なきまでに叩きのめしたものだった。
時事ネタを扱うお笑い芸人は日本にも少なからずいる。でもその90%が「知識はないけど勘が鋭い」ストリート・スマートなタイプであるのに対して、地雷原フミヤのネタには相当な知性と知識のバックボーンがあるように思えた。
「やっぱりそうなんだ。ドロシー・ママが彼のことえらく気に入っていたみたいで」
「なんとなくわかります。あの人、口癖のようにサミー・デイヴィス・ジュニアこそ最高のエンターテイナーだって言ってましたもんね」
「アルゴンキン」の女主人ドロシー・ママは、ニューラテン・クオーターでホステスとして働いていた若い頃、当時のアメリカの一流アーティストのステージを毎晩のように間近で観ていた。そのせいか音楽も笑いもやたらアメリカンなものが好みだったのだ。
「今から2年くらい前に、常連のお客さんがいかにもママが気に入りそうだからって彼を店に連れてきたみたい。それから時々、日曜の夜に飲みにくるようになった」
「アルゴンキンって日曜も営業していたんですか? 銀座のこういうお店って、普通は土日は休みだと思ってました」
「テレビ局のプロデューサーや芸能プロダクションの重役が貸し切り状態で飲んでいて、そこで情報交換や売り込みが行われていたみたいなんだよね。地雷原フミヤもそこでネタを見せていた」
「結果はどうだったんですか?」
「マワローが知らないんだから、結果は言うまでもないでしょう。ママのメモにはこんな風に書いてある。『ネタ自体は絶賛されるも、素に戻ったあとのアドリブや返しが弱すぎとダメ出しされる』って」
なるほど。日本のテレビ番組に出るようなお笑い芸人は、実際はネタそのものではなく、ネタ終わりのフリートークで面白いかそうでないか判断されているのだ。家でネタを徹底的に作り込んでくるタイプの地雷原フミヤは、日本のテレビにとことん向いていない芸人だったわけだ。
「地雷原フミヤはそれからもしばらく顔を見せていたけど、去年のクリスマスを境にアルゴンキンに寄りつかなくなったの。ツケはトータルで73万6218円」
俺の532万4649円に比べれば随分マシだけど、売れないお笑い芸人に到底払えるような金額ではない。しかも新型コロナのせいで、お笑いライブ自体ほとんど開かれていない状態だ。返済できる可能性は限りなくゼロに近い。
「単純に芸人としてやっていくのを諦めたんじゃないですか。コロナで仕事もないだろうし」
「それが違うみたい。予告無しに一切の消息を絶っているんだよね。SNSのアカウントも年末にひとつ残らず削除されている」
コロナ不況で廃業したお笑い芸人は結構な数いるはずだ。でも芸人を目指す人間なんて承認欲求の塊のはず。SNSをぜんぶ削除するなんて余程のことが起きたにちがいない。
「なにかトラブルに巻き込まれた可能性が高いってわけですか。でも行方をくらました人間の居場所なんてどうやってわかるんですか?」
俺がそう質問すると、楽さんは動画をリワインドして一瞬映り込んだ客席の一部を指先で拡大した。肌が青みがかって見えるほど色白の女が、ただでさえ大きな瞳をさらに大きくしてステージを凝視している。
「名波玲(ななみ・れい)、28歳。群馬県出身で、前橋女子から早稲田の政経学部に現役合格。2016年から経済産業省に勤務している」
「うわ、エリートですね」
「偶然この動画を見たうちの執事が『名波さんにちがいない』って言うんだよね。経済産業省で打ち合わせをしたとき、凄く頭が切れて見た目にも特徴があったから記憶に残っていたって。調べてみたら地雷原フミヤの他の動画にも映りこんでいた」
楽さんの口から当たり前のように「うちの執事」という言葉が出てきたのには内心驚いたけど、俺は話を続けた。
「でもお笑いマニアの官僚がいたっておかしくはないですよね?」
「実はほかにアップされていた地雷原フミヤの動画のネタに、どんな些細なことにも計画表を作りたがるコントロールフリークのガールフレンドってのがあるんだよね」
「なるほど、ふたりは付き合っていて、ネタのモデルは彼女ってことか」
「そう。名波玲なら彼が今どこにいるか知っているかもしれない。ひょっとするとまだ付き合っているかもね。だからこの子がどこに住んでいるか、まずは特定して」
そんなわけで、俺は名波玲の勤務先である経済産業省総合庁舎本館の玄関前で、帰路につく彼女を待ち伏せすることにした。経済産業省には東京メトロの霞ヶ関駅と直結した地下出入口もあるのだが、俺は地上から出てくるに違いないと睨んでいた。若手職員の彼女は、タクシーで家に帰るレベルの役職者の秘書的な役割を与えられているだろうから。
霞ヶ関に到着したのは午後5時過ぎだった。俺は原発再稼働反対のピケを張る人々の横で、まるで仲間のようなフリをしながら彼女を待った。さすがに定時にあがってくるとは思わなかったけど、いつまで経っても相手が姿を見せないことにイライラしてきた。俺の前をいかにも仕事が出来そうな同年代の男女が慌ただしく通り過ぎていく。俺の背中側には財務省の庁舎が建っていて、その左右にはそれぞれ文部科学省と外務省の庁舎があったから、そのうちどれかの職員なのだろう。
俺が未収金回収の仕事を引き受けたことをはじめて後悔したのは、まさにこの瞬間だった。官庁の街、霞ヶ関には東京の盛り場には一定数いる「何をやって暮らしているのかわからない」人の姿が全く見えない。ここには日本政府を動かしているプロフェッショナルしかいないのだ。そんな街で、俺はお笑い芸人がこしらえた借金回収のためにあてもなく佇んでいる。残酷なまでのそんな真実が、俺を軽く落ちこませていた。
でも悲しいけど、これが今の俺の仕事だ。あたりが徐々に暗くなり、腹も減ってきたけど、コンビニに立ち寄っている間に名波玲が通りすぎてしまうかもしれないので、一瞬でも目を離すわけにはいけなかった。ピケを張る人々も帰り、ひとりぼっちになってしまったが、俺は空腹と戦いながら彼女をひたすら待ち続けた。
恰幅の良い中年男と共に、レザーバッグを抱えた女が硬い表情で出口から出てきたのは、夜の9時30分を過ぎた頃だった。マスクをしているので判別しにくいが若いことは間違いない。
彼女は上司が乗り込んだタクシーを見送ると、東京メトロへの通路階段出入り口にむかって歩きはじめた。
その時だった。大柄の男が女の前に突然飛び出してきた。白いタンクトップシャツの上に黒いジャージのセットアップを着ている。髪の毛は金髪にブリーチしていたが、時間が経過しているのか生え際は真っ黒だった。どう見ても官僚ではない。ジャージ男は大声で女に話しかけてきた。
「おい、鍵を借せよ。テメエさー、汚ねえ真似すんじゃねえよ」
女は一瞬驚いた顔をしたが、表情をすぐ元に戻すと大声をあげた。
「誰か助けてください!」
経済産業省の玄関に待機していた警備員が近づいてきたので、ジャージ男は舌打ちをして逃げ出した。女は何事もなかったかのように階段を降り始める。俺も慌てて後を追った。
階段を下りるとすぐに千代田線の改札だったが、それには目もくれず地下通路を奥へと歩いていったところを見ると、彼女が千代田線直通の小田急線千歳船橋駅そばにある経済産業省独身寮に住んでいないことは明らかだった。
女は日比谷線の改札からホームへと入っていき、そのまま奥へと歩き続けた。この先にある丸の内線のホームに行こうとしているのだ。
丸の内線には池袋行きと荻窪行きの列車があったが、彼女が名波玲なら荻窪行きに乗るに違いないと俺は思った。案の定、女は荻窪行きの電車に乗り込んだ。俺も同じ車両に乗ると、気づかれないように5メートルほど離れた場所の吊り革につかまって様子を伺った。
女は冷静そのものの表情でスマホをチェックしている。さっき大声をあげたときの行動はパニックっていたのではなく、警備員に聞こえるように計算しぬかれたものだったのだ。彼女はこうしたトラブルには慣れっこになっているらしい。
あのジャージ男は風体からいって闇金の人間だろう。アルゴンキンで行われたネタ見せ会で評価されず、コロナのせいで舞台の仕事も失った地雷原フミヤは、あちこちに借金した挙句、遂には闇金に手を出したのかもしれない。そしてある日、姿をくらました。
ジャージ男は偶然、名波玲の存在を知り、借金を回収したいあまり、彼女を脅しているのだろうか。しかし彼女は今のところそれに屈していないようだ。彼の居場所を知らないのか。それとも隠しているのか。ハッキリしているのは自分がジャージ男と同じ借金取りという事実だけだった。
荻窪行きの電車は、中央線の乗換駅である四谷、伊勢丹がある新宿三丁目と通り過ぎていく。女は乗客の半分以上が降りる新宿でも席に座ったままだった。予想通りだ。名波玲は中野坂上で下りるはず。俺の読みは当たった。女は中野坂上でホームに下りると、改札を出てエスカレーターで地上へと上がっていった。気付かれないように俺も間合いをあけながら後を追った。
新宿から丸の内線で荻窪方面に二駅目、山手通りと青梅街道が交差する場所にある中野坂上は、新宿で深夜まで飲んでも歩いて帰れる立地にありながら、チェーン店にまじって昔ながらの個人経営の店も並んでいる緩いヴァイブスが漂う街だ。スーパーやファミレスも複数あるから、その気になればこの街だけで全てまかなって暮らしていくことも出来る。
同じようなポジションの街に三軒茶屋があるけど、中野坂上の方が遥かに家賃が安い。このため中野坂上は、売れないお笑い芸人が大勢住んでいる街としても知られていた。名波玲は、霞ヶ関とは正反対の、「何をやって暮らしているのかわからない」人ばかりが住むこの街で、地雷原フミヤを匿っているに違いない。だからジャージ男は、部屋の鍵を貸すよう彼女を脅したのだ。
名波玲はコンクリート打ちっぱなしのクールな駅ビルの敷地を抜けると、狭い路地へと入っていた。大通りから一歩入ったこのエリアには昔ながらの住宅街が広がっている。彼女がスーパーやコンビニに立ち寄らなかったのは、地雷原フミヤが夕食を作って待っているからだろうか。空腹をこらえながら俺はそんなことを考えていた。
彼女は6分ほど歩くと、エリート官僚にしては質素なプレハブ造の三階建アパートのエントランス内に姿を消した。彼女の姿が見えなくなるのを見計らうと、俺は集合玄関のポストを確認した。
「202号室 名波」、ビンゴ。急いで通りに戻って202号室にあたる部屋を見上げたけど、窓に灯りはついていない。しばらくするとそこは明るくなった。部屋にたどり着いた名波玲がスイッチをつけたのだろう。つまり地雷原フミヤはここには住んでいない可能性が高い。
俺はスマホをポケットから取り出すと電話した。
「楽さん? 名波玲の部屋を発見しました。中野坂上です。たぶんひとり暮らしですね。でも彼女、別の借金取りにも付きまとわれているみたいで」
「その借金取りはプロなんでしょう? マワローはビギナーなんだから、気をつけないとダメだよ」
借金取り歴は短くても、ビギナーでは断じてない。俺は旅行代理店のツアー企画兼同行者として、ジェットセッターからギャングスタまで、世界中のあらゆるお客の相手をしてきたのだから。修羅場にもそれなりに慣れているつもりだ。
「でも俺も前の仕事でそっち系のお客は経験してますんで……あっ」
思わず声をあげたのは、服を着替えた名波玲が再びエントランスから出てきたからだ。結いていた髪をおろしてキャップを被り、Tシャツのうえにヴィンテージっぽいオーバーサイズの半袖シャツを羽織っている。この界隈に住む二十代女子の典型的なファッションといえる。エリート官僚から大変身だ。
「名波玲が外に出かけるみたいです。もしかしたら地雷原フミヤとどこかで落ち合うのかも。俺、もう少し追ってみます」
楽さんに小声でそう伝えてスマホを切ると、俺は尾行を再開した。
小説『インナー・シティ・ブルース』シーズン3
イントロダクション:ファウンド・ア・ジョブ(銀座)
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク