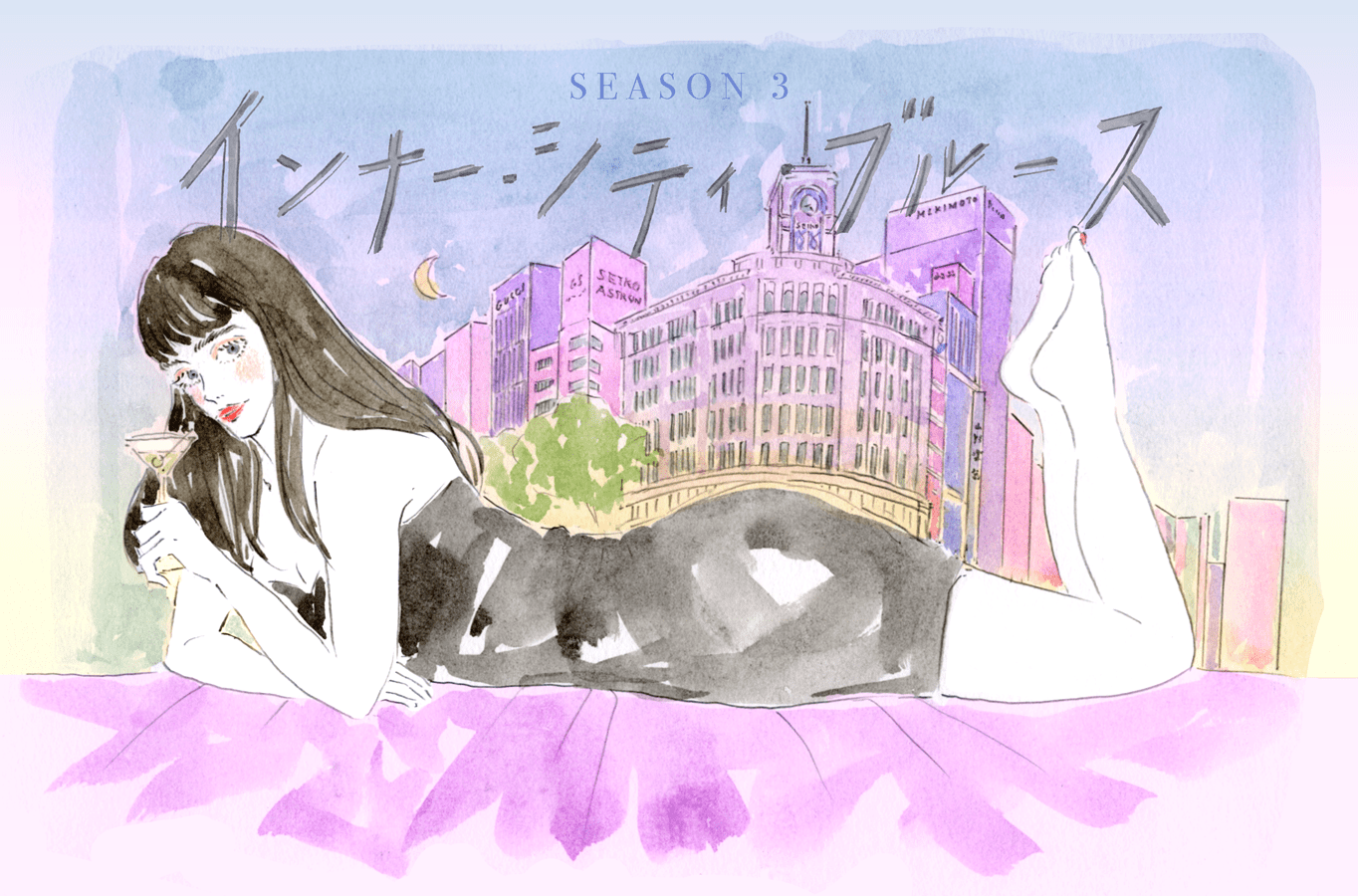毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3がスタート。新たな幕開けは、銀座を本拠地に繰り広げられる探偵物語? ディストピア感が増す東京を舞台に繰り広げられる、変種のハードボイルド小説をご堪能ください!
【あらすじ】主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)は29歳のフリーター。銀座の外れにあるバー「アルゴンキン」での過去のツケ返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収する仕事を引き受けている。今回の標的は弱冠27歳のアパレルショップ経営者、円山和馬(まるやま・かずま)。円山に会いに行くと、マワローが追っている男ではないことが判明し、円山を騙る別人物がいることを知る。しかし円山はその借金を肩代わりすると申し出て、その代わりにある女性を探すことに。紆余曲折を経て遂にその女性と対面し、円谷の使いで来たことを彼女に伝えると……。
「杏奈ちゃん、この方、WFFMの採用の人だって」
谷中純情亭のおかみさんが、カウンターに座る俺を大声でそう紹介すると、武田杏奈はその場で凍りついたようになった。
「町尾回郎(まちお・まわろう)と申します。円山社長の使いで来ました」
彼女のただでさえ大きな瞳がさらに見開かれ、整った顔から血の気が引いていく。緊張のせいだと思い込んだおかみさんは、駆け寄って肩に手を置いた。
「これから大事なお話があるんでしょう? 今日は休んで。ふたりで何とかするから」
そう言われた杏奈は、「はい、ありがとうございます」と小さな声で返すと、扉を押してふらふらと店の外に出ていった。
「町尾さん、是非お願いしますね」
おかみさんとマスターに見送られ、俺も外に出る。階段の下で俺を待っていた彼女は、自分に罰が下されることを覚悟した表情をしている。まずは安心させないと。
「武田さん、円山社長は怒っている感じじゃなかったですよ」
杏奈は思い詰めたトーンで言い返してきた。
「今はそうでなくても、本当のことを知ったら怒ります」
「事情を聞かせてくれませんか。でも全貌を知るにはあなた以外にもうひとり会う必要がありますけど。誰だかわかりますよね?」
「兄ですね」
そう口にすると彼女は、ダウンジャケットのポケットからスマホを取り出してどこかに電話した。
「あ、お兄ちゃん? うん、ぜんぶバレた。会いたいって言ってるから連れていく」
彼女は通話を打ち切ると、そのまま歩き出した。俺もついていく。俺たち二人は谷中銀座の商店街を千駄木駅とは逆方向に歩き続け、「夕やけだんだん」と呼ばれる長い階段を登って谷中霊園の前まで出た。振り返って眺めると、狭い通りは夕飯の買い出しにやって来た買い物客で埋め尽くされている。雑誌の下町特集でよく使われるアングルだ。
さらに先へと歩いていくと、JR日暮里駅の改札口に面した下御隠殿橋(しもごいんでんばし)の欄干から身を乗り出した人々が、眼下の景色をカメラやスマホで撮影しようとしているのに出くわした。
下御隠殿橋の下には14本の線路の上を、山手線、京浜東北線、東北・北陸・上越・秋田・山形の各新幹線、高崎線、宇都宮線、常盤線、そして京成本線が走っていて、一日に20種類、約2500本もの列車が行き交う姿を眺められる。俺も旅行代理店時代に海外の鉄オタを、ここに案内したことがある。
大勢の人々がこぞって下を向いている姿は相当シュールだけど、杏奈にとっては日常の風景なのだろう。無反応で通り過ぎると、そのまま日暮里駅の東口側に出て、奥の商店街の通りへと入っていった。徐々にあたりの景色が変わり始める。どの商店の店頭にも布のハギレが並べられ、店の奥には巨大な布ロールが積み重ねられている。そうか、日暮里繊維街まで歩いてきたというわけか。
日暮里繊維街は、大正時代に浅草から集団移動してきた繊維業者たちが作った問屋街だが、現在は一般客相手の店も増え、あらゆる繊維資材や革素材、ボタン、アクセサリーを入手できる街として、裁縫マニアや手芸愛好家を引き寄せている。杏奈がファッションについて豊富な専門知識を持っていたのは、この界隈で育ったからかもしれない。
彼女は、商店街の大通りからひとつ奥まった通りに立つ古いビルの階段をあがっていった。2階踊り場の正面扉に「Takeda Clothing」と刻まれた木製のプレートがかかっている。杏奈を追うように俺も室内に足を踏み入れた。部屋いっぱいの大きなテーブルの上には、布ロールや生地見本が幾重にも積み重なっている。奥の部屋の扉は開けっぱなしになっていて、業務用ミシンで作業する男の背中が見えた。
「ただいま」と杏奈が呼びかけると、その男が振り向いた。冷徹な眼差しと意志の強そうながっしりした顎。「俺が追っている方の円山和馬」こと武田松斗だ。俺は彼に近づくとお辞儀をして名刺を手渡しした。松斗は「アルゴンキン マネージャー」と書いてあるのを見て、少し動揺したようだった。
「武田松斗さん、あなたはWFFMの円山社長の名前を騙って、アルゴンキンで飲みましたね? そのときの代金がまだ支払われていません」
杏奈が尋ねる。
「いくらなんですか?」
「972万5800円です」
彼女は俺ではなく兄の方を見て叫んだ。
「わたしがお金がないから大学を休んでいるのに、エッチなところに通っていたわけ? 信じられない!」
「バカ、ちがうよ!」
きょうだい喧嘩に巻き込まれるのはごめんだ。慌てて訂正する。
「杏奈さん、ご心配なく。アルゴンキンは、銀座にある歴史あるカウンターバーです」
「ああ、ガールズバーなんだ。お兄ちゃんはぼったくられたってわけね」
若い彼女にとって、アルゴンキンは理解不能な場所のようだ。
「町尾さん。何かの間違いじゃないですか。見ての通り、わたしは慎ましくやっている仕立て屋ですよ」
松斗がしらばっくれる。今こそ「サプライズその1」を発表する時だ。
「お部屋の様子を見てわたしもそう思いました。でも真相を知りたがっているのは、わたしじゃなくて別の人なんです。そろそろ来るはずです」
俺が彼にそう話した直後にドアブザーが鳴った。杏奈がドアを開ける、そこに立っていたのは本物の円山和馬だった。谷中純情亭で杏奈を待っていた時から、俺は自分の居場所を逐一ショートメールで彼に教えていたのだ。
和馬は感慨深そうに松斗に話しかけた。
「松っちゃん、久しぶり」
続いて彼は杏奈の方を見た。
「杏奈ちゃん、気づかなくてごめん」
彼女は視線を逸らしながら口を開く。
「最後に会ったのは、わたしが幼稚園のときだから、気づくわけないですよ」
「やっぱりふたりとは知り合いだったんですか」
俺の問いに和馬は答えた。
「ある時期まで一緒に育ったようなものだったんだ。松ちゃんのお父さんは、俺のオヤジと一緒に仕事をやっていたから」
松斗の表情が変わる。
「和馬のオヤジさんが加わったのは、随分後の話だろ。WFFMを創立したのは武田家なんだから」
「えっ、ウィキペディアにはそんなこと書いてなかったですけど」
俺がツッコむと、松斗に睨まれた。
「俺も何回もウィキを修正しようとしたんだけど、なぜか管理人にすぐ文章を戻されちゃうんだよ。正しい歴史を今から話すから、町尾さんが今度書き込んでくれないかな」
「わかりました」
俺が同意すると、彼はWFFMの知られざる歴史を語り始めた。
「武田クロージングは、もともと祖父が上野のアメ横ではじめた輸入衣料店だった。最初はアメリカ進駐軍が放出したスーツ生地を扱っていたらしい。それが父の代になると、スーツから型紙を起こして、繊維街で仕入れた生地でオリジナルの服を作るようになった。そこに大学生バイトとして入ったのが、和馬のオヤジさん、円山辰平だった。武田クロージングの服作りの哲学に惚れ込んだ彼は、父が資本金を出した子会社の社長として明治通り沿いに2号店をオープンした。店名は武田クロージングだと古臭いからと、父が「Wind,Forest,Fire,Mountain」と名付けました。ネーミングの由来はわかりますよね」
風林火山……名字が武田信玄と同じことから来る駄洒落か。ふと和馬の方を見ると、「経営方針じゃなかったのか」とショックを受けている。父親に騙されていたのだろう。松斗は話を続ける。
「WFFMは渋カジブームで雑誌に取り上げられる人気店になり、系列店も幾つか出したんですが、バブル崩壊に巻き込まれて経営不振に陥ってしまった。このとき父と円山辰平の間に意見の対立がおこったんです」
和馬が補足する。
「松ちゃんのお父さんは店舗を絞って高級店化したがったけど、うちのオヤジは価格を下げて店舗規模を拡大する路線を選んだんです」
松斗が語る。
「路線を選ぶにしてもやり方が汚かったよな。円山辰平は、彼を後押しする銀行とグルになってWFFMの株式を増資した。その結果、父の持分を薄めてしまったんです。経営から外された父は、体を壊して15年前に失意の中、死にました」
なるほど。非上場企業のオーナーシップを巡る争いだから、ウィキには乗っていなかったわけだ。杏奈も兄に続いた。
「母は介護疲れで心をおかしくしちゃって。兄とわたしは子どもの頃から円山家が諸悪の根源だって吹き込まれて育ったんです。本気にはしていなかったけど、バイト先で和馬さんに偶然会ったときはさすがに驚いちゃった」
丸ビルで開催されたアパレル業界のコンベンションの時か。だから過呼吸になったんだ。
「その体験を兄に話したら、インターンとしてWFFMに潜り込んでくれないかって頼まれたんです。わたしは気が進まなかったけど、仕事の内容に興味があったから協力することにししたんです。でも履歴書に武田杏奈って書いたら、正体がバレちゃうじゃないですか。そこでバイトで一緒だった子の名前と連絡先を使わせてもらったんです」
黙りこんでいる和馬に松斗が語りかける。
「杏奈の名誉のために言っておくと、こいつは普段は真面目に働いていたと思う。俺がやらせたのは、和馬の名刺を何枚か拝借するのと、株主の連絡先台帳をコピーさせたこと、そしてそのうちの誰と和馬がよく会っているかを教えてもらっただけだ」
「松ちゃんはその情報を使って何をやった?」
和馬が尋ねると、松斗が得意げに話す。
「WFFMの有力株主のひとりがアルゴンキンの常連だったのを知った俺は、和馬の名刺を使って店に通うようになった。そして仲良くなってから正体を明かして、WFFMのあるべき未来の姿をプレゼンして賛同を得たんだ。その人が他の株主も紹介してくれてね。アルゴンキンで再建計画がまとまっていったよ。来年の三月に開催される株主総会でそれが議題にあがるはずだ。和馬は反対するだろうけど、過半数はもう押さえている」
「松ちゃんが代表取締役に就任して、俺はクビになるってわけか。だったらついでにWFFMの未来がどんなものか教えてくれないか」
和馬がそう尋ねると、松斗はホワイトボードをひっくり返した。そこには財務指標や新聞の切り抜き、色とりどりのポストイットがびっしりと貼られていた。
「COVID―19はモード界を永遠に変えてしまった。今後、オフィス通勤が復活しても、サラリーマンがユニフォームとしてスーツを着る時代は二度と戻ってこない。だとしたらWFFMが取れる道はふたつのうちのどちらかしかない。ひとつはカジュアル衣料の比重をさらに増やしていくこと。もっとも、こちらはWFFMがすでに取り組んでいる。今のところは別ブランドとの限定コラボ商品が好調なようだけど、長期的に見ればWFFM単独のブランドを毀損しているだけだ。それに同じフィールドでファスト・ファッションと戦えるとは思えない」
「値段で勝てないですもんね」
俺が口を挟むと、和馬が言い添える。
「クオリティでも勝てないですよ。大量に作るほど、良いものが安く作れるから」
彼がロードサイド店のスーツを高く評価していたのを思い出した。
「そこで浮上するのが、もうひとつの道なんだ」
松斗は自信ありげに語る。
「レディメイドからオーダーメイドへの回帰だよ。質の高い製品を相応の価格で販売する一方で、購入者には、お直しや修理をクリアーな金額体系で示して半永久的なフォローをする。手間はかかるけど、大量消費の使い捨てを旨とするファスト・ファッションと決定的な差異を図れるのは確かだ」
それはWFFMが武田クロージングだった昔に回帰させることにもなる。復讐としてもなかなか良い計画だ。
松斗のプレゼンに聞き入っていた和馬が口を開いたが、その言葉は意外なものだった。
「松っちゃんの意見に賛成だ」
どういうことだ?
「ロンドンにいたとき、俺はサヴィル・ロウの文化に心酔しちゃってね。だから日本に帰ってきて、社長として真っ先にやりたかったのは、そっちの道だったんだよ。でもそれを実現するにはWWFMはあまりにも大きくなりすぎた。もしやろうとしたら大量リストラは避けられない。でもこのコロナ騒動の最中にそんなことがやれるか? 社員の生活を預かる経営者として俺は出来なかった。これはまだ秘密なんだが……悩んだ末にラッフルズ・インベストメントに資本参加してもらうことにした」
「ラッフルズ・インベストメントって?」
「シンガポールの投資ファンドだ。俺の持分の株をすべて売却する。あの会社は信じられない高値でほかの持分も買いたがっている。3月の株主総会で俺から報告する予定だ。付け加えると、しばらくは俺が社長を続ける予定で、杏奈ちゃんも良かったら働いてもらいたい」
もはや松斗は平静を保っているフリをするのが精一杯の様子だった。そりゃそうだ、自分の再建計画に一旦は乗った有力株主だって、目の前で札束をちらつかせられたら、和馬の売却案に乗り換えるに決まっている。WWFMを取り戻す松斗の長年の夢は泡と化したのだ。和馬は俺にむかって言った。
「お約束した通り、アルゴンキンのツケはWWFMが支払います。松ちゃんや杏奈ちゃんの思い入れが深い会社を、他の会社に売ってしまうことが気に咎めるってのもあるんですが、実はオヤジの時代の使途不明金がほかにもあるので、さっさと損金処理してしまいたいんです」
彼が「12月決算だから身綺麗にしないといけない」と言っていたのは、ラッフルズ・インベストメントに会計上クリアーな状態で会社を譲渡する必要があったからなのか。
武田兄妹は呆然としている。今こそ「サプライズその2」を発表する時だ。
「松斗さん、アルゴンキンのオーナーのドロシー・ママはあなたのヴィジョンに将来性を見出していたようでした。ですからママの意思を尊重して、ツケはこれまで通り出世払いにさせて頂きます」
「どういうことだ?」
松斗の疑問に俺は答えた。
「円山社長からアルゴンキンに972万5800円が振り込まれたら、それをそっくりそのまま武田クロージングにお預けします。社長からもすでに内諾を得ています。考えてみたんですけど、松斗さんの計画ってWWFMの看板がなくても、ある程度の資金があれば始められるんじゃないですか。但しそれには条件があります」
「条件とはなんですか?」
「その資金の一部で、杏奈さんを大学に復学させてください」
顔を輝かせる杏奈を見た松斗が、和馬に話しかける。
「そもそも俺には条件について文句を言う資格なんてない。でも和馬、金を受け取っていいのか? 俺たち、会社を乗っ取ろうとした敵なんだけど」
和馬は笑った。
「松ちゃん、その計画を始めておいてくれよ。一段落したら俺もそっちの会社に合流させてもらうかもしれないし」
俺は、杏奈が微笑んだように見えた。そろそろ幕引きだ。
「杏奈さん、今川瑠璃さんにはWWFMの人事部が勘違いしていたって俺から報告しておきます。きっと彼女なら信じるでしょう。じゃあ俺はここで失礼します。幼馴染同士で思い出でも語りあってください。メリー・クリスマス!」
そう言うと、俺は扉から勢いよく外に出た。人気がなくなった日暮里繊維街を歩きながら、囲間楽に電話をかけた。彼女は待ち侘びていたのか、すぐに電話に出てくれた。
「マワロー、推理は当たった?」
「意外な事実も明かされましたけど、三人が知り合いってところは当たっていました」
「じゃあ、借金を一気に減らすチャンスをわざわざドブに捨てたんだ?」
「それは言わないでくださいよ。でも俺、最高に格好良かったんですよ? 楽さん、あの場に居たら良かったのに」
「じゃあ飲みながら話を聞かせてよ、店は開けとくから」
「飲み代は……」
「ツケに加算するに決まってるでしょ」
電話は切れてしまった。夕闇の中、空気が一層冷え込んできた。今にも雪が降ってきそうなくらい、寒い。でも駅へと向かう俺の足取りは軽快そのものだった。
『インナー・シティ・ブルース』発売記念
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク