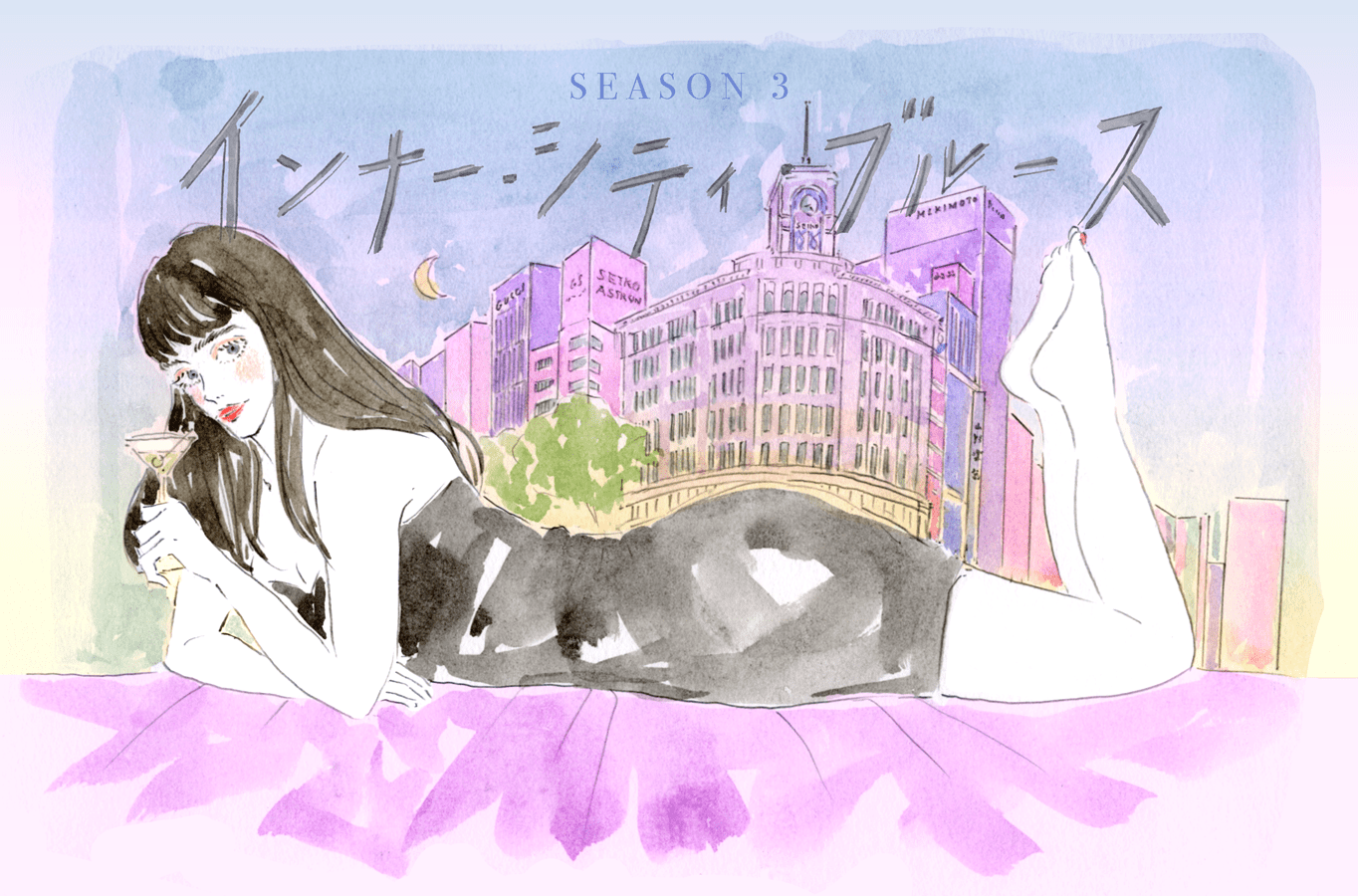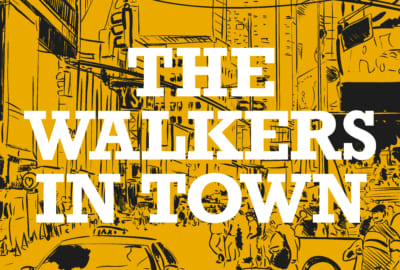毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3がスタート。新たな幕開けは、銀座を本拠地に繰り広げられる探偵物語? ディストピア感が増す東京を舞台に繰り広げられる、変種のハードボイルド小説をご堪能ください!
【あらすじ】主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)は29歳のフリーター。銀座の外れにあるバー「アルゴンキン」での過去のツケ返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収する仕事を引き受けている。今回の標的は昭和13年生まれの戦中派、向原功。裕福ではないが、モダンジャズの知識と愛情が豊富で、ジャズにうるさい他の常連から一目置かれていた。しかしツケを回収しようと、電話したのがちょうど向原功の葬式の翌日だった。49日が明け、回郎が、あのとき電話に出た向原の妻、節子を訪ねると……。
日比谷で乗り換えた都営三田線が、高島平に着いたのは10時過ぎのことだった。駅の改札から出ると、俺はすぐ目の前にそびえる高層マンション街にむかって歩き出した。高島平団地だ。
高度成長の時代、人口が急増した東京の深刻な住宅問題を解決すべく、日本住宅公団が広大な耕作地の跡に建設した、64棟もの建物からなるこの巨大なコミュニティは、1972年の完成から半世紀経った今も1万6000人もの住民が暮らしているという。
大通りに面した1階フロアーには、その住民たちの日常生活を支えるための様々な商店がテナントとして入っていた。区画のところどころにシャッターが下りてはいたものの、多摩ニュータウンのような侘しさは感じられず、それなりの賑わいを見せている。なにより若い親子連れの姿が目立つ。大手町まで30分強というアクセスの良さのお陰だろうか。
年季の入った案内板で目的の棟を確認する。そこから3分ほど歩くと、薄いオリーブグリーン色の建物に着いた。棟内に入るとエレベーターホールに向かい、昇降ボタンを押した。高島平団地が完成した1972年の時点では、オートロック設備はまだ一般的ではなかったらしい。そのため各住戸の玄関先まで誰でもノーチェックで行くことが出来るのだ。
こうした仕様と、高層マンションが珍しかった当時の状況が原因となって、悲劇が起きた。世を儚む人々が、都営三田線に乗ってわざわざ高島平団地に飛び降りにやって来るようになったのだ。マスコミが「自殺の名所」として報道したことが更に事態を煽る形となり、1980年から82年にかけては50名以上がこの団地から飛び降りて命を絶ったそうだ。
このため現在の高島平団地では、3階以上のすべての開口部に飛び降り防止用の柵が嵌め込まれている。今日訪れた棟の共用廊下も、てっきりそうなっていると思い込んでいたのでエレベータを降りた途端、予想と異なる景色だったことに驚いた。廊下が屋外とは繋がっておらず、向かい側の建物の廊下と回廊状に結ばれていて、中心が巨大な吹抜けを構成していたのだ。吹き抜け部から身を乗り出して上を見上げると転落防止用の金網ごしの初春の薄い青空が、下を覗きこむと底部に張り巡らされた夥しい数の給排水用パイプがこちらに向かって上方に伸びてきているのが見えた。
「これが、久世野さんが話していたツインコリダー型住宅か」
集合住宅の一階に、集会室や商店といった広い面積を必要とする共用施設をもうける場合、上層部の住宅の設備配管がそれらの間取りに影響を及ばさないようにと考案されたツインコリダー型は、維持管理しやすい反面、廊下側の景色が殺伐としたものになってしまう。
加えてデッドスペースが多くなるため、採算性が重視される現在の集合住宅では滅多に採用されないそうだ。しかしその希少性から、わざわざ遠くから見学にやって来る建築マニアが多いようで、前職の旅行代理店時代に先輩だった久世野照生はそうした需要を当て込んで「面白公団ツアー」なるものを企画していた。高島平団地のツインコリダー棟はそのツアーのハイライトを構成していた。
久世野さんから既に写真を見せられてはいたが、肉眼で見る吹き抜け部からの光景は圧巻だった。建築系ブロガーはよくこの景色を、『スター・ウォーズ』のデス・スターや『ブレードランナー』の宇宙船内部に喩えるそうだけど、建物の色がくすんだオリーブグリーンだったこともあって、俺は戦艦の内部にいる気分になった。
部屋番号を見ながら回廊を歩いていき、そのひとつのスチールドア横のブザーを鳴らす。中からチェーンを外す鈍い音が聞こえた。ドアが開くと、中から白髪の女性が姿を現わした。今日の訪問相手、向原節子だ。
「アルゴンキン・マネージャー、町尾回郎(まちお・まわろう)と申します」
俺は名刺を手渡した。
「まあ、わざわざありがとうございます。どうぞ中におあがりください」
囲間楽(かこいま・らく)から事前に渡されていた資料には82歳と記されていたが、もっと若々しく見えた。でも右手には杖を抱えている。俺は靴を脱いで、スリッパに履き替えた。
「まずは功さんにご挨拶したいのですが」
俺がそう言うと、玄関をあがってすぐ横の和室に通された。正面奥に小さな仏壇が置かれている。近寄って正座をし、線香に火を灯して、位牌に向けて手を合わせた。俺が、バー・アルゴンキのツケを取立てに来た相手である向原功は、昨年末に急死していたのだ。向原節子は、彼の未亡人だった。
挨拶を終えた俺は、LDKに通されると、ダイニング・チェアに座るよう促された。窓ガラスの向こう側には高島平団地の別の棟が幾つも折り重なって見える。向原節子が日本茶をお盆に乗せて運んできた。
「その折は、大変失礼いたしました」
彼女に詫びたのには理由がある。ツケを回収しようと、電話したのがちょうど向原功の葬式の翌日だったのだ。そんなシチュエーションにも関わらず、向原節子は優しく応対してくれたのだが、あまりに申し訳なかったので訪問は49日が明けてからにしたのだった。
「いいえ、こちらこそお呼びだてしてしまってすみません。でもホラ、私こんなだから」
向原節子は杖を右手でひょいと持ち上げてみせる。
「なにか持病がお有りなんですね」
「5年前に脳出血を起こしてしまいまして。主人は健康そのものだったので、てっきり私が先に逝くもんだとばかり思っておりましたの。ひとの人生って不思議なものですね」
確かに不思議だ。少し昔まで、外国人たち相手に東京を案内して回っていた俺が、今ではバーのツケの取り立てのために同じ都市を駆けずり回っているのだから。
「それで、電話でもお話ししたアルゴンキンの件なのですが。功さんの未払金はこちらになります」
俺はリュックの中から封筒を取り出すと、向原節子に手渡した。彼女は封筒の中の計算書を見て少々驚いた顔をしている。
「あら、こんな額なの」
「申し訳ございません。でも15万円6200円というのはウチにしては少額なのです」
「いいえ、逆です。主人からは銀座の高級店だと聞かされていましたので、この程度で済むのかと思いまして」
「おそらく多くの場合、同席されていた方が勘定をお支払いになっていたのではないかと」
「そうかもしれませんね。主人はジャズをマトモに話せる仲間がいるのは、アルゴンキンだけだって言っておりましたから」
昭和13年生まれの戦中派。もともとはジャズのライブハウスで知り合った別の常連が連れてきた客。有名企業に勤めているわけでも、特別裕福でもなかったが、モダンジャズの知識と愛情が豊富で、ジャズにうるさい他の常連から一目置かれていた男。俺は、囲間楽から渡された向原功のデータを頭の中で反芻していた。
「功さんの世代はジャズがお好きな方が多そうですけどね」
「お茶の水の聖橋学院に通っていたので場所柄、ジャズ好きになったんだと思います。でも大学を中退したせいで元のお友達とは疎遠になってしまったみたいで。だからアルゴンキンに行く日は楽しそうでしたわ」
おそらく中退の理由は60年安保だろう。この年代の聖橋学院生には結構な数の中退者がいたと聞いている。
「功さんのレコード・コレクションは、さぞ凄かったんでしょうね」
「お見せしたかったわ。床が抜けそうなくらいの量があって。もうそんなガラクタを買うのは止めてって何度言ったことか」
「今はもうないんですね」
向原節子がLDKの奥にある小部屋の方を指差した。俺が椅子から立ち上がって覗くと、そこには部屋の壁三面に、重々しいスチールラックが備え付けられていた。だが最下段の隅っこに設置された幅40センチほどの金庫以外は何も置かれていない。
「ここいっぱいにレコードが詰まっていたんですね」
「ええ。でも娘に処分してもらいましたの。いけなかったかしら?」
「いいえ。個人のコレクションなんて、どんな価値があっても最後はそんなもんですよ」
俺は、入社二年目のときにアテンドしたニューヨーク在住のナットさんというジャズマニアを思い出していた。
「今や日本こそがジャズ・カントリーだよ。こっちがおのぼりさんってわけだ」
成田空港で出迎えた俺に会うなり、笑いながらそう告げてきたナットさんは、東京中のレコードショップやライブハウスを朝から晩まで案内させた。ハイライトは、本場のジャズマンも唸るというオーディオ・システムによって、世界中にその名を轟かせている岩手県一関市のジャズ喫茶店「BASIE」への訪問だった。
「マワローも一緒に来るんだ」
ナットさんは、別のスタッフが担当予定だったツアーに強引に俺を通訳として同行させると、「お前に興味が無くてもいずれ絶対役立つ時がくる」と言い張って、東北新幹線に搭乗中の二時間半、延々と英語でジャズの歴史をレクチャーし続けた。メモを必死に取ったものの聞き取れない箇所も多くて、今では全く覚えていない。唯一覚えているのは、「BASIE」の店内で聴いたLPレコードの漆黒のビロードのような深い音の響きだけだ。曲はたしかシャンソンの「枯葉」を4ビートでアレンジしたものだったっけ。
ナットさんは満面の笑顔を浮かべながら帰国したが、その翌年に亡くなった。長年病に苦しんでいた彼にとって、日本旅行は最後の思い出作りだったのだ。未亡人からお礼代わりに送られてきたメールによると、彼女は膨大なレコード・コレクションを教会バザーで売り払って、孫の学費の足しにしたそうだ。eBayで一枚ずつ売っていけば、もっと高く売れたかもしれないけど、彼女にしてみればその手間よりさっさと処分したい気持ちの方を優先したかったのだろう。向原節子も同じことをしただけだ。悪いことでも何でもない。
「どうぞご確認ください」
今度は、向原節子から封筒を手渡された。中を確認すると紙幣が入っている。
「レコード・コレクションの買取り総額、16万円です。主人は『俺のコレクションにはお前が死ぬまで豪遊しながら暮らせるくらいの価値がある』なんて自慢していましたけど。もともと私は疑っていたんですよ。だってレコードなんて、もう誰も聴かないでしょう」
「最近はまたレコード・ブームみたいですけどね」
「町尾さん、ジャズはお詳しい? 主人は死ぬ前の5年間くらい『この言葉を覚えておけ』って繰り返し言っていたんです」
「どんな言葉だったんですか?」
「『1500と4000がオリジナルで揃っているのは世界でウチだけ』だって言ってました。『ジャズに詳しい奴に確認してもらえば分かる』とも」
1500と4000? オリジナル? 何のことか意味不明だ。
「申し訳ないですが、わたしには分からないです」
向原節子は「そうでしょうとも」という表情を浮かべた。
「いいんです。娘が呼んでくれた、ジャズに詳しいレコード屋さんがわざわざここまで来て一枚一枚調べた結果がこれなんですから。おそらく主人は勘違いしていたのでしょう。アルゴンキンへの支払分を残しておいてくれたのを感謝することにしますわ」
「それでは確認させていただきます」
俺が紙幣を数えはじめても、彼女は喋り続けた。
「今になって思うんです。主人の人生って何だったのかなって。会社の付き合いでお酒を少しやるくらいで、ゴルフも麻雀も嗜みませんでしたし。土曜日になると神保町まで出掛けてジャズのレコードを安く買ってきては、日曜日は朝から晩までずっとひとりで聴き入っていましたの。わたしが倒れる前の年に、ニューヨークにひとり旅したのが唯一の贅沢だったと思います」
確かにマンションの室内を見回しても、お金がかかっていそうな調度品は何ひとつ置かれていない。戦中派の家庭のLDKは往々にしてそんなものではあるけど、それにしても質素極まりない。
「金庫には何か価値ある物は入っていなかったんですか?」
「そこには昔から、主人のパスポートとこのマンションの権利証しか入っておりませんの。でも故障したみたいで開かなくなってしまって。業者さんを呼ぼうかと考えていたところなんです」
金庫に近づいてパネル面を眺める。テンキー方式で暗証番号は簡単に変更できそうだ。
「亡くなる前に功さんが暗証番号を変えられたんじゃないですか?」
「それはありえませんわ。あの人はあらゆる暗証番号をウチの電話番号の下4桁にしていましたから。『そんなのバレるわよ』って何度注意しても、『ラッキーナンバーだから』って絶対変えようとしなかったんです」
「そうなんですか」
お宝が入っている可能性はゼロか。
「でも私はいいんです。ここには五十年来のご近所さんが住んでいますし。助け合いながら慎ましく暮らしていくつもりです」
「そうですか」
俺はそろそろお暇(いとま)しようと、自分の財布を取り出して中身を確認した。3800円見つかった。しかしお釣りを支払おうと顔を上げたとき、向原節子の姿がどこにも見えないことに気がついた。慌てて室内を見回していると、下の方からゴソゴソと音が聞こえる。音の鳴る方角へと目を向けると、向原節子は床に倒れたまま白目を剥いて小刻みに痙攣していた。
「マズい!」
俺は室内電話の受話器を掴み取ると、「199」を押して向原節子の名と住所を告げた。
「いま救急車を呼びましたから」
呼びかけても反応がない。体を抑えつけても痙攣は止まらない。この状態がこのまま永遠に続くのかと観念した瞬間、サイレンが遠くから聞こえてきて、やがて救急隊が慌ただしく室内へと上がり込んできた。
救命士たちは向原節子を軽々と担架に乗せると、俺に告げた。
「お孫さん、ご同行願いします」
「えっ? 孫じゃないんですけど」
「とにかく来てください!」
パニクリながら電話台の引き出しの中を漁る。財布、手帳、保険証、キーケース。携帯電話がどうしても見つからない。まあ、これだけあれば何とかなるか。
俺はそれらをひと掴みすると、リュックの中へと投げ込み、外に運び出されていく担架についていった。
『インナー・シティ・ブルース』発売記念
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク