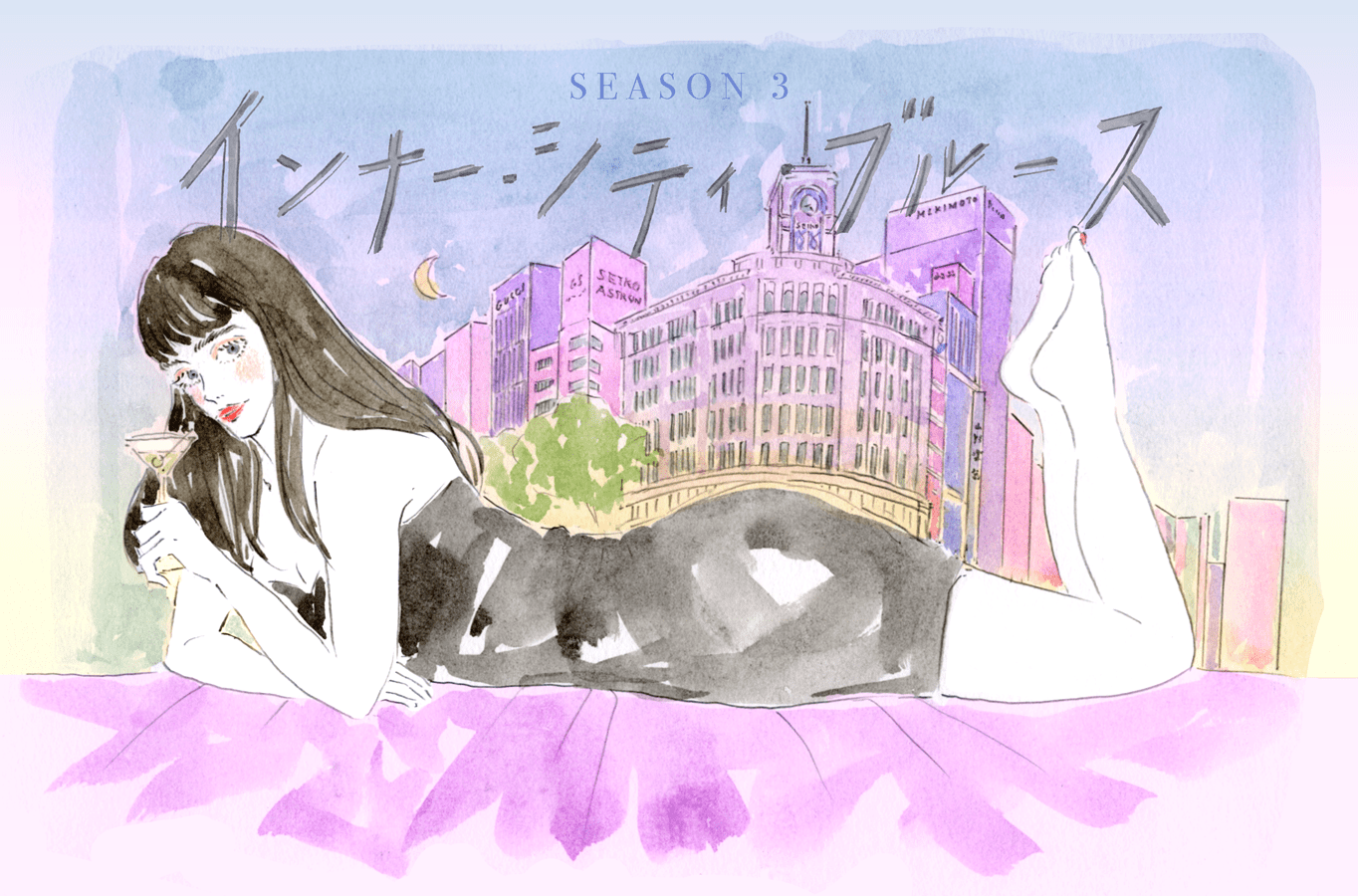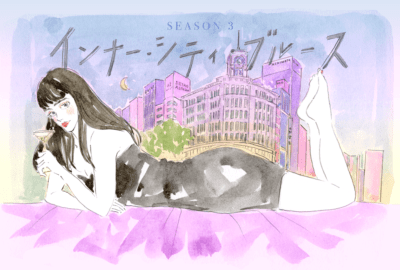毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3。銀座を本拠地に、ディストピア感が増す東京を東へ西へ行き来しながら繰り広げられる、変種のハードボイルド探偵小説をご堪能ください!
【あらすじ】主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)はアラサーのフリーター。銀座の外れにあるバー「アルゴンキン」での過去のツケ返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収する仕事を引き受けている。今回の標的は、人気俳優の立花英明。居場所を突き止め、本人と直接話すも、立花は不明な誰かから送られてきた自分のセクハラまがいの写真をマワローに見せ、それをもとにゆすられるのが不安だから支払いを待ってくれと言う。狡猾な立花はマワローに、その写真の後ろに写っている女性と会って、誰がこれを撮ったか覚えていないか聞いてくれと依頼する……
ご本人に直接お会いして、お話させていただけませんでしょうか。
そう書いたメールに、連峰陽子のマネージャーから了解した旨の返事があったのは、メールを送ってから二日後のことだった。待ち合わせ場所を見て、俺は驚いた。女優だというから、てっきり青山や赤坂のカフェを選ぶのかと思ったら、同じ港区でも新橋にある「ニュー新橋ビル」の喫茶店を指定してきたのだ。
ニュー新橋ビルが竣工したのは、今から50年以上も前の1971年のことである。戦後、焼け野原と化した新橋駅前に出現した巨大なヤミ市「新生マーケット」を収容するために建てられたという。旅行代理店時代に「昭和レトロビル探訪ツアー」を担当した経験があったので、俺自身はレトロなビルの面白さを知ってはいるけど、仕事でもないのにこんな場所を選ぶとは、只者ではないセンスの主だ。一体、どんな人なのだろう。
「楽さん、連峰陽子って知っています?」
囲間楽に訊いてみたけど、「うーん、一時期バラエティ番組によく出ていたみたいだけど」といったありきたりの言葉しか返ってこない。東京のありとあらゆる裏事情に精通している楽さんが、俺と同程度の知識しか持っていなかったのは意外だったが、考えてみたらそれも当然だった。バラエティ番組がテレビで放映されている時間帯、彼女は必ずどこかのバーで飲んでいるのだから。
連峰陽子がアルゴンキンの飲み代を支払ったのは一回きりだったので、ドロシー・ママのメモにも彼女についての記載は何もない。面会日の直前になって、俺は慌ててウィキペディアで彼女の名をサーチしてみた。
連峰陽子(れんほう ようこ、1977年11月16日 – )は、東京都大田区出身の女優(元・子役)、タレント。引っ込み思案の子どもだったが、幼稚園のお遊戯会で児童劇団主宰者にスカウトされて入団。6歳のときに舞台デビュー。翌年、初めてのテレビドラマ出演作『ズベ公ナース 少女鉄面皮伝説』で主人公の幼少時代を演じ、「天才子役」と騒がれる。13歳でジュニアアイドルとして売り出されるものの、事業に失敗した父親の連帯保証人だったために借金1億円を負う。しかし1993年に『トリプレッツ教師』で再ブレイク。ゼロ年代にはバラエティ番組にも進出し、奔放な言動から「人間凶器」の異名を轟かせた。現在は舞台を中心に活動中。
なるほど、1980年代前半から芸能界で活動していたベテランだから、待合せ場所のセンスが渋いのか。それにしても波乱万丈な人生を送っている人だ。
セレブなイメージがある銀座とは対照的に、新橋は庶民の繁華街とされているが、実際は隣り合っているので、アルゴンキンから歩いて15分もかからずに新橋駅前へと着いてしまった。スーツ姿の男女が慌ただしく行き交っている。日本初の鉄道駅であるため、駅前広場には蒸気機関車がシンボルとして置かれている。今月はちょうど鉄道開通150周年にあたるため、機関車のあちこちにはデコレーションが施されていた。
その広場に面してそびえ立っているのが、ニュー新橋ビルだ。アトランダムな大きさの格子で構成されたファサードは、ほかのオフィスビルにはないユニークなものだ。俺は、キャッシュ・ディスペンサー横にあるエントランスからビルの中へと入った。昼過ぎなのに、入り口横のバーでは客がすでに何人かいて、ビールや焼酎を飲んでいる。全員がラフな格好をしたお年寄りだ。彼らは会社を退職してから相当な年月が経過しているにもかかわらず、かつて勤務先があった新橋までわざわざ飲みに通っているのだ。俺には彼らが昭和の亡霊に見えた。
いや、彼らだけではない。新幹線の切符や金券を扱うディスカウント・チケット店、黒と茶の紳士靴ばかりが並ぶ靴屋、名刺をスピード印刷するコーナー、花屋(かつて男たちはここで花束を買ってから銀座へと繰り出していったのだろう)そしてエナジードリンクの品揃えが妙に充実したドラッグストア。この建物の中にある、ありとあらゆるモノが昭和の亡霊なのだ。
事実、ニュー新橋ビルはとっくにこの世から消え去っていてもおかしくなかった。2014年、東京都は老朽化が著しいこのビルに対して耐震調査を行った。結果は、震度6強以上の地震が起きたら倒壊・崩壊の恐れが強いというもの。ビルにとっては死刑宣告に等しい。この結果を受けて再開発組合が発足し、30階建ての高層オフィスビルへの建て替え計画が華々しく発表された。当初の竣工時期は2023年だった。
ところがいつまで経っても建設はおろか取り壊しすら始まらない。おそらく権利形態が複雑すぎて、テナントを退去させるのに難儀しているのだろう。そうこうしているうちに、新しいテナントが続々とオープンした。その殆どがマッサージ・パーラーだ。俺がエスカレーターで2階にあがってくると、ヒマそうに廊下に立っているアジア系女性たちがこぞって視線をこちらに向けてくる。
決まりが悪い思いをしながら、そのまま3階へと上がる。連峰陽子が指定した待ち合わせ場所のティーラウンジ「カトレア」は、昭和の雑誌を集めたブックカフェの隣にあった。
壁の一面は鏡張りで、ブラウン系のカーペットが敷き詰められた床には、大理石調の丸テーブルとレモン色をしたひとりがけ用ソファが埋め尽くすように置かれている。1971年のビル竣工以来、内装を変えていないのだろう。空気がうっすらと澱んでいることに俺は気がついた。この店は未だに分煙していないのだ。そのせいもあってか、客の平均年齢はおそろしく高い。
「町尾さんですか?」
声がする方向へと目を向けると、店の中央に置かれた黒いグランドピアノの向こう側から、ブラウンのショートヘアの女性が軽く手を振っていた。連峰陽子だ。ベージュ色のジャケットの下に白いシルクのシャツを着ている。マネージャーはおらず、ひとりきりだった。俺は、鉄道広場を一望できる窓際のテーブルへと近づくと、お辞儀をして彼女に名刺を手渡した。
「アルゴンキンでマネージャーをやっている町尾回郎と申します。こんな早くからいらっしゃっているとは思わず、失礼しました」
「ううん、いいのよ。職業病だから気にしないで」
連峰陽子ははにかむように笑った。仕事現場には早く到着することを心がけているのだろう。こんなしっかりした人なら、立花英明からの無理な頼み事を果たせるかもしれない。その前に自分の仕事を片付けてしまわなくては。俺は水が入ったグラスを運んできたウェイターにホットコーヒーを注文すると、あらためてアルゴンキンの現在の状況を説明し、未収金になっている飲食代を支払ってほしいことをお願いした。
「それでお幾らになるんですか?」
「3万4200円になります」
ちなみに明細は、バーボンのロックとシャーリー・テンプル一杯ずつ。おそらく前者を注文したのが酒癖の悪そうな立花で、ハリウッドを代表する天才子役の名を冠したカクテルを頼んだのが元天才子役の連峰だろう。
「わかりました」
「高いとは思わないのですか?」
請求金額を聞いた客から必ず言われる感想が、連峰陽子からあがってこなかったので、俺はつい逆に質問してしまった。
「だってあそこのお店は、お酒を飲ませるというより、人の繋がりを作る場所でしょう。しかたないわよ」
そう言うと、彼女はハンドバッグからルイ・ヴィトンの長財布を取り出すと、白く細長い指でぴったりの金額をテーブルに並べた。
「ありがとうございます」
「ああいうお店って、東京から無くなっちゃうのかしらね」
「『ああいう』というのはどんな意味ですか?」
俺の問いに連峰陽子は答えた。
「普通の暮らしを送っていたら、絶対会えないような類の大人の話を聞けるような場所。まあ、わたしは人の奢りで飲んでいただけだけど」
例の話を切り出すチャンスだ。
「奢りといえば、連峰さんは立花英明さんと親しかったようですね。アルゴンキンでお支払いされた時、ご一緒だったと聞いています」
「ああ、英明ね。舞台で共演したのをきっかけに、一時期は毎晩のように飲んでいたわね」
「実は先日、立花さんのところにも伺ったんですよ」
連峰陽子の瞳が悪戯っぽく光る。
「あの人の飲み代、とんでもない額なんでしょ?」
「ええ、具体的には言えませんが、かなりのものでした。その時に立花さんから相談を受けたのですが……」
「アルゴンキンについての相談?」
「いいえ、場所はアルゴンキンではなく、麻布の『アモーレ』という会員制バーです」
「ああ、アモーレね。あのお店はわたしが英明に教えてあげたの。でもあの人、今はブラックリストに載っちゃって、あそこではもう飲めないんじゃなかったっけ」
「わたしもその話は伝え聞いています」
そう、「アルゴンキンでこんな事をやったら出禁になるだろ」と語っていた立花は、実際はアモーレで出禁を食らっていたのだ。本人が語らなかった事実を、俺が知っていたのには理由がある。以前、未収金を取り立てた相手に、麻布でよく飲んでいるというアパレル会社の社長がいたので、彼に電話して「アモーレ」についてのネタを仕入れていたのだ。社長はこう語っていた。
「立花英明? あそこに通いはじめた頃にはもう出禁になっていたから一緒に飲んだことはないなあ。何でもいきなり素っ裸になって踊り出したみたいですよ」
写真に撮られた例の事件だ。
「そんな有名な噂なの?」
連峰陽子が驚いた様子で言う。
「いいえ、一部にしか知られていないと思います。5年前、立花さんはアモーレでブラックリストに載るきっかけとなった騒動を引き起こした。そのとき、あなたもご同席されていましたよね」
連峰陽子は記憶を辿るような表情をしばらく浮かべていたが、突然何かを見つけたような声をあげた。
「あ、あれがきっかけだったんだ! ええ、いました」
「立花さんがあなたの前でどんなことをしたかは覚えていますよね? 実はそのときの様子が、何者かに撮影されていたんです。その写真が4月頃、立花さんに突然送られてきた。立花さんは誰が撮影したのか、連峰さんならご存知なんじゃないかと気にされていました」
「町尾さん、わたしから聞き出してこいって英明に頼まれたのね?」
こういう時、嘘をついても上手くいかないので、俺は正直に答えた。
「はい、そんな話には関わりたくはなかったのですが」
「言っとくけど、わたしは犯人じゃないわよ」
「勿論わかっています」
「もしわたしがあんな写真を持っていたら、黙って送りつけることなんかせずに、ドラマの役をくれって具体的に脅しちゃうもの」
連峰陽子は自分が発したジョークにしばらく笑っていたが、次第に不安げな顔になっていく。
「誰か心当たりがあるようですね」
彼女は答えた。
「育(いく)です。わたしの弟」
連峰陽子は紅茶を口に運ぶと、訥々と語り始めた。
「わたしがアモーレを知っていたのは育があそこで働いていたからなんです。でもアルゴンキンみたいなお店とちがって、アモーレのVIPルームでは結構ヤバいことが行われていたみたい」
セックス、ドラッグ、金のやりとりか。
「育はそこで見聞きした秘密を、ひとに話すのが大好きで」
「弟さんから何か具体的な話を聞いたことがあるのですか?」
連峰陽子は困った表情をした。
「あいつ、何か見聞きするといつも電話してきて、ぺらぺら喋るんだけど、なぜか決まってわたしが台本を覚えようとしている時なのよね。わたしってセリフ覚えがとても悪いのよ。だから大抵スマホは遠くに放っておいたまま。ちゃんと聞いてはいないです。それにしてもなんで盗撮なんかしたんだろう?」
盗撮しなければいけなかった理由は、おそらくこうだ。連峰育はアモーレで仕入れた秘密を、ひとに話すだけでなく、情報屋に売っていた。そういう連中は信憑性がない情報には報酬を払わない。だから証拠としての写真が必要なのだ。それは写真週刊誌に掲載されるような、撮られる側も納得ずくの小綺麗なスクープ写真とは全く異なる、ダークでえげつないものだったりする。
しかし連峰育がこれだけ時間をおいてから金目当てで、姉の友人だった立花英明を脅迫するだろうか? 可能性は低い。立花に写真を送ってきたのは第三者だろう。
「あくまでも推測なのですが、弟さんは何かの問題に巻き込まれているんじゃないでしょうか。その結果、写真が外部に漏れたような気がします」
連峰陽子は不安げな表情を浮かべたまま、黙りこんでいる。
「弟さんは今もアモーレで働いているのですか?」
「いいえ、コロナのあおりでリストラされたの。今は実家で暮らしている」
相手が大人の社交場だろうが、ヤバいやりとりが行われる会員制バーだろうが、お構いなしに経営を悪化させる。COVID-19はある意味、平等主義者なのかもしれない。俺はウェイターが運んできたコーヒーをひとくち飲むと、彼女に提案した。
「わたしが弟さんのところに伺って話してきますよ」
「あら、関係ない人がそこまであいつの心配をしなくてもいいのに」
いや、関係大アリだ。写真の送り主を突き止めない限り、立花からは880万4682円の未収金を支払ってもらえない。
「わたしもご一緒したいけど、明日からしばらくの間、地方公演なの。育には町尾さんのことをラインで伝えておきます」
「ご実家はどちらですか?」
俺の問いに、彼女は知らない街の名前を答えた。
「糀谷(こうじや)です」
『インナー・シティ・ブルース』発売記念
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク