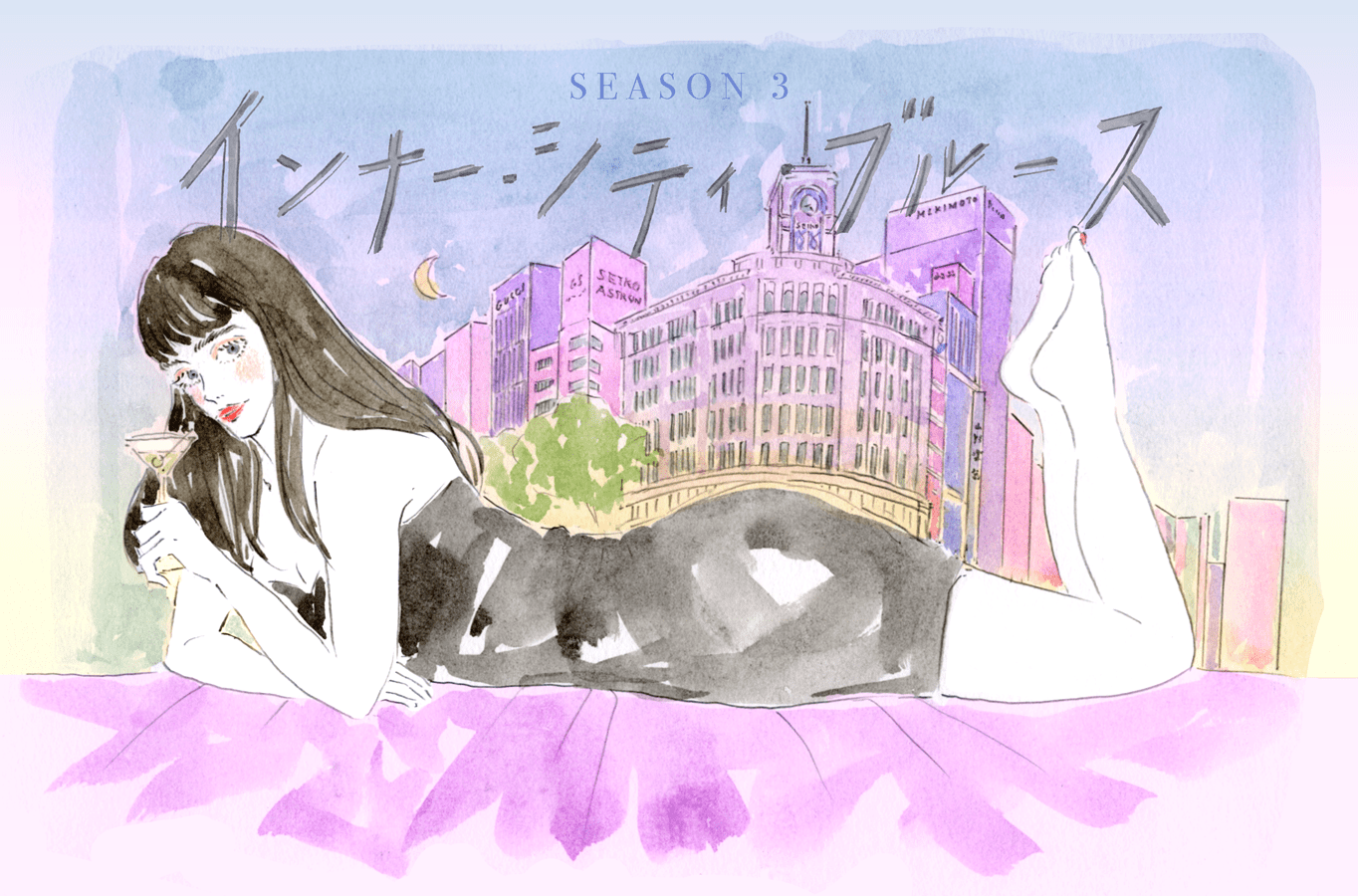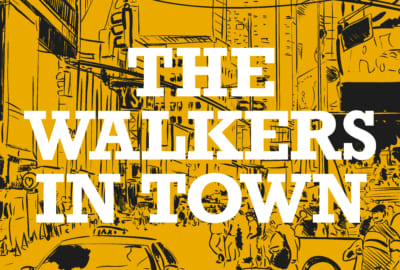毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3。銀座を本拠地に、ディストピア感が増す東京を東へ西へ行き来しながら繰り広げられる、変種のハードボイルド探偵小説をご堪能ください!
【あらすじ】主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)はアラサーのフリーター。銀座の外れにあるバー「アルゴンキン」での過去のツケ返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収する仕事を引き受けている。今回の標的に会うため、マワローは東京を代表する高級住宅街、松濤へ。日本で最もリッチな階級に属するであろう角松家の邸宅地へと足を踏み入れた。まるでホテルのような洋館の応接室で顔を合わせた当事者の角松とは話が噛み合わない。そこへいかにも上流階級然とした老婦人がワゴンを押しながら部屋に入ってきて───。
渋谷駅はその名の通り、谷底にある。だから駅からどこに行くにも宮益坂や公園通りといった坂道を登る羽目になる。そのひとつである道玄坂を登って頂上に辿り着くと、いつも賑やかだったこの辺りに寒々とした空気が漂っていた。今が真冬だからではない。ランドマークだった東急百貨店本店が1月末で閉店したからだ。
1967年の開業以来、東急沿線から買物に訪れる中産階級の市民たちにスペシャルな夢を与え続けた建物は、4月に解体工事が開始され一旦更地になる。夢の跡地には、商業施設やホテルなどからなる地上36階の複合施設「渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクト」が建てられるそうだ。開業は2027年を予定している。
東急百貨店の親会社である東急電鉄は「百貨店がテナントとして入るかは未定」としているが、これまで百貨店に出入りしていた協力業者を気遣って口を濁しているだけで、出店する気なんかさらさら無いことは明らかだ。何故ならこのプロジェクトには、共同事業主としてLVMHグループが参画しているからだ。
おそらく渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクトの商業棟には、百貨店の代わりにルイ・ヴィトンをはじめ、ディオールやセリーヌ、フェンディ、タグ・ホイヤー、モエ・エ・シャンドン、ドン・ペリニヨンといったグループのブランド旗艦店が軒を連ね、ホテルはジェットセット御用達のラグジュアリーホテルになるに違いない。
でもこのプロジェクトの成功を、俺は疑っている。日本が今後ますます貧しくなっていく中、こうしたハイブランドの商品を購入できる人口は減っていくはず。となると、おのずと海外からの旅行者をターゲットにせざるを得なくなるわけだが、元旅行代理店勤務の経験から言わせてもらえば、そうした人々に頼るのはあまりにリスキーすぎる。
かつて日本でブランド物をバカ買いしてくれた客の相当数は、ブランド直営店の出店が遅れている国に住むスーパーリッチだった。でも今ではLVMHグループはこうした国々にも直営店のオープンを加速させている。だから渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクトがオープンする2027年まで、直営店ゆえのスペシャリティを維持できるとは到底思えないのだ。まあ、一張羅のスーツで仕事をしている身としては、ジェットセット向けの施設がどうなろうと関係ないわけだが。
俺は、このプロジェクトの影響で4月から長期休館に入る「Bunkamura」の前を通り過ぎると、最初の信号を右折した。少し歩いただけでヴァイブスが変わってくる。それまで通りに漂っていた猥雑さは影を潜め、代わりによそよそしいほどの静けさを感じる。そう、ここは松濤。東京を代表する高級住宅街は、渋谷の繁華街のすぐ隣に位置しているのだ。
しばらく歩いた後、スマホを取り出して確認すると、Googleマップの自分の位置が行き先として設定した場所と重なっていることに気づいた。道沿いにそびえる高いコンクリート塀の向こうに何か見えないか背伸びしてみたが、鬱蒼とした高木ばかりで分からない。でもさらに歩いていくと、黒く塗られた金属製の巨大な門が見えてきた。門の横には表札がかけられている。
角松。
目的地に辿り着いたようだ。俺は表札の下に壁付けされているインターフォンのブザーを押した。
「はい」
男のくぐもった声がする。
「角松様、『アルゴンキン』の町尾回郎(まちお・まわろう)と申します。11時のお約束で伺いました」
電子錠が解除される鈍い金属音が響き渡る。俺は、門の脇にもうけられた通用扉を押しながら開くと、角松邸の敷地へと足を踏み入れた。
角松正樹。「アルゴンキン」のドロシーママのメモには、有限会社角松商事の経営者としか書かれていない。そんな名前の会社は聞いたこともなかったけど、囲間楽(かこいま・らく)に言わせれば、日本で最もリッチな階級はこういう人たちなのだそうだ。楽さんはこんな風に説明してくれた。
「この角松って人、たぶん明治維新の元勲の子孫だと思う。そういう人たちって先祖から受け継いだ財産を運用していれば余裕で暮らしていけるから働く必要なんて本当はないんだよね。でも無職だと格好つかないから、表向きは自分の資産運用会社の経営者って名乗っているわけ」
アスファルトで舗装された車路が、林を切り裂くように弧を描きながら奥へと伸びている。どれだけ歩いただろう。ようやく辿り着いた玄関には車寄せがあって、建物から張り出したキャノピーによって雨に濡れずに乗降できるようになっていた。まるでホテルのようだ。玄関横の呼び鈴を鳴らして、すこしの間待っていると扉が開く音がした。
「どうぞ」
男が招き入れる。顔は面長で無精髭をはやしている。年齢は三十代後半だろうか。ライトブルーのボタンダウンシャツの上に黒いスウェットを着ている。きっと彼が角松正樹だ。少し強張った表情をしているのは、これから金の話を聞くことになるので緊張しているのだろう。
角松は、俺に背を向けると黙って廊下の奥に歩いていってしまったので、俺は慌てて靴を脱ぎ、スリッパに履き替えると彼についていった。追いかけるように廊下の行き止まりに位置する部屋へと入る。大きさは20畳以上あるだろうか。壁にはウィリアム・モリス風の植物モチーフ柄のクロスが貼られ、板張りの床には毛足の長い大きなラグが敷かれていた。ガラステーブルの周りに革張りの椅子が並べられている。昔ながらの洋館の応接室だ。
俺は、胸ポケットにしまっていたレザーケースから名刺を一枚取り出すと、角松に手渡した。
「本日はお時間を頂き、ありがとうございます。アルゴンキンの町尾回郎と申します」
彼がひとりがけのチェアに座ったので、俺も向かいあわせのソファーに腰掛けた。さっそく要件を切り出すか。
「角松様、これまでアルゴンキンへのご愛顧ありがとうございました。実はこのたび事業を整理する運びになりまして、未収金をお支払い頂けないかお願いにあがりました」
角松は虚を突かれたような表情を浮かべながら言った。
「アルゴンキンって、バーの名前?」
何をトボけたことを言っているのだろう。
「もちろん。銀座6丁目の交詢ビルの向いのビルに入っているバーですよ。覚えていらっしゃると思うのですが」
記録によると角松は一時期、週3のペースでアルゴンキンに通っていた。
「俺、銀座のバーなんてコスパが悪いところに行く習慣ないんだけど」
この場に及んで、シラを切るつもりか。
「でも当方で台帳を確認したところ、これまでの飲食代が相当な額溜まっております」
「いくらになるんですか?」
「645万3400円になります」
角松が声を荒げる。
「知らねえよ! 俺、そんなぼったくりバーで飲んでねえし」
「失礼かもしれませんが、ご自分がなさった事は覚えていた方がよろしいかと思いますが、角松正樹さん」
角松の表情が固まる。そしてそのまま5秒ほど経過すると、大声で笑い出した。
「ハハハハハハ、俺、角松直樹(かどまつ・なおき)なんだけど」
直樹?
ちょうどその時、いかにも上流階級然とした老婦人がワゴンを押しながら部屋に入ってきた。髪は綺麗な銀髪で、青みがかった灰色のツーピースにパールのネックレスをしている。歳は70代半ばくらいに見えた。彼女は俺の前にティーカップを置くと、突然目をまっすぐ見ながら話しかけてきた。
「これは弟。正樹は兄の方です」
俺が戸惑っているのを察した角松直樹が助け舟を出す。
「母です」
母親に出てきてもらっても困る。俺が会いたいのは角松正樹なのだ。
「それでは正樹さんはご在宅でしょうか?」
老婦人が答えた。
「正樹は昨年亡くなりました」
「……それはご愁傷様です」
あれ、待てよ。俺は角松直樹に訊ねた。
「電話したのは2週間ほど前ですから、私がアポイントメントを入れた相手は正樹さんではなく、直樹さんということになります。心当たりがない人間と何故会おうと思ったのですか」
角松直樹は面倒くさそうに答えた。
「こういう場所に家があると、出費が色々かさんじゃってさ。うっかり振込を忘れていたら、業者に押しかけられたなんてことがしょっちゅうなんだよ」
松濤の富裕層ってそんなものなのか。
「まあ、会っていただけたのはありがたいのですが。それでは大変おそれいりますが、ご遺族として代金をお支払い頂けないでしょうか」
角松直樹が渋った。
「でも飲んだのは兄貴だろ。自分が飲んだわけじゃないからなー」
すると老婦人が口を挟んだ。
「成美さんに払いなさいっていえばいいじゃない」
「ええと、その方は正樹さんの奥様でしょうか」
俺が角松直樹に質問すると、老婦人は彼を阻むように先に答えた。
「ええ、そうよ。でもわたしは結婚に心配していたの。相手が芸能人なんて……」
芸能人?
角松直樹が俺に訊ねてきた。
「町尾さん、佐野成美って知っていますか」
名前の響きは何となく覚えているけど、どんな女優かは思い出せない。
「いいえ」
「世代的に地下鉄戦隊メトロンジャーはご存じですよね? あれに出ていたんだけどなー」
「まさかあの銀座オレンジの?」
『地下鉄戦隊メトロンジャー』とは、2004年(平成16年)2月15日から2005年(平成17年)2月6日までテレビ朝日系列で毎週日曜7:30 - 8:00に全50話が放送された、特撮テレビドラマ、および作中で主人公たちが変身するヒーローの名称である(ウィキペディアより)。
地底人と戦うスーパー戦隊を描いた同作最大の特徴は、東京メトロの全面協力で製作されたこと。そのためヒーローも丸の内レッド、東西ブルー、銀座オレンジ、千代田グリーン、半蔵門パープルといった地下鉄にちなんだ名前だった。
このうち女性ヒーローは東西ブルーと銀座オレンジの2名。東西ブルーがカツカレーと麻雀が大好きな、今でいうサバサバ系だったのに対して、銀座オレンジは蛯原友里を崇拝する女子力高めのキラキラ系だった。しかし番組後半、オレンジにはシリアスな展開が待ち受けていた。地底人との戦いのストレスで重度のショッピング中毒になった彼女は、カード破産寸前まで堕ちたのだ。あのエピソードでの彼女の演技はリアルすぎてヤバかった。
「わかりました。成美さんに会ってみます」
角松直樹が慌てはじめる。
「いや、それは義姉さんに申し訳ないよ。向こうも色々大変なんだから。まずこちらで支払えるか検討してみますよ」
老婦人が怒り出した。
「直樹、ダメよ。成美さんに払わせないと。それとね、町尾さんっておっしゃるの? あなた、あの人に会ったら聞いてくださらない? 勝手にこの家を売ろうとしたでしょうって」
何を言っているのかよく分からない。
角松直樹が口ごもりながらフォローしてくれた。
「この前、馴染みの不動産屋が『ここ、本当に売っちゃうんですか』って母に電話してきたんですよ。どうやら義姉さんがどこかの仲介屋に見積もりを依頼したのが巡り巡って、耳に入ってきたらしい」
ただでさえ松濤の一等地なのにこの広さ。ここを売却したら相当な金額になる。
老婦人が勝ち誇ったかのように喋り始めた。
「成美さんったら今でも自分がこの家の持分の6割を持っていると勘違いしているのよ。もう4割まで減ってしまったのにね。わたしだって自分の持分が半分以下だったらあの人に従うわよ。でも4割しかない人の言うことを聞くのはごめんだわ。可哀想に、正樹はあんな常識のない人と結婚したから金遣いが荒くなっちゃったのね。小さい時はおもちゃ屋さん……あそこ何ていう名前だったかしら」
彼女の独り言に、角松直樹が答えた。
「Paoだよ」
「そうだったわ、そのPaoに連れていって、何でも買ってあげるってわたしが言っても『ぼくは何もいらないよ、欲しいものはぜんぶあるから』って言うような子だったのに」
ふと角松直樹の方を見ると、目が死んでいる。これほどエキセントリックな母親の面倒を見るのはさぞ大変だろう。
「わかりました。成美さんに話してみますので」
「お願いするわ」
俺と老婦人が勝手に合意したので、角松直樹が困りはてたような声を出した。
「町尾さんに義姉さんの連絡先を教えるつもりはないですよ。彼女も困っちゃうだろうし」
俺は答えた。
「教えていただけなくても大丈夫です。勝手に突き止めるのが、こちらの仕事ですから」
実のところを言うと、俺はこのミッションに乗り気になっていた。中学生の頃、銀座オレンジのことが少し好きだったからだ。
『インナー・シティ・ブルース』発売記念
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク