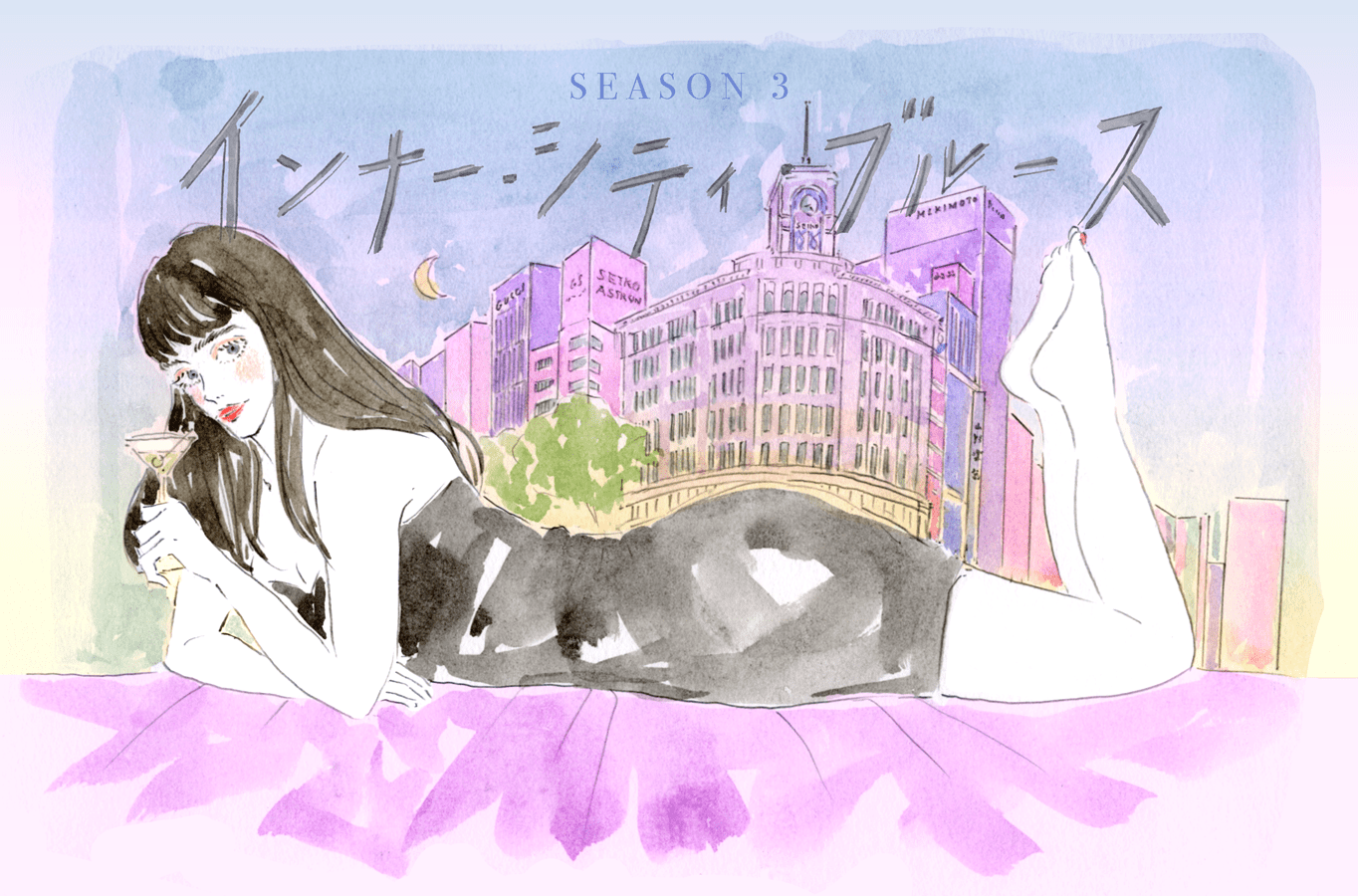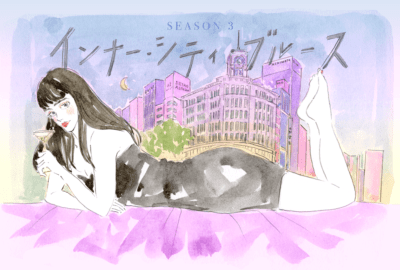毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3。銀座を本拠地に、ディストピア感が増す東京を東へ西へ行き来しながら繰り広げられる、変種のハードボイルド探偵小説をご堪能ください!
【あらすじ】主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)はアラサーのフリーター。銀座の外れにあるバー「アルゴンキン」での過去のツケ返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収する仕事を引き受けている。今回の標的は、西葛西に住む在日インド人コミュニティの大物、タイガー・カーン。彼に会うことはできたが、逆にある相談を引き受けてしまう。その条件は、カーンの姪、ケリーの身辺調査をしたら借金を分割ではなく一括返済するというもの。そこでマワローはカーンとケリーのひさしぶりの邂逅を画策するのだが───。
インターホンのブザーが鳴ったのは、夜7時ちょうどだった。スチール製の玄関ドアを開けると、そこには全身白装束の老人が立っていた。タイガー・カーンだ。
「こんばんは。わざわざお越し頂いてありがとうございます」
「確かにその通りだ、町尾さん。なんで君の話を聞くために、こんなところまで来なければいけないのだ」
機嫌が悪そうである。無理もない。西葛西の名士である彼にとって神楽坂は滅多に行くことがない完全なアウェー地帯だろうから。
「理由は後から説明します。まずは夕食をお召しあがりください」
「ここはレストランなのかね? 他に客はいないようだが」
「『ラ・パン・デ・デュー』という名前のビストロです。今日は、休業日だったのを特別に開けてもらいました」
タイガーさんがテーブルに座るのを待ってから、俺は一枚の紙を差し出した。
「スペシャルメニューです」
紙にはこう書かれていた。
スペシャル・ディナー
東京産クラフトビールと茨城旭村産トマトのレッド・アイ
熊谷市産小麦のクリームパン
千葉産馬鈴薯のポテトサラダ
いすみ市産牛乳のクリームシチュー
外房伊勢海老のエビフライ スパゲッティ・ナポリタン添え
レアチーズケーキ 抹茶アイス添え
小笠原父島の珈琲豆によるアイスコーヒー
「ほお」
メニューを見ただけで、タイガーさんはこれが凡庸な料理ではないと直感したようだった。スタッフが食事を運んでくると、彼は旨そうに次々と平らげていく。てっきりインド料理しか食べないんじゃないかというこちらの思い込みはあっさり裏切られた。かつて夜な夜な「アルゴンキン」に通ってビジネス・チャンスを獲得した人物だけあって、タイガーさんには様々な国の料理を食べる機会があったようだ。そんな彼も今日の料理には満足しているようだ。
「町尾さん、とても美味しかったよ」
「わたしが作ったわけではないので……いまシェフをお呼びします」
俺がシェフを呼ぶと、髪を後ろにきつく束ねた若い男がテーブルに近寄ってきた。
「ムッシュ・タイガー、リュカ・ファビアンと申します」
「フランスの方か。こちらこそ素材選びと見事な技術に感銘を受けました」
タイガーさんに、俺は尋ねた。
「本日のディナーに、ある共通点があることにお気づきになりましたか」
「さあ、強いて言えば日本で『洋食』と呼ばれている料理のような気がしたが」
「その通りです。実はすべて日本で発明された料理なのです」
俺は説明を始めた。
「最初に飲んで頂いたレッド・アイは、ビールとトマトジュースにスパイスを入れたカクテルです。1970年代後半に沖縄の米軍基地周辺のバーで作られたそうなので、歴史が浅い飲み物と言えます」
「あんパンが日本発祥なのは知っていたが、クリームパンもそうなのかね? 私はてっきりヨーロッパ由来のクリームパンにインスパイアされて、あんパンが作られたとばかり思っていたよ」
「わたしもタイガーさんと同じ認識だったのですが、事実は逆です。シュークリームの美味しさに感銘を受けた新宿中村屋の創業者が、あんパンの製造法を応用して1904年に販売を開始したそうです」
「なるほど。だがポテトサラダはどこか別の国で食べた記憶があるぞ」
「そうなんですか?」
予期せぬ質問に戸惑う俺に、リュカ・ファビアンが助け舟を出してくれた。
「19世紀にモスクワのレストラン『エルミタージュ』で、ジャガイモ、ライチョウの胸肉、固ゆで卵、グリーンピースなどをマヨネーズで和えたオリヴィエ・サラダという料理が人気を博したとの記録があります。正確なレシピはロシア革命で失われてしまったそうですが、味自体は『ロシア・サラダ』という名前で中東諸国に伝わりました。ムッシュ・タイガーが食べたのも中東のどこかの国ではないでしょうか」
「たしかにアブダビだったかもしれないな」
俺が補足した。
「ヨーロッパではジャガイモは酢で和えるのが一般的で、マヨネーズで和えるレシピは大正時代に日比谷の帝国ホテルが考案したものだそうです。クリームシチューも牛乳や生クリームをルーに使うこと自体はヨーロッパでも行われていましたが、小麦粉でとろみをつけるレシピは日本由来です」
「日本人はあまり牛乳を飲まない印象があるから意外だな」
タイガーさんの質問に、今度は答えることが出来た。
「その通り日本には牛乳を飲む風習は根付いていませんでした。しかしその反動で明治以降、子どものカルシウム不足を補うために教育現場で牛乳を飲むことが強く奨励されたのです。クリームシチューの直接的なルーツは、戦後まもなく学校給食の定番メニューになった脱脂粉乳産の「白シチュー」だと言われています」
俺の説明はメインディッシュへと突入した。
「エビフライの発祥は諸説ありますが、銀座の煉瓦亭がトンカツやメンチカツから着想を得て1900年に売り出したとの説が一般的です。付け合わせで添えられていたトマトケチャップで炒めたスパゲッティ・ナポリタンは、昭和20年代に、横浜のホテルニューグランドで出されたのが始まりです。ちなみに本場イタリアのナポリにはナポリタンと呼ばれる料理はありません」
「ナポリタンについては知っていたが、レアチーズケーキが日本発祥とは意外だったな」
リュカ・ファビアンが笑いながら答えた。
「フランスではこんなもの何処にも売っていませんよ」
俺が続けた。
「チーズケーキは本来ベイクドタイプです。クリームチーズと生クリームを混ぜて、ゼラチンを加えて冷やしたレアチーズケーキは、赤坂のトップスが1964年に発売したものです。抹茶アイスは言うまでもありませんね。アイスコーヒーは明治時代に神田の氷屋で売り出されたのが始まりと言われています。現在では世界中で飲まれていますが、それはスターバックスが商品展開した1990年代以降の現象でしかありません」
「よく調べましたな」
「ありがとうございます。いまお話したことは、前職の旅行代理店勤務時代に海外からの旅行者向けに企画した『洋食ツアー』のために仕入れた情報を元にしています。このツアーに参加したのは、すでに寿司や天ぷらといった日本料理の魅力を知っているフーディーばかりだったんですが、皆さんこぞって海外由来に見せかけて作られた『洋食』のオリジナリティに驚いていました。300年近く鎖国した後にいきなり開国した島国の人間だからこそ作れた料理と言えるでしょう」
リュカ・ファビアンが語りはじめた。
「わたし自身、日本で洋食の存在を初めて知って衝撃を受けたひとりでした。この味付けを逆にフレンチにフィードバックしてみたらどうなるか。それがわたしの料理のテーマになったのです。しかしそんな時、あるスタッフが新しいディレクションを提示してくれました。ウェイウェイ、こちらに来てください」
「ウィー、ムッシュ!」
快活な返事とともに、エプロンをしたケリーさんが現れた。手には深皿を手にしている。
「よろしかったらこちらも召し上がっていただけないでしょうか」
ウェイウェイさんがタイガーさんのテーブルに深皿を置いた。彼はそこに注がれていた茶色いペースト状の物体をスプーンで口に運んだ。
「カレーですな。これは……美味い!」
「ありがとうございます」
ウェイウェイさんは嬉しそうに微笑んだ。
「彼女はミャンマー出身です。当初テーブル・スタッフとして雇っていたのですが、ある日まかない料理を任せたところ、いきなりこれを作ったのです」
「わたし、日本に住んで長いので、日本のレトルトカレーも大好きなんです。最初はそういう味を作ろうと思ったんですけど、ここはフレンチ・ビストロなので材料が普段のものとはぜんぜん違っていて。パニくっているうちに、ミャンマーの味付けが混じってわけわかんなくなっちゃって」
「いや、これは他のどこにもない新しい美味しさだと思いますよ」
タイガーさんのフォローに、俺は言葉を続けた。
「このカレーの味に感心したファビアン・シェフは、これぞと思う客を選んで裏メニューとして振る舞うようになりました。すると今のタイガーさんと全く同じ感想を抱いた人が現れた。そろそろいいですよ」
奥からウェイウェイさんとは別の女性がこちらにやって来た。ケリーさんだった。手には別の深皿を抱えている。
これ以降のタイガーさんとケリーさんの会話は、ヒンディー語だったので何を言っているかさっぱり分からなかったのだけど、おそらくこんな感じだろう。
タイガー「ケリー、なぜこんなところに?」
ケリー「おじさん、今まで黙っていてごめんなさい。これまでの経緯を話すわね。ランチ・ミーティングで、この『ラ・パン・デ・デュー』に案内されて、偶然このまかないカレーを食べたの。そうしたら日本風でも欧州風でもない新しい味に衝撃を受けちゃって。作った人を呼んでもらったら、ここにいるウェイウェイだった。話していたら意気投合しちゃって。そうこうしているうちに、インドカレーのテイストを入れたらもっとスゴいものが出来るんじゃないかって思うようになったの」
タイガー「スゴいもの?」
ケリー「それで毎晩ここに通って、ウェイウェイとレシピを研究したの。お店のスタッフにはまかない、時には裏メニューとしてお客様に食べてもらいながらスパイスの調整を繰り返した。それで出来たのがこれ。まだ改善の余地があるけどね」
ケリーさんに促されて深皿のカレーを口に運んだタイガー「なんだ、これは!」
得意げなケリー「ね、イケてるでしょ?」
俺はタイミングを見計らって話し始めた。
「さっきフェビアン・シェフが話していた『新しいダイレクション』とは、移民によるオリジナル料理を指しているんだと思います。たとえばハムとチーズで作られたキューバン・サンドイッチという料理がありますが、キューバで発明されたものではありません。かといって、スパゲッティ・ナポリタンのように妄想で作られたものでもない。19世紀後半にアメリカのフロリダに出稼ぎ労働していたキューバ系移民が「ボカティート」と呼ばれる故郷のサンドイッチを、アメリカ風にアレンジしたものが始まりなんです。そのためキューバ本国ではポピュラーではありませんが、フロリダでは定番料理として愛されています」
ケリーさんが口を挟む。
「ハワイにも日系移民が創りだしたポケ丼やスパムむすびがありますよね。でも東京では赤坂の四川飯店が発明したエビのチリソース煮以来、ポピュラーな移民料理は作られていない。わたしたちみたいな人間がたくさん住んでいるのにね」
たしかにそうだ。東京都在住の外国人は58万人。全人口の約4%を占める。それなのに彼らは観光客と一緒くたにされ、見えない存在にされてしまっている。
「傲慢かもしれないけど、わたしとウェイウェイは、カレーでそれを変えたいんだよね。おじさんが反対するのはわかっている。インド人イコール・カレーという偏見で、カレーしか売るものがなかった状態からスタートして、頑張って別分野に事業を広げていったんだもの。わたしがカレーを作り始めたら後戻りしたように感じちゃうでしょ?」
タイガーさんが苦虫を噛み締めたような表情になる。
「決してカレー屋を見下しているわけじゃない。飲食業にはあまりに不確定要素が多すぎるんだ。為替レートや天候、人手不足、そして流行。あらゆるものに商売を左右されるからな。その証拠にちょっと前まであらゆるところにあったタピオカ・ドリンク店が今じゃ殆ど見当たらないだろう」
「あのー」
ウェイウェイさんが話し始めた。
「でもカレーには流行廃りはないと思いますよ。日本人はみんなどの国のカレーも大好きですし。町尾さんなんて、ミャンマー人しかいない父の店にわざわざミャンマー・カレーを食べに通ってくれているんですから」
彼女は、俺が無料だからリトル・ヤンゴンに通っていることを父親から聞いていないようだ。まあ黙っているか。
ケリーさんが加勢する。
「そうよ、カレーは日本の国民食よ。わたしとウェイウェイにカレーショップをやらせて、おじさん」
タイガーさんは腕を組んで暫く目を閉じて黙考し、やがてくわっと目を見開いた。
「会社を辞めることは絶対許さん」
「えーっ」
「まずは土日祝日限定でやってみろ。それでうまく行けそうだったら、そのとき将来を考えろ」
そう言い放つと、手を取り合って喜ぶ姪とその親友の姿をまともに見ること無しにスマホを見始めた。
「タイガーさん、本当にいいんですか?」
俺が彼に小声で尋ねると、タイガーさんは答えた。
「当たり前だろう。この味ならイケるかもしれない、いま西葛西に空き物件がないかチェックしているところだ。待てよ、キッチンカーという手もあるか。資金もさほどかからないしな……。というわけで町尾さん、支払いは今まで通り分割で支払うからよろしく!」
そりゃないよ。自腹を切ってこの店を貸切りにしてディナーまで提供してやったのに。店内の隅に行き、椅子に座り込んで呆然としていると、ケリーさんが話しかけてきた。
「町尾さん、本当にありがとうございます。わたしがここに通っていることを叔父に伝えるだけでいいのに、説得の機会までお膳立てしてくれて」
「いえいえ、こっちも人助けが趣味みたいなものなので気にしないでください」
また楽さんにいじられるな。気落ちしているのを察したのか、今度はウェイウェイさんが話しかけてくる。
「わたしのお父さんは、わたしたちを全面的に応援してくれるって言ってくれました」
「意外ですね。あんなにインドを嫌っていたのに」
「カレーを食べさせたら、あっさり意見を変えました。地元のいざこざとは関係無しに、日本では連帯しなきゃいけないって」
「アジア系アメリカ人みたいにですか」
現在アメリカでは、中国系や韓国系、日系の文化がひとつに溶け合って、Kポップを聴きながら飲茶を食べ、広島・長崎への原爆投下を人種差別の仕業と批判する「東アジア系アメリカ人」が生まれつつある。
ケリーさんが俺の言葉に応じた。
「わたしたちのこと、みんなが『南アジア系東京人』だって認めてくれたらいいんですけどね」
ウェイウェイさんが口を挟む。
「もしお店がオープンしたら、リトルヤンゴンと同じく未来永劫無料にしますから、ぜひ通ってくださいね」
何だ、俺がタダ飯なのを知っていたのか。ということは、彼女は俺が食事代無料であることにわざと触れずにタイガーさんを説得したことになる。このずる賢さがあるなら店も成功するかも。
リュカ・ファビアンが、俺のテーブルにもカレーを運んできた。ナンで掬って口に運ぶ。今日のカレーはタイガーさんの好みに合わせて作ったせいか、とてつもなく辛い。でもその辛さには、怖いものなしのポジティブなヴァイブスが漂っていた。
『インナー・シティ・ブルース』発売記念
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編
『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク