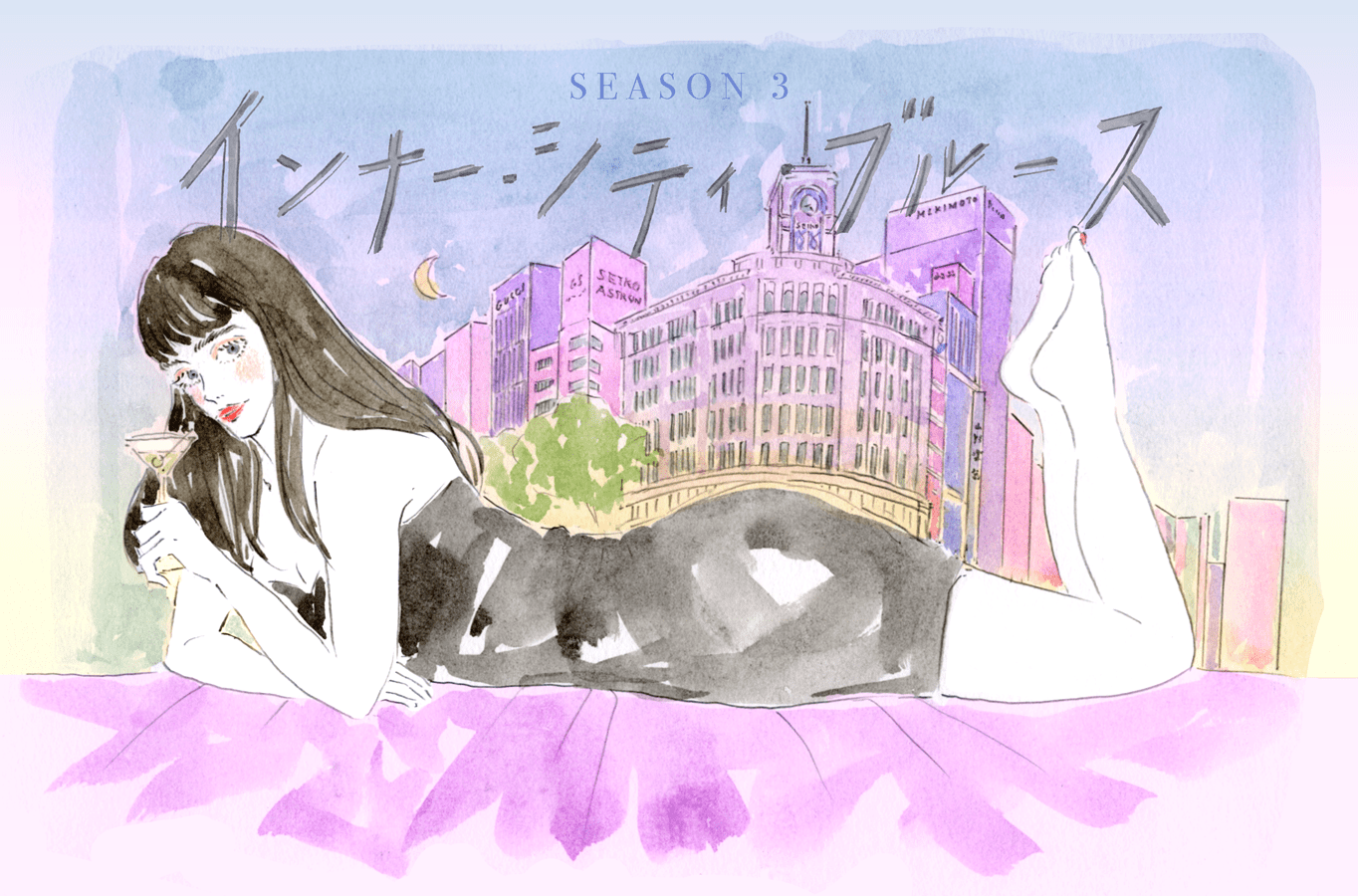毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3。銀座を本拠地に、ディストピア感が増す東京を東へ西へ行き来しながら繰り広げられる、変種のハードボイルド探偵小説をご堪能ください!
【あらすじ】主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)はアラサーのフリーター。銀座の外れにあるバー「アルゴンキン」での過去のツケ返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収する仕事を引き受けている。今回、最後となりそうな標的は、マワローが昔働いていた旅行代理店の先輩であり恩人でもある久世野照生。アルゴンキンにマワローを初めて連れてきたのも久世野だ。ということは、アルゴンキンに久世野のツケがあってもおかしくはない。しかしマワローは久世野ともう長い間会っていなかった───。
「次が最終試験だから」
囲間楽(かこいま・らく)はそう言うと、分厚い大学ノートを取り出して、バーカウンターの上に置いた。細長い指でページをパラパラとめくり、真ん中あたりでぴたりと止める。
「回収を頼みたい相手の未収金額は、345万9678円。これ、どういう意味かわかるよね?」
もちろん。2年半前、俺は今こうして座っている銀座のバー「アルゴンキン」に532万4649円のツケがあると楽さんから知らされた。そして自分と同じようにツケがある客から未収金を回収する仕事に半ば強制的に就かされたのだ。報酬は回収額の15%。俺はそこから部屋代や食費、水道光熱費を差し引いた残りの金でツケの返済を続けてきた。もし次に345万9678円を回収できたとしたら報酬は約51万円。これをそのまま楽さんに支払えば、ツケは全額返済ということになる。
「相手はどんな奴なんですか?」
「マワローの知っている人だよ。久世野照生(くせの・てるお)」
驚きのあまり声も出なかった。久世野さんは俺が働いていた旅行代理店、一橋ツーリストの先輩で、新卒社員の俺にビジネスについてのありとあらゆる事を教えてくれた恩人だ。このアルゴンキンに初めて連れていってくれた人でもある。だから考えてみたら、彼自身がこの店にツケがあっても全くおかしくはない。但しあの人とはもう長い間会っていない。
「久世野さんにはたしかにお世話になりましたよ。でも親の仕事を手伝うとか言って会社を辞めてしまってから音信不通になっちゃって。連絡先とか分かるんですか?」
「携帯番号だけだけどね。今も通じるかはわからないけど」
そう言うと、楽さんはノートを広げたままこちらに見せてくれた。ページには久世野さんの一橋ツーリスト時代の名刺がセロテープで無造作に貼られていて、さらにその名刺に青いインクで電話番号が殴り書きされている。
「こんなことなら久世野さんに最初に会いに行ったのに」
楽さんは微妙な表情になる。
「でもそう簡単に旧交を温めさせてあげるわけにもいかなかったんだよね。マワロー、ドロシーママのメモのことを知っているでしょ」
「もちろん」
アルゴンキンのママだったドロシーママは、生来の鋭い勘と長年にわたる夜の仕事を通じて培った観察眼で、常連客についての所感をこのノートに書きつけていた。
「ここにはこう書いてある。『頭がとことん切れてぞっとするほど冷酷。なぜ人の下で働いているのか不思議』だって」
ノートを覗き込んでみたけど、以前見た時と同じように楔形みたいな記号がびっしり書かれていて、何が書かれているのかはまったく分からない。ドロシーママは万が一、他人に覗かれても秘密を保持できるようにと、本人にしか読めない書体で文章を書いていたのだ。今まで俺は、楽さんが例の腕利き執事に解読させて、名前と素性がわかった順に回収を指示してきたのだとばかり思っていた。でも実は解読はとっくの前に完了していて、楽さんは俺のスキルアップを確認しながら、回収相手のレベルを徐々に上げていたのかもしれない。
「久世野さんがラスボスってわけですか」
「まあそんなところだね」
これまでツケを回収してきた相手の顔を思い出してみる。銀座の名門バーの常連客と言われて、誰もが想像するだろう政治家や会社経営者、売れっ子俳優といったセレブから、執事カフェの店長や地下芸人まで、職種も年代も国籍も多岐にわたっていた。そんな中、単なるサラリーマンが一番の難敵だったとは。
「ほかに手掛かりとかないんですか?」
念のため楽さんに訊いてみたけど、彼女はマティーニを飲みながら黙って首を振るだけだった。俺は久世野さんの名刺に書かれた電話番号を自分のスマホに登録すると、彼女に振る舞われるまま酒を飲んで、朝5時ちょうどにアルゴンキンを後にした。
いったん部屋で少し休むか。アルゴンキンが入っているビルが面した交詢社通りから、銀座六丁目の交差点に出る。真正面にはGINZA SIXが建っている。真冬の夜明け前に白い息を吐きながら、誰もいない銀座の目抜き通りを歩いた。
銀座四丁目の交差点を渡って、三越と和光の間を直進する。松屋銀座を横目に通り過ぎ、巨大な赤いクリップが目印の銀座・伊東屋のすぐ先の階段口から地下へと潜った。そのまま銀座一丁目駅の改札を抜けて有楽町線に乗りこむ。上り電車だったらこの時間でもそれなりに人が乗っているところだけど、乗り込んだのは下り電車だったのでガラガラだ。
アルゴンキンの革張りの硬いスツールとは座りごこちが段違いの座席に腰掛けた途端、猛烈な眠気が襲ってきたけど、中吊り広告に書かれた凡庸な宣伝文句を頭の中で読みあげながら睡魔と戦った。降車駅の池袋まで20分ほどしかないので、うっかりすると終点の和光市まで乗り過ごしかねないからだ。事実、アルゴンキンで囲間楽と飲み明かした翌朝、俺は何度もそうした失敗をしてきた。
それにしても彼女は一体何者なのだろうか。いつも黒い色の服を着た真っ白い肌をした女。インテリアデザイナーを名乗ってはいるけど、事務所として使っているはずのアルゴンキンにはパソコンも製図台も置かれていない。そもそもバーの薄暗い照明では壁クロスや家具の色味なんか判別しようがない。最近ではしょっちゅうスマホでどこかに呼び出されて、無言で店を出ていくと、いつのまにか戻ってきていて酒を飲んでいる。
つまり彼女にとってインテリアデザイナーは隠れ蓑にすぎず、人には明かせない仕事が本業にちがいない。但しこうした状況証拠から第一に想像できる類のムードはなぜか感じない。それでは彼女の正体は? これまで日々の忙しさにかまけて真剣に考えてこなかった謎について思いを巡らしていると、車内放送が「池袋」への到着を告げた。ちなみに東京メトロの車内放送は、フリーアナウンサーの森谷真弓という人がほぼすべてをひとりで担当している。おそらく日本で最も多くの人が正体を知らずに日常的に声を聞いている女性のはずだ。
時間はまだ5時30分を過ぎたばかりだったが、ターミナル駅である池袋には既にラッシュアワーが訪れていた。改札に押し寄せる人の波を掻き分けながら、東口に出る。池袋という街は紛らわしい。なぜなら西口のランドマークが東武百貨店で、東口のランドマークが西武百貨店だからだ。どちらも巨大デパートだが、特に西武池袋本店は伊勢丹新宿本店、阪急うめだ本店に次ぐ日本第3位の売り上げを誇る人気店である。池袋と並ぶ東京西部の繁華街、渋谷の象徴的なデパートだった東急百貨店が本店、東横店ともども改装が理由とはいえクローズしてしまったのとは対照的だ。
自由が丘や田園調布、二子玉川といった名の知れた高級住宅街を沿線上に従えていた東急百貨店ですら集客に苦慮していたのに、西武百貨店はなぜ今も健在なのだろうか。実は資産があってもそれを見せびらかさないサイレント富裕層が多く住む「第一山の手」住民の相当数がこのデパートの熱心なカスタマーなのだ。
西武流通グループを、創始者であり父だった堤康次郎を受け継いだ堤清二はこの事実を知ると、呉服屋を母体とするライバル店が手を出さなかったジョルジオ・アルマーニやラルフ・ローレンといった欧米ブランドとの提携を敢行。デビュー間もない川久保玲や山本寛斎の服もいち早く店頭に置いた。同時に「不思議、大好き。」や「おいしい生活。」といったキャッチコピーを用いた巧みなイメージ戦略で西武百貨店のイメージを上げていき、1980年代初頭には最先端の文化施設の座に押し上げたのだ。
セゾングループと名を改めたグループは西武百貨店に加え、西友、パルコ、ファミリーマート、無印良品、ロフト、WAVE、シネセゾン、ダンキンドーナッツ、そして吉野家と拡大し続けたが、バブル崩壊がもたらした不動産事業の破綻とともに終焉を迎えた。たとえ無理やりでもイメージを浴びせ続ければ、やがて日本人全員が第一山の手住民級のセンスを獲得して、セゾン文化を享受するようになる。堤清二のそんな夢にも似た構想は失敗に終わったのだ。
但しグループ解体後、西武百貨店を買収したセブン&ホールディングスは、すべてのはじまりだった池袋西武を支えるコアな顧客層の豊かさまで実態がないものと捉えてしまった感がある。商品単価さえ下げれば売り上げがアップするだろうと、食料品売り場にプライベートブランド商品をフィーチャーしたりして、デパートの価値を毀損してしまったのだ。その結果、事業を売却せざるをえなくなったのは当然の帰結といえる。新しくオーナーになったヨドバシカメラはどのようにしてこの巨大店舗を再度上昇気流に乗せるつもりなのだろうか。ひとつだけはっきりしているのは、品揃えが最高だった大型書店「リブロ」が店内に復活する可能性がゼロに等しいということだ。
そんな西武池袋本店から真っ直ぐに伸びるグリーン大通りをしばらく歩くと、俺はサンシャイン大通りへと入った。ファストフードや居酒屋、ゲームセンター、そしてアニメや声優関係のグッズ店が並ぶ、ある意味最も池袋らしい通りだ。路上にはチューハイの空き缶や煙草の吸い殻が散乱している。オールナイト営業を終えたカラオケ店の前で、女の子たちのグループが名残り惜しそうにおしゃべりをしていた。
そのまま通りを直進して首都高5号線の高架を潜ると、そこはもうサンシャインシティだ。オフィスや商業施設、ホテル、劇場や水族館まで入ったこの複合都市施設もまた堤清二の構想によるものだ。エントランス的役割を果たしている建物は、サンシャインシティアネックスと名付けられている。実は施設本体は道路を挟んだ向こう側に位置するため、ここから歩行者を一旦地下に潜らせて道路を渡らせる役割を果たしている。現実を可視化すると「駅から遠い」と思われるため、カモフラージュしているというわけだ。これもひとつのイメージ戦略である。
サンシャイン大通りの歩行者の大半はこの建物の中に入っていくのだけど、俺の目的地は通りの終点に位置する小さな雑居ビルが軒を連ねている一角にあった。俺の部屋がその中のひとつの屋上にあるからだ。この部屋は元々ビルを建てたオーナーが、建物に立ち寄った際に事務作業のために使っていた倉庫だったらしい。それを無理やり改装したため、ベッドと机がぎりぎり置ける4畳半ほどのスペースしかない。その分、家賃が信じられないほど格安だったので、上京して以来、俺はここで暮らしていた。玄関ドアを開けてベッドへと倒れ込む。いつものように首都高の騒音がハンパなかったけど、慣れっこになっているので、そのまま眠りに落ちてしまった。
高さ240メートルのサンシャイン60を筆頭とするビル群に囲まれてはいるものの、俺の部屋は屋上にある。しかもビルとの間にはそれなりに空間があるため、陽がのぼってくると強烈な光が窓ガラスから降り注いでくる。だからいくら眠かろうが、8時過ぎには起きてしまう。スマホを手に取ると、ショートメールに着信があった。
「マワローひさしぶり」
送り主は久世野照生だった。なぜ俺の携帯番号を知っているんだろう? とにかく電話しなくては。電話番号をタッピングしようとした途端、新着メッセージが送られてきた。
「直接は話したくない」
「今まで何をしていたんですか」
「それは言えない」
「なんで連絡をくれたんです?」
「そろそろアルゴンキンの未収金を回収しようとするんじゃないかと思ったからね」
完全にこちらの行動を読まれている。どういうことだ? 俺は返信を送った。
「どうして俺の仕事が分かったんですか?」
「俺も囲間楽に働かされていたから」
なんだって? 向こうからまたショートメールが送られてくる。
「今なら間に合う。すぐに東京を離れろ。これ以上あの女に関わるのはやめておいた方がいい」
「ちょっと待ってください。久世野さん、未収金の件は横に置いておいて、お話できませんか?」
するとメールはそれっきり途絶えてしまった。「直接は話したくない」ではなく本当は「直接は話せない」のではないか。なぜなら囲間楽に居場所がバレてしまうから。久世野さんはツケ以外の理由で以前から彼女にマークされ続けていたにちがいない。ということは、俺は囮に使われていることになる。
とりあえず俺はシャワーを浴びることにした。タオルで体を拭き、電動ケトルで沸かしていたお湯をインスタントコーヒーに注ごうとした瞬間、新着メッセージが送られてきた。そこにはこう書かれていた。
「今夜の零時ちょうどに雑司ヶ谷霊園に来てほしい」
小説『インナー・シティ・ブルース』シーズン1
渋谷編:ウッパ・ネギーニョ①
渋谷編:ウッパ・ネギーニョ②
豊洲編:スケアリー・モンスターズ①
豊洲編:スケアリー・モンスターズ②
八重洲編:ゴーイング・アンダーグラウンド
浅草〜三ノ輪編:It’s Okay(One Blood)①
浅草〜三ノ輪編:It’s Okay(One Blood)②
新大久保〜新宿編:タイニー・ダンサー①
新大久保〜新宿編:タイニー・ダンサー②
小石川後楽園編:ファミリー・アフェア
赤坂〜六本木編:シャンデリア①
赤坂〜六本木編:シャンデリア②
葛西臨海公園編:ヘイ、ナインティーン〜チェイン・ライトニング
神田明神編:ウェディング・ベル・ブルース①
神田明神編:ウェディング・ベル・ブルース②
小説『インナー・シティ・ブルース』シーズン2
フューチャー・ショック 大江戸線 前編
フューチャー・ショック 大江戸線 後編
チェンジズ 目黒通り編
サタデイ・イン・ザ・パーク 代々木公園編
エレファント・トーク 吉祥寺編
愚かなり我が心 麻布新龍土町編
ハネムーン 湾岸道路編
サムシング・イン・ジ・エアー 押上・浅草編
ハイチ式離婚(アイ・ウィル・セイ・グッドバイ) 新宿東口編
クール・イン・ザ・プール ホテルニューオータニ編
ザット・レディ パート1&2 駒沢オリンピック公園編
ある愚か者の場合 品川編
ロボット 都内某所編
ゴースト・タウン ① 明石町・千駄ヶ谷
ゴースト・タウン ② 目黒通り・池袋
ゴースト・タウン ③ サンシャインシティ
バック・トゥ・ザ・ワールド 西原
小説『インナー・シティ・ブルース』シーズン3
イントロダクション:ファウンド・ア・ジョブ(銀座)
雨に微笑みを(丸の内線) 前編
雨に微笑みを(丸の内線) 中編
雨に微笑みを(丸の内線) 後編
オール・シングス・マスト・パス(千代田線)前編
オール・シングス・マスト・パス(千代田線)中編
オール・シングス・マスト・パス(千代田線)後編
サムシン・エルス 前編(都営三田線)
サムシン・エルス 中編(都営三田線)
サムシン・エルス 後編(都営三田線)
リキの電話番号 前編(日比谷線)
リキの電話番号 中編(日比谷線)
リキの電話番号 後編(日比谷線)
プライベート・アイズ 前編(都営浅草線)
プライベート・アイズ 中編(都営浅草線)
プライベート・アイズ 後編(都営浅草線)
プライベート・アイズ 完結編(都営浅草線)
ア・ハウス・イズ・ノット・ア・ホーム 前編(銀座線)
ア・ハウス・イズ・ノット・ア・ホーム 中編(銀座線)
ア・ハウス・イズ・ノット・ア・ホーム 後編(銀座線)
ホット・スタッフ 前編(東西線)
ホット・スタッフ 中編(東西線)
ホット・スタッフ 後編(東西線)
リヴィング・フォー・ザ・シティ 前編(南北線)
リヴィング・フォー・ザ・シティ 中編(南北線)
リヴィング・フォー・ザ・シティ 完結編(南北線)
PROFILE
長谷川町蔵
文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。
https://machizo3000.blogspot.jp/
Twitter : @machizo3000
『インナー・シティ・ブルース』
Inner City Blues : The Kakoima Sisters
2019年3月28日(木)発売
本体 1,600+税
著者:長谷川町蔵
体裁:四六判 224 ページ 並製
ISBN: 978-4-909087-39-3
発行:スペースシャワーネットワーク